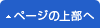家を売りたい!家の値段を知るための「不動産査定」とは?
家を売却することを考えたら、まず気になるのは「いくら」で売れるのかということ。一般的に家の価格を確認する方法は不動産会社に「査定」を依頼することになります。
「査定」には「簡易査定(机上査定)」と「訪問査定」の二種類があり、主な違いは以下のとおりです。
現地を見学せずに、住所や間取りなどの物件情報、類似物件の販売事例、景気の動向などデータから算出する方法です。現地調査をしないため、個別要因を踏まえないおおよその金額を算出します。この「机上査定」の次に「訪問査定」を依頼するのが一般的です。
現地を訪れ、家の状態や道路と敷地の位置関係、境界の有無など、現地調査により精度の高い査定価格を算出します。この時の金額が実際に売り出す金額を決める元になります。まずは複数の不動産会社に簡易査定を依頼し、そこから2~3社を選んで訪問査定を依頼します。
マンションならば、リフォームをしていたり、使い方に問題があったりして条件が大きく異なる場合を除けば、同じマンションの異なる部屋の売却事例から机上査定だけで正確な査定金額が算出できることもありますが、土地や中古戸建の場合は、実際の物件の状態を調査しなければ、ほぼ正確な査定金額を導き出すことは困難です。
不動産査定の流れ
| ①ネット上の一括査定で複数の不動産会社に簡易査定を依頼する |
|---|
| 簡易査定ならば、当日から数日中までには連絡があります |
| ②簡易査定の結果を基に不動産会社を選択し訪問査定を依頼する |
| 査定内容や対応の良さそうな不動産会社を2~3社選んで依頼する |
| ③訪問日時を決める |
| 立ち合いできる日でスケジュールを調整します |
| ④現地調査を行う |
| 周辺環境の確認も含め調査は数時間かかります |
| ⑤必要書類を確認し用意する |
| 書類を早く揃えておけば、その分査定もスムーズに行われます |
| ⑥査定結果を聞く |
| 査定結果だけではなく、不動産会社のレベルや対応力などを総合的に判断し、安心して取引できる不動産会社と媒介契約を交わします。 |
査定価格の算出方法
査定価格を算出するためには、まず対象不動産の評価を行います。宅建業者や金融機関が不動産の評価を行う際に使う方法が、「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」の3つです。評価対象の不動産の種別により最適な評価法を選択しますが、それぞれ次のようなポイントがあります。
1.原価法
現在、評価したい建物と同等の建物を新築した場合の価格(再調達価格)を計算し、経年による建物や設備の劣化を評価額から差し引く(減価修正)ことで対象不動産の試算価格を求める評価法。
対象不動産が「建物」または「建物およびその敷地」である場合、再調達価格の把握と減価修正を適切に行なうことができるケースで有効な方法で、主に一戸建ての評価に使用されます。
なお、このような原価法による試算価格を「積算価格」といいます。
建物評価額(円)
=建築単価(円/㎡)×建物面積(㎡)×(耐用年数− 経年年数)/耐用年数
例.自己居住用の木造一戸建て(築12年、総面積120㎡)
・建築単価15.65万円/㎡
・木造一戸建ての耐用年数33年
再調達価格:15.65万円/㎡×120㎡=1,878万円
減価修正 :(33年−12年)/33年≒0.64
積算価格 :1,878万円×0.64≒1,202万円
建物評価額:1,202万円
※建築単価は国税庁サイトの「建物の標準的な建築価額表」を参照
※耐用年数は国税庁サイトの「耐用年数表」を参照
(所得税法施行令第85条より自己居住用の耐用年数は事業用×1.5として計算)
主な建物の耐用年数
| 構造 | 事業用(賃貸) | 自己居住用 |
|---|---|---|
| 木造、合成樹脂造 | 22年 | 33年 |
| 鉄骨造(骨格材肉厚3㎜超) | 27年 | 40年 |
| 鉄骨造(骨格材肉厚4㎜超) | 34年 | 51年 |
| れんが造、石造、ブロック造 | 38年 | 57年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 | 70年 |
また、対象不動産が「土地のみ」である場合においても、路線価や最近造成された造成地などのように、再調達原価を適切に求めることができる場合は原価法の適用が可能です。まずは路線価による評価を算出し、実際の取引事例により比較検討する方法が理想です。
土地評価額=実勢価格(時価)による単価(円/㎡)×土地面積 (㎡)
※路線価は実勢価格(時価)の80%とします
例.自己居住用の木造一戸建て(築12年、総面積120㎡)、土地面積140㎡
・建築単価15.65万円/㎡
・木造一戸建ての耐用年数33年
・路線価20万円/㎡
建物評価額 =15.65万円/㎡×120㎡×(33年−12年)÷33年
≒1,202万円
土地評価額 =20万円/㎡÷80%×140㎡
=3,500万円
査定地評価額=1,202万円+3,500万円
=4,702万円
2.取引事例比較法
査定地周辺のエリアにおいて条件の類似する複数の成約事例地を選択し、形状、環境、方位などの個別要素を比較検討して、売却理由など個別事情による修正を行う評価法。主にマンションや土地の評価に使用されます。
この評価法を使用するポイントは成約事例地の選択にあり、宅建業者ならばレインズ(不動産情報のデータベース)の成約情報を活用します。ただし、条件の類似する成約情報が少なかったり、成約までの期間が確認できなかったりと、慎重な価格決定が必要となります。なお、このような取引事例比較法による試算価格を「比準価格」といいます。
評価額=事例地の単価(円/㎡)×面積(㎡)×補正率
※補正率は100%を基準に、案件ごとの個別要素、個別事情を考慮して掛け率を決定します。
例.土地(面積140㎡)
過去の成約事例
土地面積160㎡、成約価格4,000万円
→1㎡あたり25万円
比準価格=140㎡×25万円/㎡
=3,500万円
3.収益還元法
対象不動産が賃料により将来生み出すと予想される純利益から現在の不動産価値を決定する評価法。主に収益物件の評価に使用されます。
この方法は「収益性」のみ重視しており不動産の個別要素が全く反映されないため、評価額を上げるには賃料の一定額以上の上昇が必要となります。また、期待する還元利回りの設定値によって評価額が大きく変わります。
評価額=1年の純利益÷還元利回り×補正率
※1年間の純利益=1年間の総収入―1年間の諸経費(管理費など)
例.家賃12万円/月、管理費等2万円、還元利回り8%、補正率100%
年間純利益=(12万円×12か月)-(2万円×12か月)
=120万円
評価額 =120万円÷8%×100%
=1,500万円
収益還元法で適切な価格を導くための還元利回りを設定するのに注意すべきこと
・空室リスク
中長期の入居率、家賃変動率の予測が特に重要
・修繕計画
外壁、屋根、給排水設備等の将来的な修繕計画が重要。過去の修繕履歴の確認は必須
・管理費・修繕積立金改定予定(区分所有建物の場合)
修繕積立金累計額、大規模修繕工事の実施状況の確認は必須
査定を依頼する時のポイント
1)必要書類を揃える
本人確認書類、物件の登記済権利書、固定資産税納税通知書、公図、壁芯面積(専有面積)が分かる資料(マンションの場合)など。
2)不具合や修繕の必要性の有無
値下げ要因や、売却後のトラブル回避のために、家の不具合や修繕状況を不動産会社に伝えます。不具合や瑕疵がある場合は、それぞれ修繕可能かどうか確認します。
不具合や瑕疵について契約書に明記しておかないと、売主は不適合責任を負うことになります。
3)リフォームやクリーニングの必要性
売主がリフォームやクリーニングをして家の状態を良くしたとしても、買主が自分好みのリフォームを計画している場合は無駄になるので、余計な出費を増やさないよう慎重に検討する。
リフォームやクリーニングの必要性については、売却を依頼する不動産会社に相談するのが良い。
4)境界線が明確かどうか(土地・一戸建ての場合)
一戸建てや土地の売買において一番多いトラブルが境界線に関することです。査定後に調べることも可能ですが、問題となる可能性があるかどうか最初に把握しておくことが重要です。
境界線に問題が無ければ査定時間も短くなります。
まとめ
査定はあくまでも家を売るための前のステップです。家を売るために不動産会社に売却活動を依頼(媒介契約)することになりますが、不動産会社の中には売主と媒介契約を交わすために、相場より高めの査定額を提示してくるような会社も存在します。そのような業者に依頼してしまうと適正な価格で販売活動がされないため、家もいつまでも売れずに結局値下げすることになってしまいます。間違った選択をしないためにも査定額の根拠を業者にしっかり確認し、それに対して的確に応えられる不動産会社を選ぶことが大切です。
①査定価格とその根拠
②見込み客の有無
③集客方法
④対象エリアの知識
⑤会社の強み(セールスポイント)
⑥売却達成のための戦略
住建ハウジングが売却に強い3つの理由
- 理由1 東京都内にこだわり続けた揺るぎない実績
- 理由2 物件の魅力を最大限に引き出すノウハウ
- 理由3 業界トップクラスの集客力とネット番組の圧倒的な反響
60秒でカンタン!問い合わせ【無料査定】
査定対象は東京都心部のみとなります
- Step1 ご相談
- Step2 現地調査
- Step3 媒介契約
- Step4 販売活動
- Step5 売買契約
- Step6 決済登記
その他売却について
【区ごとの一戸建て相場と事例】
【区ごとのマンション相場と事例】

 0120-172-111
0120-172-111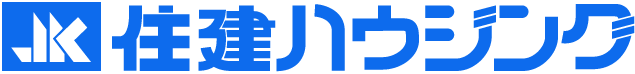
 0120-172-111
0120-172-111
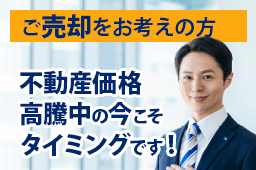
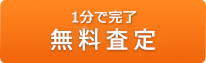
 マンション売却にかかる税金はいくら?
マンション売却にかかる税金はいくら? おさえておきたいマンション売却の流れとは?売却時のポイントやコツも紹介
おさえておきたいマンション売却の流れとは?売却時のポイントやコツも紹介 固定資産税はいくら?計算方法と「戸建て・マンション」などによる違い
固定資産税はいくら?計算方法と「戸建て・マンション」などによる違い