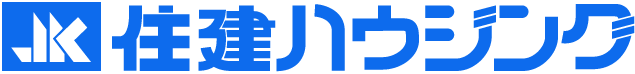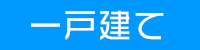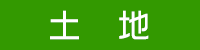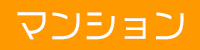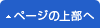不動産取得税 

有償・無償を問わず、土地や家屋を取得した時にかかる税金

不動産取得税とは
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、土地や家屋(建物)を購入したり、贈与を受けたり、家屋を新築したりするなど、不動産を取得した人に対して一度だけ課税される地方税(その不動産の所在する都道府県が課する税金)です
『取得』とは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。また、取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれかであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
これは、不動産の取得という事実に着目して課税される「流通税」の一種で、毎年課税される固定資産税とは異なります。
不動産取得税の計算式
不動産取得税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率(4%)
不動産取得税の課税標準額について
課税標準額には、実際の購入価格ではなく、原則として固定資産税評価額が用いられます。新築の家屋で固定資産税評価額が算出されていない場合、家屋であれば、購入価格の6割程度の金額を算出することで、おおよその不動産取得税の金額を試算することができます。
不動産取得税の税率について(標準税率と特例)
標準税率は ですが、現在は土地と住宅の取得について、税負担を軽減するための特例が適用されています。
| 不動産の種類 | 軽減税率 | 適用期限の目安 |
|---|---|---|
| 土地(住宅用地) | 3%(本則:4%) | 令和9年3月31日まで |
| 住宅(居住用) | 3%(本則:4%) | 令和9年3月31日まで |
| 住宅用以外の家屋(店舗・事務所など) | 4%(軽減措置なし) | — |
※上記の期限は変更されることがあるため、最新の情報は取得時の各都道府県の税制を確認する必要があります。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には、マイホームの取得を支援するため、税額が大幅に軽減される特例措置があります。これらの軽減措置を受けるためには、取得者が都道府県税事務所に申告する必要があります。
①建物(新築住宅)の軽減措置
一定の要件(床面積の制限など)を満たす新築住宅を取得した場合、建物の課税標準額から1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。
建物の不動産取得税額=(固定資産税評価額−控除額)×3%
②土地の軽減措置
宅地(または宅地並み)の取得に対しては、以下の優遇措置が適用されます。
- 課税標準の特例:土地の固定資産税評価額が1/2になる
- 税額の軽減(控除):以下のAまたはBのいずれか高い方の額が税額から控除される
A:45,000円
B:(土地1㎡あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積の2倍<上限200㎡>)×3%
これらの軽減措置を適用すると、土地にかかる不動産取得税はゼロになるケースが多くあります。
不動産取得税の納税の時期
不動産を取得してから、おおむね数ヶ月後(4ヶ月〜1年程度)に、都道府県の税事務所から納税通知書が送付されます。通知書に記載された期限までに、金融機関などで納付します。
軽減措置を適用するためには、納税通知書が届く前に取得後60日以内など、都道府県が定める期間内に申告手続きを行う必要があります。
マンション(建物)の各住戸の課税標準額(固定資産税評価額)は、専有面積の割合を基に按分して計算されるため、同じマンション(棟)の場合、専有面積が同じなら税額も同じになるのが一般的でした。
タワーマンションの高層階と低層階の公平性を図るべく、固定資産税の課税方法が見直され、2017年(平成29年)4月1日以降に新築された居住用超高層建築物(高さ60m超のタワーマンション。20階建て以上が目安)の固定資産税には、階層による市場価格の差が反映されるようになり、固定資産税評価額から算出する不動産取得税も、階層の違いによる影響で変動するようになりました。
この2017年度改正において、高層階ほど取引価格が高い実態を反映させるため、建物の評価に「階層別専有床面積補正率」が導入されました。この補正率により、高層階の住戸は固定資産税の評価額が増加し、そのまま課税標準額となります。結果、高層階の住戸を取得した人は、以前よりも不動産取得税の負担が増えることになり、逆に、低層階の住戸は評価額が下がるため、不動産取得税の負担も軽減されます。

 0120-172-111
0120-172-111