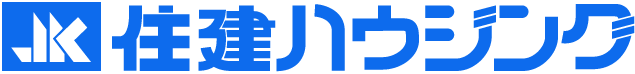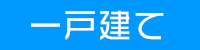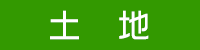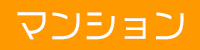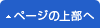所得税・住民税 

不動産を賃貸して出た利益にかかる税金
不動産を売却した際の利益(譲渡所得)にかかる税金
所得税とは

所得税とは、個人が1年間(1月1日から12月31日)に得た所得(もうけや収入)に対して、各種控除を差し引いた金額に応じて課される国の税金です。所得が高い人ほど税率が上がる「累進課税」が特徴。日本では「国税」に分類され、国の歳入の中でも大きな割合を占めています。
対象となる所得は次の10種類に分けられ、それぞれ計算方法が異なります。
| 所得の種類 | 例 |
|---|---|
| 給与所得 | 会社員の給料や賞与 |
| 事業所得 | 自営業・フリーランスの利益 |
| 不動産所得 | アパート・土地の賃貸収入 |
| 利子所得 | 預貯金の利子 |
| 配当所得 | 株式の配当 |
| 譲渡所得 | 株式や不動産の売却益 |
| 一時所得 | 保険の満期金、懸賞金など |
| 雑所得 | 公的年金、ネット副業など |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡収入 |
| 退職所得 | 退職金 |
所得税の基本的な仕組み
1.課税対象
- 給与、事業、年金、不動産、株式の売却益など、すべての所得が対象です。
- ただし、基礎控除や各種控除(扶養控除・医療費控除など)を差し引いたあとの「課税所得」に対して税金がかかります。
2.課税期間
- 1月1日から12月31日までの1年間に得た所得が対象です。
3.納め方
- 会社員などは、毎月の給料から源泉徴収され、年末に年末調整で精算します。しかし、住宅ローンを組んだときなど限られた場合には、会社員でも確定申告の必要があります。
- 自営業者やフリーランス、会社を退職した人などは、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行い、後日税務署から郵送されてくる納付書を使い自分で納税します。
4.税率(累進課税)
- 所得が多いほど高い税率がかかる「累進課税制度」を採用しています。
- たとえば、課税所得が少ない人は5%、多い人は最大45%(+住民税10%)です。
所得税の計算式
所得税額=(所得金額-所得控除)×所得税率
不動産を売却したときの所得税の仕組み
1.譲渡所得とは?
不動産を売ったときの売却益(もうけ)に対して課される所得税のことです。
売却代金の全額に課税されるのではなく、取得費や売却費用を引いた残りの利益だけが課税対象になります。
2.譲渡所得の計算式
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
さらに、マイホームなど一定の資産には「特別控除」が使えます。
例:自宅を5,000万円で売却した場合
- 売却価格:5,000万円
- 取得費(購入価格+購入時の諸費用):3,000万円
- 譲渡費用(仲介手数料・登記費用など):200万円
※3,000万円特別控除を適用すれば、課税所得は0円(税金なし)です。
3.所得期間で税率が変わる
| 区分 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 39% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 20% |
※所有期間は「売却した年の1月1日時点で5年を超えるかどうか」で判断します。
4.マイホームを売ったときの特例
自宅(居住用財産)を売った場合は、税負担を軽くする特例がいくつもあります。
| 特例の内容 | 適用条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 自宅を売却した場合 | 譲渡所得から3,000万円を控除 |
| 軽減税率の特例 | 所有期間10年以上 | 税率を14%(所得税10%+住民税4%)に軽減 |
| 買換え・交換の特例 | 新しいマイホームを購入した場合 | 譲渡益の課税を繰り延べできる |
5.納税の流れ
- 売却した翌年に 確定申告(2月16日〜3月15日)を行う
- 税務署で計算し、所得税・住民税を納付する
参考:自宅を1億2,000万円で売却した場合
想定条件
- 売却価格:1億2,000万円
- 取得価格(購入時の金額):7,000万円
- 取得時の諸費用(登記・仲介・税など):300万円
- 売却時の諸費用(仲介手数料・登記など):400万円
- 所有期間:10年以上(=長期譲渡所得)
- 対象物件:自宅(居住用財産)
1.譲渡所得の計算
1億2,000万円-(7,200万円+700)=4,300万円
譲渡所得は4,300万円
2.マイホーム特例(3,000万円控除)
居住用財産の売却には「3,000万円特別控除」が使えます。
よって、対象となるのは:
課税譲渡所得1,300万円
3.所得税・住民税の計算(長期譲渡所得)
長期譲渡所得の税率は次のとおりです。
| 税の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20% |
納税率:260万円
4.軽減税率の特例(所得期間10年以上)
さらに、マイホームを10年以上所有していれば「軽減税率の特例」が使えます。
| 課税譲渡所得 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14.21% |
| 6,000万円超の部分 | 20.315% |
今回は課税譲渡所得が1,300万円なので、全額が「6,000万円以下の部分」に該当。
実際の税率:約185万円(所得税+住民税の合計)
5.まとめ
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 1億2,000万円 |
| 取得費+諸費用 | 7,700万円 |
| 譲渡所得 | 4,300万円 |
| 特別控除(マイホーム) | ▲3,000万円 |
| 課税譲渡所得 | 1,300万円 |
| 税率(軽減特例) | 14.21% |
| 納税額(合計) | 約185万円 |
| 実際の手取り額 | 約1億1,815万円 |
(注意1)特例を使うには 確定申告 が必要です(翌年2月16日〜3月15日)。
(注意2)マイホームとして住んでいた実績が必要(転居後3年以内の売却など条件あり)。
(注意3)買い替え・同居などのケースでは別の特例(買換え特例)も検討可能です。
住民税とは

住民税(じゅうみんぜい)とは、都道府県や市区町村といった地方自治体に納める地方税を合計した税金のことで、自分が住んでいる地域の行政サービス(道路整備・ごみ収集・教育・福祉など)をまかなうための財源になります。
住民税の基本の仕組み
住民税は、前年(1月~12月)の所得に応じて、翌年に課税されます。つまり「後払いの税金」です。
例)2024年に得た所得 → 2025年6月から2026年5月までの住民税に反映。
住民税の内訳
住民税は次の2つの部分で構成されています。
| 区分 | 内容 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の所得に応じて課税される部分 | 所得税に似ており、所得が多いほど増える |
| 均等割 | 所得に関係なく一律で課税される部分 | 誰でも一定額(市区町村+都道府県)を負担 |
たとえば東京都23区の場合、均等割は多くの区で、
- 都民税:1,500円
- 区民税:3,500円
合計 4,000円(+復興特別税500円) 程度です。
所得税との違い
| 比較項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 納める先 | 国 | 都道府県・市区町村 |
| 計算期間 | 1月~12月 | 1月~12月 |
| 納付時期 | 翌年3月に確定申告 | 翌年6月~翌々年5月 |
| 累進性 | 強い(高所得ほど税率が上がる) | 穏やか(所得割は原則10%前後) |
住民税の支払方法
- 給与所得者(会社員など)
- 自営業・フリーランス
→給与から「特別徴収」として毎月天引きされます。
→自分で納付書や口座振替で支払う「普通徴収」。
会社員であれば毎月の給料から天引きされ、勤め先が本人に代わって各市区町村に納められます(特別徴収)。
一方、自営業の人や会社を退職された人は、各市区町村から郵送されてくる納税通知書にしたがって、本人が直接納めます(普通徴収)。普通徴収の納め方は、“一括”と“分割”の2種類で本人が自由に選択できます。分割で納める場合は、6月、8月、10月、翌年1月の年4回が一般的です。住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得で、納めるのは所得のあった翌年の6月からです。
住民税の計算式
住民税は基本的に次のように計算されます。
住民税=所得割+均等割
それぞれを詳しく見ると、
所得割=(所得金額-各種控除)×税率(約10%)
税率は、都道府県民税4%と市区町村民税6%を合わせた10%が一般的です。
均等割: 所得に関係なく一律で課される税金。
多くの自治体で、年間5,000円前後(例:都民税1,500円+区市町村税3,500円など)です。
税負担例:年収1000万円(会社員・妻・小学生の子どもふたり・東京都在住)
前提情景
- 年収:1,000万円
- 職業:会社員(給与所得者)
- 家族構成:妻(専業主婦)、子ども二人(小学生)
- 居住地:東京都内
- その他:生命保険料控除などは標準的に考慮
1.課税所得の算出
| 計算項目 | 概算金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 年収(給与収入) | 1,000万円 | ― |
| 給与所得控除 | 約195万円 | 国税庁の控除表より (収入850万円超~1,000万円) |
| 所得金額(給与所得) | 約850万円 | 1,000万-195万 |
| 各種所得控除 | 約320万円 | 内訳例: 基礎48万+配偶者38万+扶養76万×2 +社保150万+生命保険など |
| 課税所得金額 | 約485万円 | 805万-320万 |
2.住民税の計算
住民税は、
| 項目 | 計算 | 税額 |
|---|---|---|
| 所得割 | 485万円×10% | 48.5万円 |
| 均等割 | 一律 | 約5,000円 |
| 合計 | 約48万9,000円/年 |
月あたり約4.1万円(翌年6月~翌々年5月まで給与天引き)
3.所得税の計算(概算)
所得税は累進課税で、
課税所得485万円の税率は20%(控除額42.75万円)
ただし、配偶者・扶養控除・子ども控除(住民税と微妙に計算方式が異なる)を考慮すると、 実際の所得税はおおよそ50万円前後になります。
4.所得税+住民税の合計
| 区分 | 年間税額 | 月平均 |
|---|---|---|
| 所得税 | 約50万円 | 約4.2万円 |
| 住民税 | 約49万円 | 約4.1万円 |
| 合計(実質負担) | 約99万円/年 | 月あたり約8.3万円 |
参考:社会保険料も含めた手取り感覚
社会保険料(健康・年金・雇用など)を年収の約15%として計算すると:
| 区分 | 概算額 |
|---|---|
| 税引き前年収 | 1,000万円 |
| 社会保険料 | 約150万円 |
| 所得税+住民税 | 約99万円 |
| 手取り年収(目安) | 約750万円前後 |
ポイントまとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 所得税は国税、住民税は地方税 | 納付先が異なる |
| 所得税は当年払い、住民税は翌年払い | タイミングに注意 |
| 住民税は一律10% | 所得税より計算が単純 |
| 控除が大きいほど両方の税金が減る | ふるさと納税・医療費控除なども有効 |

 0120-172-111
0120-172-111