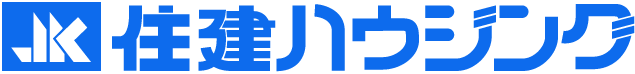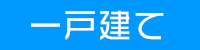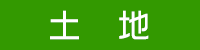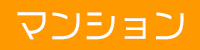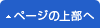相続税 
相続や遺贈によって土地や住宅などの財産を取得したときにかかる税金
相続税とは

相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。
この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。
相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産 |
|---|
| 土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨董など(個人営業の場合には、売掛債権とか受取手形など営業上の財産も対象となります) |
| 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 |
| 生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など |
| 相続税の対象とされない財産 |
| 相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち、法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計算します)、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など |
相続税の計算式
1)各相続人ごとに、課税される金額「課税価格」を算出する
課税価格=相続税対象財産価格+生前贈与財産価格(死亡前7年以内の贈与分)-債務及び葬式費用
2)課税される遺産の総額を算出する
課税遺産総額=各人の課税価格の合計額-基礎控除額
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
課税価格の合計がこの基礎控除額より少なければ、相続税はかかりません。
3)相続税の総額の計算
各人の法定相続分に対する税額=A(課税遺産総額×法定相続分の割合)×B相続税率-C控除額
相続税率[B]と控除額[C]は、各人の法定相続分による取得額[A]により下表のように変化します。
各人の法定相続分による取得額[A] |
H26.12.31まで | H27.1.1以降 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税率[B] | 控除額[C] | 税率[B] | 控除額[C] | |
| 1000万円以下 | 10% | - | 10% | - |
| 1000万円超 3000万円以下 |
15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超 5000万円以下 |
20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超 1億円以下 |
30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 |
40% | 1700万円 | 40% | 1700万円 |
| 2億円超 3億円以下 |
45% | 2700万円 | ||
| 3億円超 6億円以下 |
50% | 4700万円 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 | ||
各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが、相続税の総額です。
4)各人の実際の相続税額の算出
各人の相続税額は、課税価格総額に対する実際に取得した財産の課税価格の割合で決まります。
各人の相続税額=相続税の総額×各人の実際に取得した財産の割合(課税価格÷課税価格の合計)
法定相続人の優先順位
まず、亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、順位に関係なく必ず相続人になります。
配偶者以外の順位が次の通りです。
- 第1順位 被相続人の子供
- 第2順位 被相続人の父母や祖父母などの直系尊属
- 第3順位 被相続人の兄弟姉妹
(注1)相続を放棄した人は、初めから法定相続人でなかったものとします
(注2)内縁関係の人は、法定相続人に含まれません
第1順位の人がいなければ第2順位の人が、第2順位の人もいなければ第3順位の人が相続人になります。
法定相続分
| 法定相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 配偶者 | 配偶者以外 | |
| 配偶者と子供 | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ二人以上いる場合の割合は、原則として配偶者以外の法定相続分をそれぞれの人数分で均等に分けます。

 0120-172-111
0120-172-111