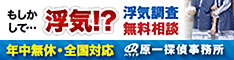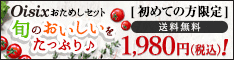吉原【台東区】

江戸文化が咲き誇った遊里の記憶
吉原(よしわら)は、現在の東京都台東区千束周辺にかつて存在した、江戸随一の遊廓(遊里)です。創設は1617年(元和3年)。もとは現在の日本橋近くにありましたが、火災や都市整備の影響で1657年に浅草北東の地、現在の場所へ移転し、「新吉原」と呼ばれるようになりました。
吉原といえば、江戸時代から明治時代にかけて、遊女や芸妓が集まる遊廓として栄え町として有名です。その起源は、元和3年(1617)、江戸幕府はそれ以前に散在していた傾城屋(けいせいや)商売を禁じて、日本橋葺屋町東側の土地(現在の中央区日本橋人形町)に幕府公認の遊廓を開設することを許可。小田原出身の庄司甚右衛門により遊廓が開設されました。その地は葭(よし)の生い茂る低湿地を造成したため、「葭原(吉原)」と呼ばれるようになったと言われています。
吉原は、幕府公認のもとに栄え、最盛期には数百軒の店と千人以上の遊女がいたとされます。単なる遊びの場ではなく、和歌・書画・香道・茶道などの教養も重んじられた文化サロンとしての一面も持っており、江戸庶民の憧れの地として多くの文学や浮世絵にも描かれてきました。
明暦2年(1656)、江戸の市街整備のため、遊郭を浅草日本堤(浅草千束村内、台東区)へ移転するよう幕府は吉原の町名主に対して命じました。そして、明暦3年(1657)に起きた明暦の大火で日本橋の吉原遊廓は消失、浅草日本堤の田圃が広がる土地を築地して遊廓浅草新吉原が誕生しました。この新吉原に対し、日本橋の方を元吉原と呼ぶようになります。
吉原は塀で囲まれており、唯一の出入り口は大門(おおもん)と呼ばれる門だけでした。大門のすぐ右には遊女の脱走を監視する四郎兵衛会所という番小屋があり、廓内の遊女の人別帳を常備していました。また大門の右側に高札場、左側に見返り柳がありました。見返り柳の名前の由来は、客が吉原から帰るときに後ろ髪を引かれる思いで振り返ったことからと言われており、現在も土手道沿いに残されています。大門という名称も場所は異なりますが、交差点名やバスの停留所名として今も使われています。
遊客は、新吉原移転後から江戸前期までは旗本や大名などが主でしたが、元禄期(1688~1704)には紀伊国屋文左衛門や奈良屋茂左衛門が大金を投じて豪遊、享保期(1716~1736)には蔵前の札差や日本橋の大店の旦那たちが通人の遊びをするなど、豪商の客層へと変化していきました。
吉原は、江戸時代から明治時代にかけて、遊女や芸妓が集まる遊廓として栄え、第二次世界大戦後も「赤線」となって商売は続いていました。しかし、昭和33年(1958)の売春防止法の施行により赤線は廃止され、これまでの吉原は終焉を迎えました。 現在では、当時の街並みや建物はほとんど残っていませんが、「見返り柳」や「吉原神社」など、かつての面影を伝える場所が点在しています。周辺は静かな住宅街と歓楽街が混在する独特な雰囲気を持ちつつ、浅草や入谷に近く、観光・下町散策の延長として立ち寄る人も増えています。
吉原は、華やかな江戸文化の影と光を物語る、東京に残された歴史の深層。表舞台とは異なる「もうひとつの江戸」を垣間見られる場所です。
- 吉原神社
稲荷神と弁天様を祀る神社で、家内安全や商売繁盛、技芸上達などの御利益があるといわれています - 吉原弁財天本宮
関東大震災で亡くなった遊女や殉難者を慰霊する観音像があります - 見返り柳
吉原で遊んだお客さんが遊郭を振り返ったことから名付けられた柳の木です - 吉原大門
吉原の入り口にあった黒塗り木造のアーチ門の跡です - 鷲神社
「おとりさま」とも呼ばれ、11月の例祭は「酉の市」として有名。祭神は天日鷲命と日本武尊で、日本武尊が東征の際に戦勝を祈願したと伝えられています - あしたのジョー像
泪橋交差点のそばから土手通りにかけて連なっているいろは会商店街や地域の活性化のために2012年建立。「あしたのジョー」の舞台「山谷のドヤ街」とはこの一帯のこと
猿若町【台東区】

江戸歌舞伎の原点、芝居町の記憶を刻むまち
猿若町(さるわかちょう)は、現在の台東区浅草六丁目付近にあたる地域で、江戸時代に誕生した「江戸歌舞伎発祥の地」として知られています。
天保13年(1842)に天保の改革で、日本橋や京橋などにあった芝居小屋が浅草聖天町に移されたときに誕生した芝居の町で、歌舞伎や人形浄瑠璃などの演劇が盛んに行われました。同年に、聖天町は江戸における芝居小屋の草分けである猿若勘三郎(初代中村勘三郎の名跡)の名に因んで、猿若町(さるわかまち)と改名。猿若町には、江戸三座と呼ばれる「中村座」「市村座」「森田座」などの主要な歌舞伎劇場が集まり、江戸の人々が娯楽を求めて訪問、飲食店や小物商、宿屋なども立ち並んで、江戸庶民の娯楽と文化の中心として栄えました。
こうして「猿若町時代」なる一時代を築き、江戸の娯楽と芸能文化の一大拠点となった猿若町が、浅草を芸能の街として発展させる礎を築いたと言えます。
江戸歌舞伎の祖といわれる猿若勘三郎は、寛永元年(1624)に江戸に下り、江戸中橋(現、中央区京橋付近)で興行を始めたと言われています。その後、堺町(現、日本橋人形町3丁目)への移転の際に、座元の名字である中村に合わせて中村座と改称しました。
中村座は江戸歌舞伎界を代表する歴史と由緒を誇り、勘三郎が幕府から依頼された仕事を成功させた褒美として、幕府から金の麾(ざい:旗)と陣羽織を賜ったという記録もあります。
明治時代になると都市再開発の一環で、歌舞伎座の機能は新富町(現在の中央区)へと移され、中村座・市村座・森田座の三座がそれぞれ別の場所に移転し、猿若町の芝居町としての役目は終焉を迎えました。しかし、猿若町には現在も、江戸三座の跡地や芝居関係者の墓所など、芝居の歴史を伝える碑や史跡が残り、地域にはその歴史が今なお息づいています。
現在の猿若町周辺には、浅草公会堂や木馬亭(大衆芸能の小屋)などがあり、江戸以来の芸能文化を受け継ぐ場となっています。また、浅草寺や花やしきといった観光地にも近く、下町情緒と伝統芸能の雰囲気を感じながら散策できるスポットです。
猿若町は、江戸歌舞伎の幕が上がった原点。芝居の賑わいと文化の息吹が、今も浅草の空気の中に静かに残っています。
- 江戸猿若町中村座跡
中村座は江戸三座の一つで、初代中村勘三郎が創立した歌舞伎の発祥の地です。現在は石碑と看板が残っています - 江戸猿若町市村座跡碑
市村座は江戸三座の一つで、歌舞伎の名作を数多く生み出した劇場です。現在は石碑と看板が残っています - 江戸猿若町守田座跡
守田座は江戸三座の一つで、河原崎座として創立し、後に森田座と改称しました。現在は石碑と看板が残っています - 浅草花やしき
日本最古の遊園地で、昭和レトロな雰囲気が楽しめます。観覧車やジェットコースターなどのアトラクションや、お化け屋敷や芝居小屋などの施設があります
▶テーマパーク「浅草花やしき」について - 浅草演芸ホール
落語や漫才などの伝統的な日本の笑いを鑑賞できる劇場です。毎日昼夜2回公演が行われており、入れ替え制で6~7組の芸人が出演します
向島【墨田区】

江戸の粋が薫る、隅田川の向こう岸に広がる花街のまち
向島(むこうじま)は、東京都墨田区の西部、隅田川の東岸に位置する歴史ある街です。地名の由来は、その名の通り「隅田川の向こうの島」にあったことから。江戸時代には、風光明媚な地として将軍家や文人墨客にも愛され、花街や料亭文化が栄えた江戸随一の風流な地でした。
かつて、向島芸者などで知られていた地で、江戸時代から花街(料亭街)として栄えてきた歴史があります。社寺や文豪の名所といった観光資源も多く、向島百花園や牛島神社などがあります。また、永井荷風の『墨東奇譚』の舞台にもなっています。
向島の花街は東京で最も芸妓数が多い花街で、向島墨堤組合という組織が芸妓や料亭を管理しています。西川流や猿若流といった日本舞踊の流派もあり、春には桜茶屋を設けて花見客を接待したり、様々な催し物を行ったりしています。
向島は桜の名所としても知られています。江戸の行楽地として多くの人に親しまれた隅田川堤(墨堤)の桜は、八代将軍吉宗の時に本格的に桜の植樹が行われたと記録があります。桜の名所としては、王子飛鳥山(北区)や上野山(台東区)もありましたが、飛鳥山は向島よりも江戸市中から遠く、上野山は音曲禁止といった規制もあったため、向島が江戸郊外の花見の名所として、一番の賑わいを見せていたようです。
今も名物として残る「長命寺の桜もち」は、享保2年(1717)に、墨堤沿いの長命寺で働く山本新六が、試みに墨堤の桜の葉を樽の中に塩漬けにして餅を包んで売り出したのが始まりです。他にも、向島界隈には和菓子屋や料理屋などが数多くありました。
文化元年(1804)、向島の地を愛した文人墨客の助けを受けて、仙台生まれの商人佐原鞠塢(さわらきくう)が寺島内多賀屋敷跡に百花園を開き、文人が集まる風流なところとして、たちまち有名になりました。新春に一年の幸せを願って七福神を巡礼するという「隅田川七福神めぐり」は、ここに集まった文人たちの間で考え出されたと言われます。
近代以降も、静かな住宅街とともに文化の香りが残り、鳩の街通り商店街や向島百花園など、昭和の面影と自然美が融合したスポットが点在。東京スカイツリーからもほど近く、下町情緒と現代の景観が調和した街並みが広がっています。
向島は、江戸の粋と静けさが息づく、水辺の文化都市。花見、芸、甘味処。四季折々の風情が、今も静かに人を引き寄せています。
- 隅田公園
桜やスカイツリーの景色が美しい公園です。隅田川七福神巡りのスタート地点でもあります - 牛嶋神社
隅田公園に隣接する綺麗で立派な神社です。撫牛と呼ばれる牛の像に触れると病気が治ると言われています
▶「東京のおすすめパワースポット!縁結び・商売繁盛・金運などのご利益がある神社・寺院『牛嶋神社』 - 向島百花園
江戸時代から続く花の名所です。四季折々の花が楽しめます - 東京スカイツリー
日本一高い電波塔で、展望台からは東京の街並みを一望できます。周辺にはショッピングモールや水族館もあります - 羽子板資料館
江戸時代から現代までの羽子板の歴史や文化を紹介する博物館です。作り方や道具も展示されています
飛鳥山【北区】

将軍も愛した花の名所、庶民の行楽地の原点
飛鳥山(あすかやま)は、東京都北区王子に位置する小高い丘で、江戸時代から現在まで続く桜の名所として知られています。古くから眺望に優れた景勝地とされ、周辺地域とともに親しまれてきました。地名の由来は定かではありませんが、元亨年間(1321~1324)に、武蔵国の土豪豊島氏が紀伊国新宮(和歌山県新宮市)の飛鳥明神の分霊を祀ったことにちなむという説があります。飛鳥山という地名は、今も東京都北区の区立公園や、都電荒川線の停留所の名前として残っています。
特に有名なのは、八代将軍・徳川吉宗が享保の改革の一環として、享保年間(18世紀前半)にこの地に桜を植え、庶民の行楽地として開放したこと。これにより飛鳥山は、江戸庶民が気軽に花見を楽しめる初の公園的空間となり、「江戸六園」のひとつにも数えられるようになりました。
享保5年(1720)9月、徳川吉宗はこの地を行楽地とするために、江戸城の吹上苑内で育てた桜の苗木200本を植えさせ、翌6年には松・楓各100本と、桜1000本を植えさせました。
桜の咲く頃には、飛鳥山の西側の田の菜の花も咲き乱れ、かなりの絶景だったと伝わります。享保18年(1733)には水茶屋も10軒を数え、花見で賑わう名所となりました。
元々、夏は蛍、秋は虫聴と紅葉、冬は雪見の名所でもあった飛鳥山に桜も加わったことで、江戸近郊で有数の四季を通じた行楽地へとなりました。
明治以降は、正式に日本初の公園(飛鳥山公園)として整備され、明治6年(1873)に、上野、芝(港区)、深川(江東区)とともに日本初の公園として開園。現在も春には数百本の桜が咲き誇る都内有数の花見スポットです。また園内には、紙の博物館・北区飛鳥山博物館・渋沢史料館などの文化施設も集まり、近代日本の礎を築いた実業家・渋沢栄一ゆかりの地としても注目を集めています。
山頂へは、小さな自走式モノレール「アスカルゴ」で気軽にアクセスでき、東京スカイツリーや東京タワーなど、東京の街並みを一望できるスポットとしてファミリーや観光客にも人気。歴史と自然、文化が同居する、のんびりとした時間が流れる都会のオアシスです。
飛鳥山は、江戸の粋と近代の知が交差する、東京らしい風景が残る丘。今も昔も、人々の憩いの場として愛され続けています。
- 飛鳥山公園
桜の名所として有名な公園で、渋沢栄一の旧邸や博物館、野外ステージなどもあります - 大神神社
日本最古の神社の一つで、三輪明神として親しまれています。王寺駅からバスで約15分です - 長谷寺
西国三十三観音霊場の第八番札所で、国宝の本堂や礼堂があります。王寺駅からバスで約20分です - 巌島神社
市杵島姫命を祀る神社で、白い鳥居が目印です。王寺駅からバスで約25分です - 中村家住宅
慶長年間に建てられた代官の家で、重要文化財に指定されています1。王寺駅からバスで約30分です - 王子神社
この一帯の王子という地名の由来となった神社。開運招福や運気の回生、厄除けや家内安全、身体健全、交通安全などに御神威深き神社。「子育大願」の神社として、子どもに関する祈願(初宮、七五三、学業成就など)も多く受けられています - 七社神社
安産・厄除・お宮参りなどの祈願やお参りに多くの人が訪れる神社。境内には「御衣黄」という里桜が植えられており、春には淡い緑色から紅色に変化する美しい花を咲かせます。八月の例大祭には、北区無形民俗文化財に指定されている七社神社の田楽舞が奉納されています
※参考資料:大石学著『地名で読む江戸の町』PHP新書
東京の街から江戸の暮らしに思いを馳せる 江戸から続く東京の地名シリーズ
投稿者プロフィール
-
「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。
不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。


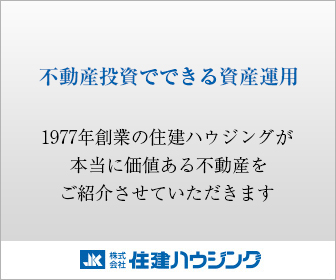

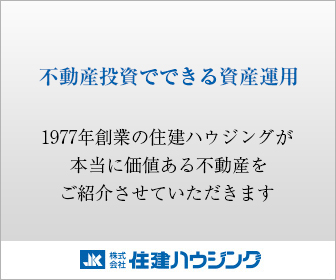























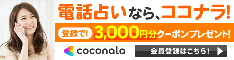










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説