東京都の中心より東に位置するエリアは、河川に囲まれた自然豊かな土地が広がり、下町人情溢れる街並みが特徴です。多くの公園や緑地があり、子育てしやすく暮らしやすい地域ですが、比較的都心部より土地の値段が安くなる傾向にあります。都心へのアクセスも良く、ショッピングモールなど商業施設の充実した駅も多くあり、マイホーム購入の選択肢として人気があります。
日暮里【荒川区】

下町情緒と多様な文化が交差する、東京の“玄関口”
日暮里(にっぽり)は、東京都荒川区に位置するエリアで、JR山手線・京成線・舎人ライナーなど複数路線が交差するアクセス抜群のターミナル駅を擁します。成田空港と都心を結ぶ「京成スカイライナー」の停車駅でもあり、東京の東の玄関口としての役割も担っています。
日暮里は東京都荒川区にある地名で、その昔、新開拓地を意味する「新堀(にいぼり)」と記していました。この地は後北条氏の家臣遠山氏の居住地でしたが、江戸時代には幕府直轄領となり、江戸城背後の守りを目的として寺町が形成されました。
地名の由来は、江戸時代には庶民の行楽地として人気が高まり、特に春の桜や秋の紅葉は美しく、新堀の景色を見ていると日が暮れるのも忘れてしまう気持ちになるため、「日暮らしの里」と言われるようになり、「新堀」と「日暮らしの里」の字訓を合わせて日暮里と書くようになったという説が伝わっています。
江戸の名所の一つに数えられるようになった日暮里は、四季折々の自然美で人々の目を楽しませました。寺社は競って花樹を植えて庭園を造り、料理屋や茶店を設けて参詣者を招きました。
春は花見。桜の名所として賑わったのが妙隆寺・修性院・青雲寺で「花見寺」と称されました。日暮里の寺院がこぞって庭園を造るようになると、これまでの桜の名所であった上野の寛永寺(台東区)や飛鳥山(北区)の両者を凌ぐ勢いとなりました。
秋は月見。「月見寺」として知られていたのが本行寺。本行寺は太田道灌の孫である太田資高(すけたか)により建立されたと伝えられ、境内には道灌が築いたとされる物見塚があります。
冬は雪見。雪見に適するとして「雪見寺」と称されていたのが浄光寺。浄光寺は、元文2年(1739)、八代将軍吉宗が遊猟のときに休憩したのを始まりとして、同5年(1740)に御膳所に命じられました。
歴史的には、日暮里はかつての寺町・文人の隠れ家として知られ、俳人・松尾芭蕉や正岡子規など、多くの文化人に愛された場所でした。また、駅北側には今も昔ながらの風情が残る谷中(やなか)エリアが広がり、寺社や古民家、個人商店が点在する下町情緒あふれるまち並みが魅力です。
一方、駅南側には日暮里繊維街があり、服飾・生地の専門店がずらりと並ぶ、専門性の高い商店街として全国から仕入れ客やクリエイターが訪れます。さらに、再開発により高層マンションやホテルも建設され、古き良き東京と新しい都市の姿が共存するエリアとなっています。
日暮里は、歴史・文化・産業が交差する東京の縮図のようなまち。散策にも生活にも、さまざまな顔を見せてくれる奥深いエリアです。
- 谷中銀座商店街
東京都台東区谷中にある商店街です。昭和30年代には既に存在していたとされ、現在では約70店舗が軒を連ねています。商店街には、和菓子屋、洋菓子屋、飲食店、雑貨店などがあります。また、毎年4月には「谷中銀座桜まつり」が開催され、多くの人で賑わいます - 夕やけだんだん
JR日暮里駅の北口から御殿坂を上っていくと、谷中銀座商店街に通じる階段のことで、夕方には美しい夕焼けを見ることができるスポットです。階段名は一般公募によって命名されました - 根津神社
日本武尊によって創建されたと伝わる神社。秋に開催される例祭は、江戸3大祭りの一つとなっています。境内には約2000坪のつつじ苑があり、四月終わりごろにはたくさんのツツジが咲き誇ります - エキュート日暮里
JR日暮里駅に直結している商業施設。飲食店や雑貨店、書店などが入っていて、地元の人や観光客に人気です。様々なイベントが毎月開催されます - 和洋菓子 EDO USAGI
妖怪大福が名物の和洋菓子店。「江戸うさぎ」という名前で創業17年目を迎え、「和洋菓子 EDO USAGI」としてリニューアル。オンラインショップもあります - 経王寺(きょうおうじ)
日蓮宗の寺院。明暦元年(1655)創建の寺、山号は大黒山。境内には日蓮上人作という大黒天が祀られています。
下谷・入谷【台東区】

江戸の風情と人情が息づく、静かな下町の時間
下谷(したや)と入谷(いりや)は、台東区の北部に位置する隣接したエリアで、江戸時代から続く庶民の町として発展してきました。上野のお膝元にありながら、観光地の喧騒とは一線を画す落ち着いた下町の空気が流れています。
下谷は旧東京市下谷区の範囲を指す地域名でもあり、下谷町のほか、入谷町、稲荷町、御徒町、箪笥町(いずれも台東区)など付近一帯の町に冠して用いられ、広い地域を指します。一方、入谷は下谷の中の一つの町名です。下谷は戦国時代に、入谷は江戸時代に見られた地名ですが、その起源についてははっきりしておらず、上野台地の下の谷で下谷とする説などがあります。
下谷:寺町として栄えた、江戸の面影
寛永2年(1625)、上野台地に天台宗東叡山寛永寺(台東区)が建立されると、上野台地下の下谷町を含む一帯は、門前町として町場化が進みました。正保元年(1644)、下谷町は、東叡山寛永寺の本坊御用人足、境内掃除人足を務めるようになります。「下谷」という地名は、江戸時代に上野山(寛永寺)の麓にあたる“下の谷”という地理的な特徴から名付けられました。この地域には多くの寺院が集まり、寺町として栄えた歴史があります。特に「下谷神社」は、江戸最古の稲荷神社の一つとされ、地域の守り神として今も親しまれています。
また、明治・大正期には寄席や演芸場も多く、庶民文化の中心地として賑わいを見せました。その面影は、路地裏や古い建物、町工場の風情に今も残っています。
入谷:朝顔市と信仰の町
一方の入谷(いりや)は、特に「入谷鬼子母神(真源寺)」で知られ、江戸時代には子育て・安産の神様として多くの参拝者を集めました。境内で行われる「入谷朝顔市」は、今も夏の風物詩として多くの人を魅了し、地域に根づく季節の文化を今に伝えています。
入谷周辺は、近年では静かな住宅街として再注目され、古い町並みと新しいカフェや小規模ギャラリーが同居する“東京の静かなトレンドスポット”としての顔も持ち始めています。
文化~文政年間(1804~30)、下谷・御徒町(台東区)付近の植木職人が朝顔の花や葉の変種を育成するようになり、下谷の朝顔ブームが始まりました。その後、幕末、明治、大正と朝顔ブームがありましたが、大正以降の宅地化と第二次世界大戦の戦災により朝顔栽培は一旦途絶えます。昭和22年(1947)に地元の人々によって朝顔栽培が復興され、現在、毎年7月に真源寺境内と参道で朝顔市が開かれ、多くの人で賑わいます。
下谷・入谷は、派手さはなくとも、江戸の記憶と人情が息づくまち。のんびり歩けば、東京の奥深い魅力に気づくことができます。
- 真源寺(入谷の鬼子母神)
『恐れ入谷の鬼子母神』というフレーズで有名な真源寺。伝統の朝顔市が毎年開かれ、夏の風物詩となっています - 鷲神社
台東区千束3丁目にある寺社で「おとりさま」の通称でも呼ばれ、11月の例祭は「酉の市(とりのいち)」として広く知られています - 飛不動尊
台東区竜泉3丁目にある天台宗の寺院で、正式名は「龍光山三高寺正寶院」。飛不動尊は、空を飛ぶ不動明王として知られており、航空安全・飛行安泰・旅行安泰祈願でも知られています - 下谷七福神めぐり
台東区下谷にある七つの福神を巡る参拝コース。江戸時代から続く伝統行事で、毎年1月1日から1月15日までの期間に行われます
巣鴨【豊島区】

「おばあちゃんの原宿」として親しまれる、安心と活気のまち
巣鴨(すがも)は、豊島区の東部に位置し、JR山手線と都営三田線が交わる交通の要所。かつては中山道の宿場町として栄え、現在も人情と庶民的なにぎわいが共存する下町の顔を色濃く残しています。
巣鴨の象徴ともいえるのが、巣鴨地蔵通り商店街。全長約800メートルの商店街には、衣料品、和菓子、雑貨などの老舗店や飲食店がずらりと並び、高齢者を中心に「おばあちゃんの原宿」という愛称で親しまれています。
その中心にあるのが、高岩寺(とげぬき地蔵)。正式には曹洞宗の寺院ですが、「病を取り除く」とされるとげぬき地蔵尊への信仰が広く、全国から多くの参拝客が訪れます。毎月4・14・24日の縁日には露店が並び、まるで昔話のようなにぎわいが今も続いています。
一方で、近年は若者向けのカフェや雑貨店も登場し、懐かしさと新しさが融合するユニークな街へと進化中。幅広い世代が集い、誰もが安心して過ごせる、温かみある空気が巣鴨の魅力です。
巣鴨の歴史と地名の由来
この地は江戸時代、街道沿いに植木屋が整然と建ち並び、武士たちが花見に興じ人々が真剣な目で植木を選ぶ姿が見られる園芸の中心地でした。
巣鴨の地名の由来には諸説ありますが、昔々その土地にあった大池に鴨が巣を作っていたことから巣鴨という地名が生まれたという説や、街には石神井川、谷端川が流れ、多くの州や沼地があって葭が茂っており、その地形から州賀茂、菅面、州鴨、須賀茂、須賀母、洲処面、巣鴨などのいくつかの書き方があり、いずれにしてもその地形からきた説があります。
文政11年(1828)に編纂された『新編武蔵風土記稿』によれば、巣鴨は南北朝時代にはすでに軍事、交通の要衝であったことが窺えますが、明暦の大火(1657)以後、幕府の新都市計画と市街地の拡大によって、武家屋敷や寺社が移転され、新たな町屋が形成されます。
八代将軍徳川吉宗の治世(1716~45)には全国的に疫病が流行し、公家や武家を含め多くの人々が死亡しました。これに対し、吉宗は本草学者を登用して、本格的な薬草政策と疫病対策を行いました。この一環として、全国的な薬園の整備が行われ、この巣鴨でも、江戸幕府保護下の薬園として「御薬園」が設置されました。同地は明和6年(1769)、「御林(おはやし)」に変わり、寛政10年(1798)頃、幕府のお抱え医師渋江長伯の「御預御薬園」になりました。
江戸市中には大名・旗本・寺社が所有する大庭園から、町人たちの所有する小庭園に至るまで多くの庭園が存在していました。江戸時代の巣鴨は、江戸近郊としての地の利を生かし、これらの庭園に対して植木を供給する園芸センターの役割を担っていました。花盛りの季節には江戸市民の花見遊覧の場となり、江戸近郊の花名所として知られるようになりました。
巣鴨は、時代を超えて「やさしさ」が根づくまち。どこか懐かしく、心がゆるむ東京の一角です。
- 旧古河庭園
北区西ヶ原にある日本庭園。元々は大正時代に古河財閥の屋敷として作られたもので、広さは約1.2haあります。庭園内には池や滝、茶室などがあり、四季折々の景色を楽しむことができます - 巣鴨猿田彦大神庚申堂
巣鴨地蔵商店通り商店街の端に位置する観光スポット。庚申塔を奉安するお堂で、猿田彦大神を祭神としています - とげぬき地蔵(高岩寺)
巣鴨駅からすぐの場所にある曹洞宗の寺、高岩寺にある地蔵菩薩が通称「とげぬき地蔵」です。刺し傷や怪我をした人が、その場でとげを抜いて治療するために祈願する地蔵菩薩像です - 水洗い観音(高岩寺)
高岩寺にある観音様。自身の治癒したい部分に相応する観音像の部分を洗うか、または濡れタオルで拭くとご利益があるとされています - 六義園
文京区本駒込六丁目にある都立庭園で、「回遊式築山泉水庭園」の日本庭園(大名庭園)です。国の特別名勝に指定されており、回遊式築山泉水庭園としては最大規模を誇ります - 染井霊園
豊島区駒込にある都営霊園。旧称は染井墓地。水戸徳川家墓所や府中松平家の江戸期の墓があります。園内には約100本のソメイヨシノが植えられ、桜の名所として親しまれています - 東洋文庫ミュージアム
文京区本郷にある、東洋文庫の展示施設。東洋文庫は、明治時代に創設された図書館で、アジア・アフリカの文化・歴史に関する資料を収集・保存しています - 中央卸売市場 豊島市場
豊島区南池袋にある築地市場の後継施設です。築地市場と同様、新鮮な魚介類や野菜などを扱う卸売市場で、一般人も買い物が可能です。JR池袋駅から徒歩10分ほどでアクセスできます
小松川【江戸川区】

水辺とともに歩んだ、江戸から続く静かなまち
小松川(こまつがわ)は、東京都江戸川区の北部に位置するエリアで、地名は小松川という河川の名前に由来。荒川と旧中川に挟まれた水とともにある街として知られています。江戸時代から続く低地の農村地帯であり、かつては新田開発が進められた歴史を持ちます。
特に有名なのが、小松川千本桜や小松川境川親水公園、荒川河川敷など、自然とふれあえる場所の多さ。かつての用水路を活かした親水空間や、広々とした芝生エリアは、地元住民の散歩や子どもの遊び場として親しまれ、都心近くにありながらゆったりとした時間が流れるのが魅力です。
小松川といえば、お雑煮やおひたしなどに使われる「小松菜」を思い出しますが、小松菜の名前の由来には、次のような話が伝わっています。
江戸周辺の村々は鷹場にしてされており、小松川あたりも頻繁に将軍が鷹狩に来ていました。ある時、鷹狩に来た八代将軍吉宗が香取神社で休憩した際に、神主は地元で採れた青菜をあしらった餅のすまし汁を差し上げました。吉宗はこの青菜をたいへん気に入り名前を尋ねましたが、名前がなく返答に困っていた神主を見て、「ここは小松川だから小松菜と呼べ」と命名したということです。
地名の由来となった小松川は、小松村(現、葛飾区新小岩あたり)から流れていたため小松川と呼ばれましたが、また、村境を流れていたため境川とも呼ばれていました。現在は、小松川境川と呼ばれて整備され、小松川境川親水公園が造られました。小松川境川親水公園は、同じ江戸川区内の古川親水公園に次いで全国で二番目に造られた親水公園(水に親しむ工夫がされた公園)です。
小松川のある現在の江戸川・葛飾区あたりは低湿地帯で、江戸時代は毎年のように洪水に悩まされていましたが、明治44年(1911)から昭和5年(1930)まで19年の歳月をかけて造られた西小松川村の真ん中を通る荒川放水路の完成で、繰り返す水害の歴史は幕を下ろしました。その後は再開発や区画整理が進み、今では整然とした住宅地へと変貌を遂げています。現在は都営地下鉄新宿線「東大島駅」からのアクセスもよく、都心通勤にも便利なベッドタウンとして注目されています。
小松川は、水辺のやすらぎと静かな暮らしが共存する、東京東部の隠れた良住環境。歴史を感じながら、穏やかに暮らせる街です。
- 大島小松川公園
旧中川を挟んで江東区と江戸川区にまたがる都立公園。災害時には20万人の避難場所となります。園内は都営新宿線「東大島駅」を中心に5つの広場に分かれており、アスレチック広場やバーベキュー広場などもあって家族で楽しめる公園です - 小松川境川親水公園
江戸川区内で2番目にできた親水公園。全長約4kmの境川沿いに位置し、五つのゾーンに分かれ、滝に始まり、せせらぎ、水しぶき、飛び石、釣り橋に冒険船など、変化に富んだ水遊びが出来るスポットです。桜の名所でもあります - 小松川千本桜
江戸川区の町の安全を守る荒川のスーパー堤防において、南北2kmにわたり約1,000本の桜の木が並ぶ、お花見の名所です。毎年春には「小松川千本桜まつり」が開催されます - 江戸川区総合文化センター
江戸川区にある文化施設。音楽会や演劇、映画上映などの公演が行われています。大小のホールとその他、研修室、会議室、レストランなど有り
柴又【葛飾区】

昭和の風情と人情が残る、東京の“心のふるさと”
柴又(しばまた)は、東京都葛飾区の東端に位置するエリアで、江戸川のほとりに広がる下町情緒あふれる街です。映画『男はつらいよ』シリーズの舞台として全国的に知られ、主人公・車寅次郎の故郷として今も多くの観光客が訪れます。
街の中心には、寅さんゆかりの『柴又帝釈天(経栄山題経寺(きょうえいざんだいきょうじ))』が鎮座し、厄除けや開運の祈願に多くの参拝者が訪れます。帝釈天は、江戸時代・寛永年間(17世紀前半)に創建された由緒ある寺で、室町時代初期には草庵のようなものがあったと考えられている古い寺です。 参道には老舗の団子屋や和菓子店、土産物屋が並び、まるで昭和にタイムスリップしたような風景が広がります。
さらに、柴又は江戸川の河川文化と深く結びついており、演歌で有名な堤防沿いの「矢切の渡し」は、江戸時代から続く渡し舟として、今も現役で都内に残るただ一つの渡し船です。市街地の喧騒を離れ、川風を感じながら東京のもう一つの顔を楽しむことができます。
また、近年では「寅さん記念館」や「山田洋次ミュージアム」なども整備され、映画と実際の街が重なる唯一無二の観光地として再評価が進んでいます。
柴又につながる名前が初めて出てきたのは、正倉院に残されていた「下総国葛飾郡大嶋郷戸籍」で、養老2年(718)のものとされます。この中に、嶋俣(しままた)里の名前が見られます。この嶋俣里が現在の柴又であると考えられています。
嶋俣の地名の由来は一説によると、嶋俣の文字(「俣」は分かれるという意味)や地形から推測して、昔はこの辺りまで東京湾が広がっており、その中に点々と島々があって、嶋俣もこの中の一つであったからと言われます。のちに嶋俣が柴俣に訛り、江戸時代初期には柴俣、芝又、芝亦などの地名が使われ、慶安元年(1648)の検知以降、柴又という文字に統一されました。
柴又は、懐かしさと温かさが交差する“東京のふるさと”。人情、歴史、景色が心に残る、特別な時間が流れています。
- フーテンの寅像
柴又帝釈天参道商店街に建っている、映画「男はつらいよ」シリーズの主人公・車寅次郎(寅さん)をモチーフにした像。1999年に地元商店会と観光客の募金によって建立。その傍にある「見送るさくら像」は、「フーテンの寅」役の渥美清が亡くなってからの平成29年(2017年)に建立されました - 柴又帝釈天(経栄山題経寺)
日蓮宗の寺院で、江戸時代初期の寛永6年 (1629年) に、2人の僧によって開山。正式名称は「経栄山題経寺」と号し、柴又帝釈天は俗称です。
柴又帝釈天は、映画「男はつらいよ」シリーズにも登場し、また、柴又帝釈天参道商店街には、昭和時代の下町情緒を残す商店が並び、観光客にも人気があります - 寅さん記念館
映画「男はつらいよ」シリーズの舞台である柴又をイメージした映画の世界観や各種資料を再現・展示。また、同映画の監督を顕彰する「山田洋二ミュージアム」も併設しています - 柴又ハイカラ横丁・柴又のおもちゃ博物館
昭和の雰囲気を再現した商店街で、映画「男はつらいよ」シリーズの舞台となった柴又の風景を再現した建物が建ち並び、多くの人々に親しまれています - 柴又のおもちゃ博物館
昭和のおもちゃを展示する博物館。映画のキャラクター「寅さん」が愛用していたおもちゃや、昭和30年代から40年代にかけて製造されたおもちゃなどが展示されています - 矢切の渡し(江戸時代から続く渡し船)
江戸川に橋がなかった時代、江戸と下総国を結ぶ唯一の渡し船。小説「野菊の墓」や歌謡曲で有名に。現在でも唯一現存する農民渡船です
金町【葛飾区】

水と緑に囲まれた、進化を続ける東東京の生活拠点
金町(かなまち)は、東京都葛飾区の北東部、千葉県との県境に位置するエリアで、JR常磐線と京成金町線が通る交通の要所です。かつては農村地帯として静かな下町の一角を成していましたが、昭和以降の都市化・再開発により、都心通勤者にとっての住宅地・生活拠点として発展してきました。
歴史的には、金町は中川と江戸川に挟まれた低地で、江戸時代には利根川・江戸川水系の舟運の中継地点として栄えたほか、明治時代には『水道の拠点「金町浄水場」』が整備され、現在も都内への水供給を担う重要な施設となっています。この影響で、水にまつわるインフラと文化が根づく街でもあります。
近年注目を集めているのが、金町駅北口の再開発。タワーマンションや商業施設、大学キャンパス(東京理科大学葛飾キャンパス)などが整備され、若い世代やファミリー層の流入が進んでいます。一方で、江戸川河川敷や水元公園など豊かな自然環境にも恵まれており、都心近郊とは思えない開放感を味わえる点が大きな魅力です。なお、金町駅はJR常磐線に乗り東に向かうと東京最後の駅になります。
地名の由来ははっきりしていませんが、古くは金町郷といい、下総国香取神宮領の中心地として栄え、古利根川沿いの鎌倉街道に面した町屋が形成され、金町屋と呼ばれるようになり、これが金町になったと伝えられます。また、室町時代の資料にはすでに金町の地名が見られます。
江戸川や中川は、もとは「板東太郎」の異名を持つ利根川の本流でした。氾濫続きの葛西地域を開発するために、徳川家康は農政・治水に通じた家臣の伊奈家に命じて、上流の関宿(千葉県東葛飾郡)付近で利根川の流れを付け替え、現在のように銚子(千葉県)まで流すようにしました。なお、旧河道は常陸(茨城県)・下総(千葉県・茨城県)方面と江戸との舟運に利用されたことら、江戸川の名が付いたと言われます。
江戸川に面した金町は、江戸時代を通じて交通の要衝であり、江戸防備の拠点でした。水戸街道の千住(足立区)に続く江戸から二番目の宿場である新宿(葛飾区)が西接し、村の東北端にある江戸川の渡船場には関所が設けられ、対岸の松戸(千葉県)と合わせて金町松戸御関所と呼ばれました。
金町は、都市と自然、伝統と未来が交差するバランスのとれたまち。静かに暮らしながら、確かな利便性と成長性を感じられるエリアです。
- 葛西神社
葛西囃子(江戸祭囃子)発祥の地として知られる神社。ご利益は出世、商売繁盛、開運などが主で、金運アップのパワースポットとして知られます。境内にある金町弁天社では、音楽や美術、学問などの芸術に関する神様として知られる弁財天を祀っています - 金町うどん
金町駅北口から徒歩1分の場所にある安くておいしいと評判のうどん屋さん。各種丼ぶりとのお得でボリュームのあるセットメニューが人気です - とらやベーカリー
金町駅北口から徒歩3分の場所にある地元で大人気のパン屋さん。お店のパンは、サンド系や惣菜系など質が高くセンス溢れる魅力的なパンが豊富。おすすめのパンは、「クリームパン」、「塩と黒豆」、「とらや食パン」などです - ヴィナシス金町ブライトコート
京成金町駅出口から徒歩約2分のところにあるショッピングモール。アパレルショップ・雑貨・食料品・レストラン・ファストフード・書店・ 塾・美容室・クリニック・図書館などが入っています
水元【葛飾区】

東京に残る“里山の風景”、水と緑が息づく憩いのまち
水元(みずもと)は、葛飾区の北東端に位置し、中川・大場川という二つの川に囲まれるように広がっている低地帯を指す地名で、自然豊かなエリアです。東京都23区の中で最も“田園風景”が色濃く残る場所のひとつで、都市でありながら里山のような落ち着きを感じられるのが特徴です。
この地名は、明治22年(1889)、市町村制施行に伴い誕生した村名で、明治以降の地名ですが、その由来は江戸時代に遡ります。享保14年(1729)、紀州藩出身の治水家・井沢弥惣兵衛為永が開削したのが小合溜井で、ここが東葛西領を潤す灌漑用水の水源地であったために、「水のもと(源)」という意味で名づけられたといわれます。なお、溜井とは用水をためておくために川水をせき止めたところです。現在、小合溜井は水郷風景豊かな水元公園の中心として、また釣り場として有名です。
最大の魅力は、なんといってもその水元公園。東京都内最大級の面積を誇る都立公園で、広大な水辺と森、湿地、生態園などが整備されています。ハナショウブやメタセコイア並木が四季折々の風景を彩り、都会の喧騒を忘れさせるオアシスとして多くの人に親しまれています。
水元は、かつては沼地や水田が広がる農村地帯で、現在でも旧家や畑が点在し、昭和以前の東京の風景を今に伝える貴重な地域です。また、自然環境に惹かれて移住する人やアーティストも増えており、静かながらも独自の文化やライフスタイルが根づくエリアとして注目されています。
水元は、“東京らしくない東京”が体感できる、自然と共にあるまち。のんびりと暮らす楽しさが、ここにはあります。
- 水元公園
都内で唯一水郷の景観をもった公園。約96ヘクタールの面積を誇り、ポプラ並木や紅葉の名所となる「メタセコイアの森」などがあります。また、水元公園は桜の名所でもあり、例年3月下旬頃から4月上旬頃にかけて、約740本の桜の木が咲き誇ります - 水元神社
江戸時代初期に創建された神社で、境内には「御神木」と呼ばれる樹齢800年以上の大楠があります - 水元寺
平安時代末期に創建されたお寺で、国宝に指定されている「水元狩野屏風」が有名です - 南蔵院
大岡政談「しばられ地蔵」の話に登場する石地蔵で有名。今も石地蔵は盗難除けなどの願いをかなえてもらうため、祈願者によって縛られ続けています
※参考資料:大石学著『地名で読む江戸の町』PHP新書
東京の街から江戸の暮らしに思いを馳せる 江戸から続く東京の地名シリーズ
投稿者プロフィール
-
「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。
不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。




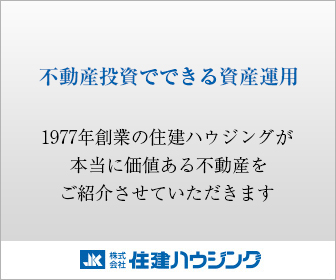


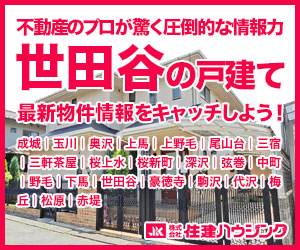














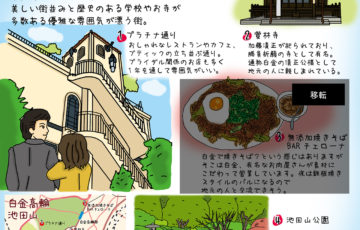




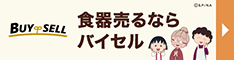
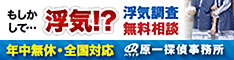










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
