
武家地とは、主に武士が居住する地区を指します。江戸時代の都市計画において、武士の居住地として定められ、大名や幕臣の屋敷が配置されました。また、下級武士の居住地として、長屋や組屋敷も含まれます。武家地は、町人地や寺社地と区別され、都市の構造において重要な役割を果たしました。
有楽町【千代田区】

千代田区に位置する有楽町は、現在の霞ヶ関・丸の内のビジネス街と繁華街「銀座」をつなぐエリア。東京駅から程近く、都内でも有数のビジネス街です。その名の由来から現在に至るまで、多様な顔を持つ魅力的な街として発展してきました。
歴史的背景
有楽町の地名は、慶長年間(1596~1615)にあった、戦国時代の武将であり茶人としても知られた織田信長の弟、織田長益(有楽斎)の屋敷跡「有楽原(うらくがはら)」に由来するとされています。江戸時代には、名奉行・大岡越前守忠相が執務した南町奉行所(時代劇「大岡越前」「遠山の金さん」でおなじみ)が置かれるなど、行政の中心地としての顔も持ち合わせていました。その後の明治5年(1872)に「有楽町」という名称になりました。南町奉行所があったところには、現在、有楽町マリオンが建っています。
明治時代以降、有楽町は急速に近代化を進めます。特に戦前は、朝日・毎日・読売といった大手新聞社の本社が集積し、「新聞街」として日本の言論をリードする役割を担いました。また、日劇や東京宝塚劇場といった一流の劇場が立ち並び、文化的・娯楽の中心地としても栄えました。
戦後、1957年のそごう百貨店進出とフランク永井のヒット曲「有楽町で逢いましょう」をきっかけに、高級志向の街からより多くの人々が集う開かれた街へと変貌を遂げ、銀座と並ぶ繁華街としての地位を確立しました。
かつて、ラジオドラマ「君の名は」で有名な「数寄屋橋」という橋が架かっていましたが、昭和26年(1951)から始まった外堀の埋め立てにより撤去され、今は「数寄屋橋交差点」とその名だけが残っています。なお、この橋名は、江戸城内の茶室や茶道具の管理を行う“数寄屋坊主”を指揮する“数寄屋頭”の屋敷があったことに由来します。
現在の有楽町の特徴
現在の有楽町は、東京の主要な玄関口の一つとして、その多面性が大きな魅力となっています。
- 交通の要衝
- 多様な顔を持つ街
- ビジネスとエンターテイメントの融合
JR山手線、京浜東北線、東京メトロ有楽町線が乗り入れる有楽町駅を中心に、東京駅、日比谷駅、銀座駅とも地下通路で繋がっており、都内各所へのアクセスが非常に便利です。ビジネスパーソンから観光客まで、幅広い層が利用する交通の結節点です。
東側は銀座に隣接し、商業施設や飲食店が立ち並ぶ華やかなエリア。西側は日比谷公園や皇居外苑に近く、オフィス街や劇場、映画館が集まる文化的な側面も持ち合わせています。北側には、国際的なイベントも開催される東京国際フォーラムがあります。
大企業のオフィスビルが集積するビジネス街でありながら、帝国劇場や東京宝塚劇場、TOHOシネマズ日比谷など、歴史ある劇場や映画館が数多く存在し、上質なエンターテイメントを提供しています。ショッピングやグルメの選択肢も豊富で、ビジネスとレジャーの両方を楽しむことができます。
- 日比谷公園
花壇などがある西洋風公園。敷地内には音楽堂やテニスコートも - 東京交通会館
複合商業施設。日本各地の特産品が買えるアンテナショップが集まる - 日比谷シャンテ
大型複合施設。ファッションから生活雑貨まで多彩なショップやビュティ―&リラクゼーション、レストランも - 有楽町イトシア
銀座から有楽町エリアを繋ぐ複合商業施設。有楽町マルイや映画館のヒューマントラストシネマ有楽町が入る - ルミネ有楽町
丸の内と大手町の結節点に立地、働く人をメインターゲットにした商業ビル - 有楽町マリオン
銀座の待ち合わせの定番のからくり時計(マリオンクロック)が有名な複合商業施設
江戸時代の有楽町周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
八重洲【中央区】

東京駅西側一帯を指す「丸の内」に対し、東側一帯を指すのが「八重洲」。隣接する丸の内・大手町・有楽町・日本橋・京橋とともに、日本最大のビジネス街を構成します。日本の陸の玄関口として常に進化を続ける活気あふれる街です。
歴史的背景
この「八重洲」という地名は、江戸時代初期に日本に漂着したオランダ人『ヤン・ヨーステン(Jan Joosten van Lodensteijn)』が「ヤンヨウス」、「ヤヨウス」などと呼ばれたことに由来するといわれています。ヤン・ヨーステンはオランダのデルフト市の名家の出身で、家康に召し出されて外交顧問を務め、外交交易について進言したり、通訳として活躍しました。幕府から日比谷堀端に屋敷を与えられ、その屋敷があった場所が「耶麻武(ヤン・ヨーステン)」と呼ばれ、やがて彼の屋敷にちなんで和田倉門から日比谷にかけてのこの堀の岸を「やよす河岸」「八重洲河岸」と呼ぶようになりました。しかし、昭和4年(1929)の町名変更で本来の八重洲という地名は丸の内となってしまい、かつて外濠川に架かっていた八重洲橋がその名を残すことになります。
八重洲橋は、明治17年(1884)、外濠川の呉服橋と鍜治橋との間に地名にちなんで架けられ(東京駅東側の八重洲口中央口交差点付近)ました。一旦、大正3年(1914)東京駅の開業にともない取り壊されましたが、関東大震災後の大正14年(1925)、震災復興再開発事業の一環として再度架橋され、昭和23年(1948)に外濠川が埋め立てられるまで存在していました。そして、八重洲橋撤去後の昭和29年(1954)、日本橋呉服町・槇町が改称して、橋の名にちなみ八重洲という町名が生まれました。これで、東京駅を中心として、かつての八重洲があった西側が「丸の内」、橋を渡った対岸の東側が「八重洲」とする位置関係になりました。
江戸時代には、東海道や中山道などの五街道の起点となる日本橋に近く、物資の集散地として発展しました。明治時代に入り、1914年に東京駅が開業すると、八重洲口側は当初、荷物や郵便物の取り扱いが中心で、駅舎も簡素なものでした。しかし、戦後復興期を経て、駅前広場の整備や百貨店の進出など、商業地としての開発が本格化しました。特に、高度経済成長期以降は、オフィスビルや商業施設が次々と建設され、東京のビジネス、そして観光の要衝としてその存在感を高めていきました。
現在の八重洲の特徴
現在の八重洲は、大規模な再開発が進み、未来志向の都市空間へと変貌を遂げています。
- 東京の新たな顔
- ビジネスと商業の融合
- 交通利便性の高さ
- 再開発による進化
東京駅八重洲口に直結するエリアであり、バスターミナルやタクシー乗り場が集中し、日本の交通のハブとしての機能は絶大です。近年完成した「東京ミッドタウン八重洲」など、大規模複合施設が次々と誕生し、国内外からの訪問者を迎える東京の新たなランドマークとなっています。
高層オフィスビルが林立するビジネス街でありながら、地下街「八重洲地下街(ヤエチカ)」をはじめ、多様な商業施設や飲食店が充実しています。出張やビジネスで訪れる人々はもちろん、ショッピングやグルメを楽しむ人々で常に賑わっています。
JR線に加え、東京メトロ丸の内線・東西線、都営浅草線など複数の路線が利用可能で、都内各所へのアクセスはもちろん、新幹線を利用した地方都市への移動も極めてスムーズです。
八重洲・日本橋・京橋エリア一体での大規模な再開発プロジェクトが進行中であり、国際的なビジネス交流拠点、そして災害に強く環境に配慮した次世代の都市空間へと進化を続けています。
- 八重洲地下街(ヤエチカ)
東京駅八重洲口の地下に広がる日本最大級の地下ショッピングモール。東京駅直結で便利 - グランルーフ
東京駅八重洲口の南北を繋ぐ商業施設。帆型の大屋根、街の景色を望む歩行者デッキが特徴 - 京橋エドグラン
東京駅東のショッピングモール。高さ約31mの吹き抜けのある京橋中央ひろば(ガレリア)は待ち合わせに最適 - 東京スクエアガーデン
落ち着いた雰囲気の商業施設。個性豊かな名店などが揃う - 東京宝くじドリーム館
ナンバーズやロト6などの抽選会が行われていて、その模様を見学できる
江戸時代の八重洲周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
お茶の水【千代田区】

千代田区の北東部に位置するお茶の水は、御茶ノ水駅を中心としたエリアを指す通称で、千代田区の神田地区の一部(神田駿河台や外神田)とその北西側の文京区湯島南部を含みます。神田川の渓谷美を望む高台に広がり、その名の通り「水の都」東京の面影を残しつつ、古くから学術と医療、そして文化の中心地として独自の発展を遂げてきた街です。教育機関や医療機関が多く、明治大学・日本大学・杏雲堂病院・東京医科歯科大学・順天堂大学などがあります。
表記は主に地名の時は「お茶の水」、駅名は「御茶ノ水」と使い分けられます。「お茶の水」は、かつてお茶の水で創設され、現在文京区大塚にあるお茶の水女子大学の名前です。
歴史的背景
高台に位置し、神田川が深く削り取られた景観は、江戸時代から景勝地として知られ、多くの浮世絵にも描かれました。
「お茶の水」という地名の由来は諸説あります。一つの説によれば、お茶の水は「御茶の湯」という意味で、かつて神田川の渓谷の近くに、将軍のお茶用の水に使われた名泉があったことが由来とされています。
現在の順天堂病院あたりにあった禅寺高林寺の庭内から湧き出た水で入れたお茶を、鷹狩に訪れた二代将軍秀忠に出したところ大変気に入り、それから毎日将軍に献上するようになったことから、寺は「御茶水高林寺」と呼ばれ、この一帯を「お茶の水」と通称するようになりました。この清泉は寛文元年(1661)に行われた神田川の拡張工事などで川底に沈んでしまいましたが、その名だけが残りました。
明治時代に入ると、この地の静かで学術に適した環境が注目され、東京大学医学部(現在の東京医科歯科大学)や明治大学、日本大学、順天堂大学など、多くの大学や専門学校、病院が次々と設立されました。これにより、お茶の水は一躍「学術と医療の街」としての地位を確立しました。
また、関東大震災や第二次世界大戦の戦火を乗り越え、戦後には楽器店街が形成されるなど、多様な文化が息づく街へと発展していきました。
現在のお茶の水の特徴
現在のお茶の水は、歴史的な重みを持ちながらも、常に活気に満ちた個性豊かな街として、その魅力を発信しています。
- 「学生街」と「医療の街」
- 楽器の街
- 交通の要衝
- 多様な文化が共存
日本を代表する数多くの大学や専門学校が集積し、全国から学生が集まる「学生街」としての顔は健在です。それに伴い、古書店や学生向けの飲食店も多く見られます。また、大学病院や総合病院が集中する「医療の街」でもあり、最先端の医療を提供しています。
明治大学の裏手から神田駿河台にかけて広がるエリアには、日本有数の楽器店街が形成されています。ギター、ドラム、ピアノなどあらゆる楽器が揃い、国内外の音楽愛好家やプロミュージシャンが訪れる聖地となっています。
JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線、千代田線のお茶の水駅を中心に、複数の路線が乗り入れ、都心へのアクセスが非常に便利です。駅前には聖橋や湯島聖堂、ニコライ堂といった歴史的建造物も点在し、歴史散策も楽しめます。
学生や医療従事者、音楽関係者など、多様な人々が行き交うことで、お茶の水独自の文化が育まれています。アカデミックな雰囲気と、音楽やサブカルチャーが混在する、魅力的なコントラストがこの街の大きな特徴です。
- 神保町よしもと漫才劇場(旧神保町花月)
よしもと漫才劇場の東京版拠点。 - マーチエキュート神田万世橋
万世橋の遺構を整備した商業施設。神田川を望めるオープンデッキも - 神田神社(神田明神)
江戸の街を見守る総鎮守。江戸下町のシンボル的存在。神田祭を行う
▶パワースポット「神田明神【神田神社】」について - 秋葉原電気街
エレクトロニック・ゲーム・アニメ・マンガなどのオタク文化を発信する人気のスポット
江戸時代のお茶の水周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
後楽園【文京区】

文京区後楽園は、江戸時代初期に徳川家康によって整備が始まった「神田上水」と深く結びついています。当時、江戸は臨海地域であったため、飲料水の確保は大きな課題でした。家康は家臣に命じて上水網を整備し、小石川上水(後に神田上水に拡張)が江戸の重要な水源となりました。
後楽園と神田上水
都立庭園の小石川後楽園は国の文化財保護法によって、特別史跡および特別名勝の二つに指定される数少ない場所の一つです。御三家(尾張・紀伊・水戸)の一つ、水戸藩屋敷内の庭園で、江戸時代初期の寛永6年(1629)、水戸家の藩祖徳川頼房が起工し、二代藩主徳川光圀によって完成されました。この光圀とは、テレビの時代劇で有名な「水戸黄門」のモデルです。小石川後楽園の庭は、神田上水から引いた水で中心に池を造り、その周りに日本や中国の名勝を随所に設けた回遊式築山泉水庭園となっています。園名は徳川光圀が招いた中国明の儒学者、朱舜水(しゅしゅんすい)の意見を参考に、中国、北宋(ほくそう)の范仲淹(はんちゅうえん)著『岳陽楼記(がくようろうのき)』に記載されている語句「天下の憂いに先んじて憂え、天下の楽しみに後れて楽しむ」に基づいて名づけられました。
小石川後楽園内には、現在も神田上水の一部であった水路の痕跡が残されています。江戸時代には、この上水の水が園内の大堰川(おおいがわ)や中心にある大泉水(だいせんすい)に引き入れられ、庭園の景観を潤していました。特に、三代将軍徳川家光の時代には、後楽園の池が上水の調整池としての役割も果たしていたと考えられています。
近代以降の水の変化
明治34年(1901年)に神田上水が廃止されると、後楽園の水源も変化しました。昭和8年(1933年)には、新たに井戸が掘られ、その水で庭園が潤されることになります。しかし、園内には神田上水の取水口跡も残されており、当時の面影を偲ぶことができます。
現在の後楽園と呼ばれるエリアは文京区後楽一丁目~二丁目にあたり、その中心には、東京ドームや後楽園ゆうえんち、中央競馬のWINS後楽園などを含む一大レジャー施設や、「後楽園」の名の由来となる小石川後楽園があります。
庭園を彩る水の景観
後楽園には、水の歴史を物語るだけでなく、その特徴的な景観を形成する水の要素が数多くあります。
- 円月橋(えんげつきょう)
- 鳴門の渦(なるとのうず)
- 白糸の滝(しらいとのたき)
水面に映る姿が満月のように見えることから名付けられた橋で、当時の高度な土木技術が用いられています。
池と木曽谷の落差を利用して作られた水の流れで、見る者を楽しませました。
かつて姿を消していましたが、2020年に大泉水の水を水源として復活し、再び園内に雄大な流れを見せています。
後楽園の水は、江戸の歴史と文化を映し出す貴重な存在であり、その変遷は日本の都市における水利用の歴史を物語っています。
- 東京ドーム
読売ジャイアンツの本拠地。野球だけではなくコンサートや各種イベントも開催 - 野球殿堂博物館
野球に関する資料を展示した博物館。偉大な選手のバッドやユニフォームなど展示 - 東京ドームシティ
東京ドームに隣接する商業施設「ラクーア」やアトラクションや宇宙ミュージアム「TeNQ」、スポーツ施設など
▶テーマパーク「東京ドームシティアトラクションズ」について - スパラクーア
スパを中心としたレジャー施設。都内で天然温泉が楽しめるリラクゼーション空間 - 東京ドームホテル
東京の美しい夜景が一望できる高層ビル。巨人戦チケットとセットのプランもあり - 小石川後楽園
江戸時代に水戸藩の屋敷内に造られた庭園。四季を彩る様々な植物が広がる都会のオアシス - 文京シビックセンター
文京区役所が入る高層ビル。25階には無料の展望ラウンジがあり、晴れた日は富士山も望める
江戸時代の後楽園周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
番町【千代田区】

江戸の武家屋敷から続く、由緒正しき住宅街の魅力
千代田区番町は、皇居の西側に位置し、「一番町」から「六番町」まで名がつく、都内でも有数の歴史と格式を誇る高級住宅地です。皇居の西側千鳥ヶ淵を臨み、北は靖国通り、南は新宿通りに挟まれたエリアを指します。その歴史は江戸時代に遡り、現代に至るまで独特の魅力で人々を引きつけています。
番町は山の手の代表的な住宅地の一つで、日本ではじめての高級住宅地と言われていますが、現在は、かつての大邸宅はほとんど姿を消し、高級マンションやオフィス中心のビル街への変貌もみられます。地域内にはイギリスやベルギーなどの大使館、日本テレビ番町スタジオなどが存在し、また、歴史ある名門校も多い文教地区でもあります。
徳川家康が置いた「番衆」の地
番町の名の由来は、江戸城を警護するために徳川家康が置いた「大番組」と呼ばれる武士たち(大番頭)の組屋敷があったことにあります。江戸城大手門の警護を担う「番衆(ばんしゅう)」が駐屯したことから、「番町」と呼ばれるようになりました。大番頭は設立当初、一番組から六番組まであり、この名目が現在の一番町から六番町に引き継がれています。しかし区画は何度か改編され、江戸時代の大番組の組番号と現在の町目の区画は一致してはいません。
番町を表すことわざに「番町の番町知らず」というのがありますが、これは、樹木が鬱蒼とする人気のない所に、表札もない同じような造りの旗本屋敷ばかりが密集していたため、住民でさえ地理を認識することが困難であったことから生まれました。そのような町の雰囲気からか、「番町皿屋敷」や「吉田御殿」、「番町七不思議」などの怪談も生まれています。
近世初頭に番方の屋敷町として成立した番町は、時代が下ると医師や学者、幕府御用絵師の住吉・板谷家などが住むようになります。維新後、武家の世は終わり、明治元年(1868)、新政府によって番町一帯の旗本屋敷は収公され、旗本たちは江戸を去ります。空いた屋敷地に東京府の奨励で桑・茶畑が造られましたが、二年ほどで中止になり、代わって華族や新政府高官の邸宅が立ち並び、次第に閑静な住宅街としての現在の姿を形成していきました。
都心にありながらの落ち着きと緑
番町は、都心にありながらも豊かな緑と落ち着いた雰囲気が大きな特徴です。大通りから一本入れば、閑静な住宅街が広がり、歴史を感じさせる邸宅や趣のあるマンションが立ち並びます。碁盤の目状に整備された町並みは歩きやすく、文教地区としての性格も強く、小学校や中学校などの教育機関が多く集まっています。
歴史・文化と利便性が融合する街
番町の魅力は、その歴史的背景と現代的な利便性が高次元で融合している点にあります。
- 洗練された住環境
- アクセスの良さ
- 豊かな自然と文化
- 教育機関の集積
高い品格と安全性を兼ね備えた住環境は、多くの方に選ばれる理由です。
複数の地下鉄駅(半蔵門駅、麹町駅、市ヶ谷駅など)が徒歩圏内にあり、都内主要駅へのアクセスは抜群です。
皇居や千鳥ヶ淵公園が近く、四季折々の自然を楽しむことができます。また、国立劇場や多数の画廊・美術館など、文化施設にも恵まれています。
有名な学校が多く、教育熱心なファミリー層にも人気があります。
「番町ブランド」とも称されるこの地域は、単なる高級住宅地にとどまらず、江戸時代から続く歴史と文化を色濃く残し、住むほどにその奥深さを感じさせる、都内でも特別な存在と言えるでしょう。
- 千鳥ヶ淵
皇居北西側のお堀。桜の名所として有名。お堀にはボート乗り場もあり - 番町文人通り
麹町大通りと大妻通りをつなぐ通り。周辺には明治から昭和の作家、文学者たちの旧居跡が並ぶ - 日本カメラ博物館
一番町にある博物館。カメラや写真の企画展を定期的に開催 - 東郷元帥記念公園
三番町にある公園。元は東郷平八郎連合艦隊司令長官の私邸跡地。邸内にあったライオン像や力石が残る
江戸時代の番町周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
八丁堀【中央区】

江戸の面影と現代が交錯する、歴史とビジネスの街
東京都中央区に位置する八丁堀は、旧京橋区に当たる京橋地域内にあります。東京駅からもほど近く、現代的なビジネス街と歴史的情緒が交錯するエリアで、オフィス街と住宅街が入り混じる独特の雰囲気を持ちます。その名は江戸時代に由来し、数々の歴史ドラマの舞台ともなりました。また、複数の主要バイパス道路に面しているため、交通の便が良い土地です。
同心屋敷が並んだ「八丁」の通り
八丁堀の地名は、江戸時代初期に徳川家康が江戸城下の整備を進める中で、この地に定住させた「与力・同心」たちの組屋敷が、開削された堀の長さ約八丁(約870メートル)にわたって並んでいたことに由来します。特に「八丁堀の同心」は、江戸の治安維持を担う重要な存在として知られ、時代劇などにも「八丁堀の旦那」として頻繁に登場します。彼らは現在の警察官のような役割を担い、この地から江戸の町を見守っていました。八丁堀は江戸文化における象徴的な地でもあります。
八丁堀の七不思議の一つに「女湯の刀掛け」という話がありますが、これは実話で、八丁堀にある銭湯は非常に混むことから、同心たちが混雑を嫌い、特に空いている朝の女湯に入る習慣があったため、普段は置かない刀掛けを女湯にも置くことがあったことから出来た話です。
明治に入ると八丁堀自体は「桜川」と改称されますが、行政区分中に八丁堀の名は残り、現在に至ります。
現在の八丁堀の特徴
現在の八丁堀は、オフィス街としての機能と下町の風情が同居した落ち着いた街並みが特徴です。周辺には老舗の飲食店や銭湯、小規模ながら個性的なカフェも点在しており、ビジネスパーソンや住民にとって居心地のよいエリアとなっています。また、隅田川や佃島、築地も近く、下町情緒を感じられる散策にも最適なロケーションです。
- 桜川公園
八丁堀駅A2出口横の公園。桜シーズンは多くのお花見客で賑わう - 小網神社
強運厄除の神・東京銭洗い弁天の杜。住所は中央区日本橋の人形町エリア - 警察博物館
京橋にある日本の警察の歴史が分かる博物館。体験型展示もあり
江戸時代の八丁堀周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
※参考資料:大石学著『地名で読む江戸の町』PHP新書
東京の街から江戸の暮らしに思いを馳せる 江戸から続く東京の地名シリーズ
投稿者プロフィール
-
「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。
不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。


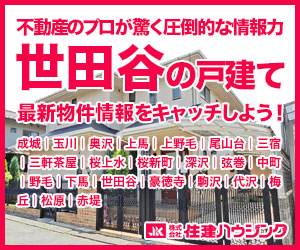

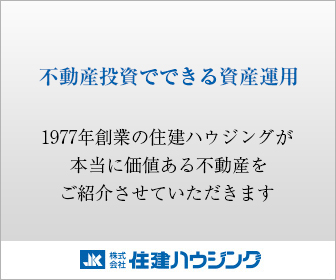
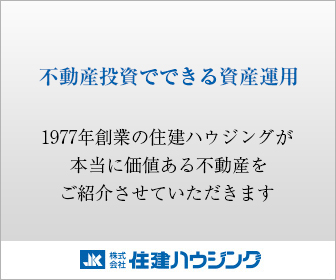





















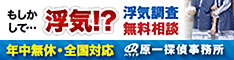
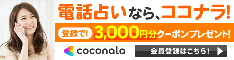










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

