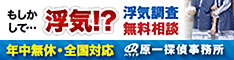武蔵野地域とは、荒川以南・多摩川以北で東京都心までの間に拡がる武蔵野台地のことを指し、武蔵野市のほか、杉並区、練馬区、三鷹市、小金井市、西東京市などが含まれます。
武蔵野台地は青梅街道を頂点として東西に細長く伸びた扇状に広がるエリアで、赤土で不毛の土壌である関東ローム層で厚く覆われているものの、その上には作物栽培に適した黒土の腐植土層が堆積していると考えられます。
武蔵野地域の観光名所としては、武蔵野八幡宮、井の頭弁財天(大盛寺)、杵築大社(きづきたいしゃ)などの神社仏閣や、井の頭公園や武蔵野公園などの自然豊かな公園があります。また、武蔵野市立吉祥寺美術館や三鷹の森ジブリ美術館などの文化施設も人気があります。
中野【中野区】

カルチャーと暮らしが融合する、進化し続ける街
中野(なかの)は、東京都中野区の中心エリアであり、新宿駅からJR中央線で約4分の中野駅を軸に多様な文化と暮らしが交差する活気ある街です。江戸時代は農村地帯でしたが、明治以降は軍の施設が置かれ、大正・昭和期には中野刑務所や警察学校などの行政施設が集中する“官の町”として発展しました。駅周辺は繁華街・オフィス街が形成され、その周辺には閑静な住宅街が広がるエリアです。また、武蔵野台地という強固な地盤を持つ地にあり、災害に強いという特徴があります。
中野の進化の歴史
現在、多くの人々で賑わう中野ですが、室町時代から江戸時代にかけてこの一帯は原野でした。地名の由来は諸説あり確かなことは分かりませんが、一つは、武蔵野の中の位置にある村という意で「中野」と呼ばれるようになった説や、かつては上野、中野、下野もあったが時代とともに上野、下野が消えて中野だけが残った説などが伝わります。ただ、江戸時代より前の古い書物にはすでに「中野」という名称が使われている記録があるため、その歴史はもっと古いと考えられます。
原野が広がる中野の開発が戦国時代から江戸前期にかけて進み、五代将軍徳川綱吉の時代にその景観を大きく変貌させることになります。綱吉が発布した『生類憐みの令』に関連して、幕府の巨大施設である犬小屋がここに設置されました。この施設は野犬を収容し世話をするための場所で、このような犬小屋はすでに江戸近郊の喜多見(世田谷)や大久保(新宿区)にもあり、四谷(新宿区)と共に新設され、中野の犬小屋は、中野御用屋敷、中野御囲(なかのおかこい)と呼ばれました。
中野の犬小屋の面積は16万坪に及び、他地域と比べてはるかに大きく、最盛期には犬が10~30万頭いたとされます。『生類憐みの令』は綱吉が死去し法令が撤回される宝永6年(1709)まで続きました。なお、昭和六年(1931)から昭和四一年(1966)までの間に「囲町」(現、中野区四丁目)という地名が見られましたが、この犬小屋にちなむ名称であることは間違いないでしょう。
享保二十年(1735)、将軍徳川吉宗の命により、犬小屋の跡地の一部(現、中野三丁目周辺)に桃園が造られます。元文三年(1738)には紅白の桃の花が咲き競うまでになり、寛保三年(1743)には御立場(おたちば)という将軍が立つところの後ろに丘を築いて諸大名が桃を見物するようになったため、このあたりは大名山と呼ばれるようになりました。江戸後期には一般庶民も多数見物に訪れるようになり、桃園は江戸市民の遊覧の地として広く知られるようになりました。
明治時代に甲武鉄道が開通すると市街化が進み、大正に入ると駅の乗降客数も増加して、中野は都心部へ通勤する人々のベッドタウンとして成長を遂げました。 その一方で、1970年代以降はオタク文化やサブカルチャーの発信地としても知られるようになります。特に有名なのが「中野ブロードウェイ」で、マンガ・アニメ・フィギュア・アイドルグッズなどを扱う専門店が密集し、秋葉原と並ぶ“サブカルの聖地”として国内外のファンに親しまれています。
駅北口の中野サンモール商店街や昔ながらの居酒屋が並ぶレンガ坂、そして再開発が進む南口エリアなど、昭和の香りと現代的な都市機能が共存しているのも中野の魅力。さらに、周辺には中野セントラルパークや大学・企業の拠点も増え、文化・教育・ビジネスが融合する新たな都市空間へと進化を続けています。
中野は、“好き”を楽しみながら、暮らしも叶う街。どこか懐かしく、それでいて刺激的。多彩な表情を持つ都市の縮図です。
- 中野ブロードウェイ
アニメやマンガの専門店が集まるビルで、サブカルチャーの聖地として有名です - 中野サンモール商店街
中野駅から中野ブロードウェイまで続くアーケード商店街で、飲食店や雑貨店などが並びます - なかの芸能小劇場
演劇やコント、落語などの舞台芸術を楽しめる小劇場です。客席は110席 - 中野区立歴史民俗資料館
中野区の歴史や文化を紹介する資料館で、郷土の文化遺産を保存し展示活用している施設。常設展示や企画展示があります - 中野四季の森公園
約2万平方メートルの広さがある防災公園。四季折々の花や木々が植えられ、噴水や芝生、遊具などがあり、家族連れやジョギングする人などで賑わいます - 中野氷川神社
中野のパワースポット。旧中野村の総鎮守社。厄除・除災招福のご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れます。社殿の裏は区立氷川公園として利用されています - 哲学堂公園
東洋大学の創立者である哲学者の井上円了博士が精神修養の場として創設。国の名勝に指定。園内には古建築物や池、芝生広場などがあり、自然と歴史を楽しめます
江戸時代の中野周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
練馬【練馬区】

自然と都市が調和する、“東京の郊外”の原風景
練馬(ねりま)は、東京都23区の最西端に位置する練馬区の中心地であり、西武池袋線・都営大江戸線の練馬駅を中心に発展した地域です。練馬区は現23区の中で一番新しい区ですが、練馬の歴史は古く、かつては武蔵野台地に広がる農村地帯で、特に江戸時代には豊かな湧き水と肥沃な土地を生かした農業地帯として知られていました。
練馬の地名については諸説あり、一つは、馬を馴らすことを「ねる」と言い、馬を訓練するところであったことから「ねり馬」と呼ばれたという説です。もう一つは、練馬城(後のとしまえん)から名付けられたという説です。他にも、関東ローム層の赤土を練ったところを「ねり場」といった説や、石神井川流域の低地の「奥まったところに沼」=「根沼」が多かった説などがあります。
江戸時代の練馬は水田より畑が多く、ゴボウ・サツマイモ・蕎麦などが栽培されていました。その中で最も練馬の名前を世に広めたのが名産の「練馬大根」でした。
練馬大根のルーツは江戸時代まで遡り、徳川綱吉が尾張の大根の種を取り寄せて栽培させたことに始まります。その後、農家たちが品種改良を重ねて、練馬尻細大根や練馬秋詰まり大根など、江戸東京野菜として認定された品種を作り出しました。練馬大根は水分が少なくて干しやすいので、沢庵漬けの原料としても最適です。練馬の地に馬頭観音が数多く残されていることから、大根を育てるなどの農作業に馬が欠かせないため、人々は馬を大切にしてきたという深い繋がりを窺うことができます。
戦後は急速に宅地化が進み、1947年には板橋区から分離して東京都23番目の区「練馬区」が誕生。以後、住宅地として整備され、ファミリー層に人気の穏やかなベッドタウンとして成長してきました。
現在の練馬駅周辺は、大型スーパーや商業施設、行政機関が集まり、生活の利便性が高いエリアです。一方で、少し歩けば石神井公園や光が丘公園など、緑あふれる自然スポットにも恵まれ、都市と自然が心地よく共存しています。また、練馬は日本のアニメ産業とも関係が深く、多くのアニメ制作会社が集まる地域としても知られています。
練馬は、都会すぎず、田舎すぎず。自然と人の暮らしが調和した、やさしい東京。子育てや日常の落ち着き、ちょっとした文化を楽しむにはちょうどいい場所です。
- 光が丘公園
約60万平方メートルの広さを持ち、芝生広場やバードサンクチュアリなどがあります。春には約290本の桜が咲き、秋はイチョウの黄葉が美しい公園です - 江古田の森公園
江戸時代は将軍の鷹狩場だった緑が多く、のんびり過ごしたい公園 - 豊島園 庭の湯
バーデと天然温泉の施設。バーデとはドイツ発祥の水中運動のこと。天然温泉は練馬区唯一のかけ流し温泉で肌にやさしいアルカリ性単純泉。岩盤浴やお食事処も楽しめる - ワーナーブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター
映画「ハリー・ポッター」シリーズの舞台裏や魔法ワールドの秘密を発見できるウォークスルー型エンタテインメント施設。としまえん跡地に2023年夏オープン。食事や限定商品などのショッピングも楽しめる
▶テーマパーク「ワーナーブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」について
江戸時代の練馬周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
石神井【練馬区】

水と緑に抱かれた、東京の隠れたオアシス
石神井(しゃくじい)は、東京都練馬区の西部に位置し、石神井公園駅を中心に広がる自然豊かな住宅地です。地名の由来は、文字通り「石の神の池」という意味です。『新編武蔵風土記稿』には、村内にある三宝寺池から出現した石剣を神体に石神井社として奉り、その神号をとって石神井村としたと記されています。古くからこの地に伝わる「石神井(しゃくじい)城跡」や「石神(しゃくじん)信仰」など、古代から中世にかけての歴史が色濃く残る地域です。
中でも有名なのが、石神井公園。園内にはボートで楽しめる石神井池と武蔵野三大湧水池の一つである三宝寺池という2つの湧水池があり、武蔵野台地の自然を今に伝える風景として都民に親しまれています。かつてこの地を治めた豊島氏の居城・石神井城跡も残されており、静かな森とともに中世の面影を感じられる貴重な場所です。なお、石神井城は、文明九年(1477)に太田道灌に城を攻められ没落、石神井郷は太田氏の所領となります。その後、徳川家康の関東支配と江戸入城により、幕府の直轄領となりました。
三宝寺池を水源とする石神井川は村内を貫流、この地域の人々に生活用水・農業用水を供給するなど、当時の人々にとって大きな役割を果たしていました。また、三宝寺池は古くから禁猟地であったためか、今日、池の水生植物や湿性植物などの沼沢植物群が国の天然記念物に指定されています。
また、石神井公園周辺は戦後から住宅地として整備され、現在では落ち着いた雰囲気の高級住宅街として人気が高く、自然と文化、暮らしやすさが調和した街並みが広がります。公園を中心に、散策道やカフェ、書店なども点在し、ゆったりとした時間が流れる東京の憩いの地となっています。
石神井は、東京にありながら“武蔵野の原風景”が息づく場所。季節の移ろいを感じながら、心を整えるにはぴったりのまちです。
- 石神井公園
約22.6ヘクタールもの広大な敷地に石神井池と三宝寺池の2つの大きな池があり、ボートやアスレチック遊具などで楽しめます。春には桜、秋には紅葉が美しい公園。三宝寺池には国の天然記念物に指定された沼沢植物群落や石神井城跡などもある - 石神井池
石神井公園内にある人工池。有料ボートあり。池の周りには野外ステージや広場、記念庭園などがある。池の中央にある中之島には、斑点模様が特徴的なホシガメが住んでいる - ちひろ美術館・東京
画家・いわさきちひろと世界の絵本原画の専門美術館
江戸時代の石神井周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
吉祥寺【武蔵野市】

自然・文化・暮らしが揃う、東京で最も“住みたい街”
吉祥寺(きちじょうじ)は、東京都武蔵野市に位置し、中央線・京王井の頭線が交わる便利な交通の要所です。毎年「住みたい街ランキング」上位の常連として知られ、自然・買い物・グルメ・カルチャーがコンパクトに集まる理想の街と称されています。吉祥寺駅周辺は大型商業施設や個性的な店が多く、食べ物や雑貨、ファッションなど何でも揃い、特に若者に人気があります。
吉祥寺は元々、江戸市中の住民たちが移住して開いた土地でした。
明暦三年(1657)一月十八日、江戸の本郷丸山(現、文京区)の日蓮宗本妙寺で火事が起こり江戸市中の大部分を焼いた、世に言う「明暦の大火」と吉祥寺の地は深い関わりがあります。大火後の市街整備の一環として、本郷元町にあった『吉祥寺(きつしょうじ)』が駒込村(どちらも現、文京区)に移転し、これに伴い門前町も同地に移りました。『新編武蔵風土記稿』によれば、万治二年(1659)に農民の十郎左衛門が、駒込の吉祥寺門前に住んでいた浪人の佐藤定右衛門らと相談して現在の武蔵野市東部へ移転、この地を開発して、火事で家や農地を失った住人たちを移住させます。そして、武蔵野台地が新田開発によって広大な農地へと変わっていくと、吉祥寺に愛着を持っていた住人たちは、新田を吉祥寺村と名付けたということです。なお、この地の土壌はあまり肥沃とは言えず、農地はすべて畑地で水田はありませんでした。
以降、寺社と農村が共存する穏やかな地域でしたが、昭和初期から鉄道の発達とともに徐々に都市化が進みました。
現在の吉祥寺を象徴するのが、井の頭恩賜公園。自然豊かな池や森、動物園、美術館が揃い、四季折々の景観を楽しめる市民の憩いの場です。一方、駅周辺には「ハモニカ横丁」やセレクトショップ、古書店、ライブハウスなど、若者文化と昭和の面影が共存する多様な街並みが広がっています。カフェ、映画館、ギャラリーといった文化施設も充実しており、トレンドと個性が交差する東京屈指のカルチャータウンとして、地元住民にも観光客にも愛されています。
吉祥寺は、“東京らしくない東京”の代表格。便利で、緑があって、どこか人情があって。日々を心地よく過ごせる街の理想形です。
吉祥寺村内の井の頭池には、神田上水の水源となる湧水があります。江戸三代将軍徳川家光がこの地を遊覧した際に、「この池は江戸のほとりの井の頭なり」(この池が江戸周辺の池の中で最も優れたものである)と言ったことから、この名がついたとされます。
- 井の頭恩賜公園
日本初の郊外公園として1917年に開園した広大な都市公園。井の頭池を中心に桜や紅葉など四季折々の景色が楽しめます。ボートやサイクリングなどのアクティビティも充実です - 井の頭自然文化園
井の頭恩賜公園内にある動物園。リスやモルモットと触れ合ったり、国内最高齢のゾウ「はな子」(1947年~2016年5月26日)の像を見たりできます - キラリナ京王吉祥寺
京王井の頭線吉祥寺駅に直結する商業施設。30代女性をターゲットにしたファッションやコスメ、雑貨などが揃っています - 武蔵野市立吉祥寺美術館
コピス吉祥寺内にある美術館です。日本画や油彩、版画、写真など約2000点の作品を収蔵しています - ハーモニカ横丁
戦後の闇市の面影を残す駅前商店街。2坪程度の店が約90店ほど集まり、居酒屋や食堂、雑貨屋などが軒を連ねています - 三鷹の森ジブリ美術館
アニメーションの美術館。スタジオジブリの作品や制作過程を紹介するとともに、オリジナルの短編アニメーションや企画展示を行う。館内にはおなじみのキャラクターたちも登場
江戸時代の吉祥寺周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
小金井【小金井市】

玉川上水と桜が育んだ、武蔵野の静かな風景
小金井(こがねい)は、東京都のほぼ中央に位置する小金井市の中心エリアで、JR中央線の武蔵小金井駅を核に発展しています。江戸時代から続く水と緑の文化的なまちであり、現在も「武蔵野らしさ」が色濃く残るエリアです。
小金井の歴史を語る上で欠かせないのが、玉川上水と小金井桜。小金井村の北境を流れる玉川上水は、江戸時代初期、江戸市中への飲料水供給のため開削されましたが、武蔵野地域の生活用水・農業用水としても機能していました。
享保七年(1722)、享保の改革で江戸幕府八代将軍吉宗は、地方御用(農政)も兼務していた大岡越前守忠助に武蔵野台地の開発を命じました。すでに小金井村は上小金井村、下小金井村に分村していて、ここに貫井村を加えた三か村がそれぞれで開発を請け負い、上小金井新田、下小金井新田、貫井新田の三か村が成立しました。各村の名主も梶野新田、関野新田(いずれも現、小金井市)、鈴木新田(現、小平市)をそれぞれ開発しました。
さらに、将軍吉宗の指示と伝えられる山桜の植樹が、寛保年間(1736~44)に小金井橋を中心とする約6キロメートルの長さで行われました。この植樹は、江戸の東の隅田川堤(現、墨田区)、西の中野桃園(現、中野区)、南の御殿山(現、品川区)、北の飛鳥山(現、北区)と、庶民の行楽地を整備した政策の一環として行われたものであったと言え、これが「小金井桜」として江戸の人々に親しまれるようになるなど、観光名所としての役割も与えられていました。江戸後期、小金井桜は庶民や墨客で大いに賑わい、名所としての地位を確立、現在は国指定の名勝となりました。 春には今も上水沿いが桜のトンネルに包まれ、都内有数の花見スポットとなっています。
また、小金井は文化・芸術のまちとしても知られています。広大な敷地を持つ小金井公園内には、江戸東京たてもの園(https://www.tatemonoen.jp/)があり、古き良き東京の町並みを再現した空間で、歴史と建築を肌で感じることができます。一方で駅周辺には商業施設や大学、高層住宅もあり、暮らしやすさも兼ね備えた文教・住宅都市として発展を続けています。
小金井は、武蔵野の面影と現代の生活が共存する、静かな知のまち。自然と歴史に寄り添いながら、丁寧に暮らす日々が似合います。
地名の由来として伝わるのが、文政十一年(1828)成立の『新編武蔵風土記稿』における当時の土地の者の話として、寺の東側に清水(しみず)がわずかに出る泉があり、これを「小金井」と言ったことによる説です。水の乏しかった武蔵野台地において、水が得られる場所は黄金のごとき価値があるということから称されたと考えられます。さらに土地の者の話として、小金井村の付近には温井村/貫井村(ぬくいむら:現、小金井市貫井)など村名に「井」の付く村があり、井戸のあるところをこう呼んだとする説もあると言っています。
- 江戸東京たてもの園
江戸時代から昭和中期にかけての歴史的建造物を移築・復元した野外博物館。江戸の町屋や商店、高橋是清邸など30棟の建物が見学できる - 都立小金井公園
都内最大級の広さを誇る公園。玉川上水沿いに桜並木があり、春には花見客で賑わいます。草地や自然林、SL展示なども楽しめる - 武蔵野の森公園
飛行場の滑走路が一望できる丘や、多目的広場、ドッグランなどがある公園です - 黄金の水(宝永四年六地蔵)
六地蔵のめぐみ黄金の水と言われる井戸水。地下100メートルから汲み上げられた中硬水でミネラルを多く含み、お茶や料理に適するといわれます。有料(500円)登録制で専用の水栓鍵をもらい自由に利用可能(8時~20時間) - 滄浪泉園(そうろうせんえん)
明治時代に造られた湧水を利用した日本庭園。池や滝、茶室などがあり、四季折々の風情を楽しめる。滄浪泉園の湧水は、東京の名湧水57選にも選ばれています
江戸時代の小金井周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
深大寺【調布市】

千年の歴史とそばの香りが漂う、東京の門前町
深大寺(じんだいじ)は、東京都調布市の北部に位置し、都内屈指の古刹・深大寺を中心に、自然と歴史、食文化が息づく趣あるエリアです。
寺の創建は奈良時代の733年と伝えられ、都内では浅草寺に次いで古い寺院として知られています。山号を「浮岳山」、正式名称を「深大寺」といい、水の神を祀る「深沙大王(じんじゃだいおう)」という鬼神に由来するとされています。深沙大王は三蔵法師の天竺(インド)への旅路で流沙川を渡るのを助けたという故事から、水神として崇められる神でもあります。かつては湧き水が豊富で、水に恵まれたこの地に仏教文化が根づいたことが、深大寺発展の基盤となりました。
昔、武蔵国多摩郡柏野村の右近という長者には一人娘がいました。ある日、福満という素性の分からない青年が現れて二人は恋に落ちます。娘の将来を案じた右近夫妻は、娘を池の中の小島に隠して二人の仲を裂こうとしますが、福満は娘に会えるよう深沙大王に祈願します。すると大きな亀が現れ、福満は亀の背に乗って島に渡ることができました。このことから夫妻は二人の仲を許し、福満を婿に迎えます。やがて二人の間に男子が誕生、成長した息子は出家して満巧上人(まんくうしょうにん)と名乗ります。その後、勉強のため唐土に渡り、大乗法相の奥義を極めて帰国。天平五年(733)、深沙大王の社を建立、名前の二文字をとって寺号とし深大寺を建てたといいます。<『江戸名所図解』より>
※深大寺は当初は法相宗でしたが、貞観年間(859~77)に天台宗となります。
地名「深大寺」の由来
深大寺は天台宗の古刹であり、寺名がいつ地名になったかは明確ではありません。しかし、戦国時代には地名としての「深大寺」も見られ、江戸時代には「深大寺村」という村名になります。
明治維新後も深大寺村は残りましたが、明治二二年(1889)の市町村制の施工により、深大寺村を代表として、佐須、柴崎、金子、入間、下仙川、大町、北野の各村の連合で「神代村」が誕生しました。新しい村名が「深大村」とならなかったのは、他の7か村との連合であったからと言われています。
深大寺という地名は神代村の大字となりましたが、昭和三〇年(1955)の調布市の市制施工により調布町と神代町が合併して、調布市深大寺町が誕生しました。現在は神代町という地名は無くなり、深大寺元町、深大寺北町、深大寺東町、深大寺南町として「深大寺」の地名が残っています。
深大寺そば
江戸時代、深大寺は蕎麦で全国に知れ渡ります。深大寺の裏山で取れる蕎麦の実は白く甘みがあり、のど越しの良い白っぽい蕎麦ができます。その蕎麦を食べた人たちが味を評価し、その噂が広まって人気が高まりました。現在も、門前町には名物の「深大寺そば」を食べさせる老舗の蕎麦屋や、茶店、土産物屋などが軒を連ね、週末には観光客で賑わいます。毎年3月に行われる「だるま市」は関東随一の規模を誇り、縁起物を求めて多くの参拝者が訪れます。また周辺には、武蔵野の自然を満喫できる神代植物公園や、調布市民の憩いの場として親しまれる緑地や散策路が点在。古刹と自然、門前町の賑わいが共存する、東京とは思えない落ち着きある空間が広がっています。
大寺は、古き良き日本の風景と、自然に包まれた心のやすらぎが出会う場所。ゆったりとした時間を求める人に、そっと寄り添う門前のまちです。
- 深大寺
天台宗の古刹で、日本三大だるま市の一つが開かれる寺院。門前町には名物の「深大寺そば」を食べさせる蕎麦屋や土産物屋などが並んでいます - 神代植物公園
日本最大級の植物園で、約100,000株のバラや約4,500種の植物が楽しめます。温室や水生植物園もあり。武蔵野の面影が残る園内で、四季を通じて草木の姿や花の美しさを味わうことができる植物園です。水生植物園や深大寺城跡なども見どころです - 鬼太郎茶屋
水木しげるの漫画「ゲゲゲの鬼太郎」に登場するキャラクターをモチーフにした喫茶店。グッズやオリジナルメニューが人気 - 深大寺温泉 湯守の里
関東屈指の黒湯と呼ばれる天然温泉が楽しめる施設。露天風呂やサウナ、岩盤浴もあります - 深大寺城跡
戦国時代に武田信玄の家臣・山県昌景が築いたとされる城跡。石垣や堀跡などが残っています - 深大寺水車館
江戸時代から明治時代にかけて使われていた水車を復元した施設。見学無料です - 国立天文台
武蔵野の自然に囲まれた天文学の研究機関で、無料見学コースや天体観測会が開催されます
江戸時代の深大寺周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
府中【府中市】

古代から続く“国府のまち”、伝統と暮らしが息づく東京の中核地
府中(ふちゅう)は、東京都多摩地域の中央に位置し、京王線・JR南武線が交わる府中駅周辺を中心に発展したエリアです。その名の通り、古代律令制の時代に『武蔵国の国府(地方行政の中心地)』が置かれたことから「府中」と呼ばれるようになり、2000年を超える歴史を持つ由緒ある土地です。なお「府中」という名前は国府の所在地につけられる名称で全国に多く見られます。
武蔵国の府中は奈良・平安の両時代を通じて、政治・経済・文化の中心地でしたが、江戸時代になると中心は東方の江戸に移り、その後は甲州街道の宿場町という交通の要所として存続しました。
甲州街道は五街道の一つで日本橋と下諏訪を結ぶ、幕府にとって重要な街道でしたが、他の街道と比べると、武家や庶民の通行は少なかったようです。
府中宿は甲州街道の江戸日本橋から数えて四番目の宿場であり、俗に府中三町と言われる番場宿・本町・新宿からなっていました。宿場の業務を取り仕切る問屋場は各町にありましたが、同時に業務を行うのではなく、月のうち十二日間を本町、残りを番場宿と新宿が分けて行いました。その後、幕末には三町が均等に十日ずつ受け持つように変わっています。
府中と言えばJRA(日本中央競馬会)の東京競馬場があることも有名です。古代の武蔵国は朝廷に献上する馬の生産地の一つでした。戦国時代から江戸時代にかけては、府中で軍馬の馬市が開かれ、多くの名馬が取引されたと言います。幕府も府中の馬市が開催されると御用馬買い上げの役人を派遣し、将軍用の馬の買い上げを行いました。幕府にとっても府中の馬市は重要なものであったことが伺えます。しかし、江戸後期になると軍馬の需要は減少し、馬市の中心は江戸市中に移ることになり、府中の馬市は次第に衰退していきました。
他に特に有名なのが、関東有数の古社である「大國魂神社(おおくにたまじんじゃ)」です。1900年以上の歴史を誇り、かつては武蔵国の守り神として広く信仰を集めました。毎年5月に開催される「くらやみ祭」は、関東三大奇祭の一つとして知られ、勇壮な神輿渡御や夜の行列で市内が賑わいます。
現在の府中は、多摩地域の行政・商業の拠点として発展しており、駅前には大型ショッピングモールや市役所、文化施設が集積。さらに府中の森公園や郷土の森博物館といった緑と学びの場も多く、歴史・文化・自然・都市機能がバランスよく整った暮らしやすいまちです。
府中は、古代の記憶と現代の利便性が共存する、東京の“歴史の核”のようなまち。深い時間の流れを感じながら、現代的な暮らしを営むことができます。
- 大國魂神社
府中随一のパワースポット。約1900年前の創建と伝えられる神社で、毎年5月5日には「くらやみ祭り」が行われます - 東京競馬場
日本最大の競馬場で、国際的なレースも開催されます。施設内には博物館やレストランもあります - 府中の森公園
広々とした公園で、芝生や噴水、水遊び場などがあります。府中市美術館も併設されています - 府中の森芸術劇場
個性豊かな3つのホール<どりーむホール(多目的)、ウィーンホール(音楽専用)、ふるさとホール(伝統芸能・演劇)>を持つ施設。様々な展示や公演が行われており、芸術を身近に感じることができます
江戸時代の府中周辺を現代地図で見る(外部サイト「れきちず」)
※参考資料:大石学著『地名で読む江戸の町』PHP新書
東京の街から江戸の暮らしに思いを馳せる 江戸から続く東京の地名シリーズ
投稿者プロフィール
-
「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。
不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。



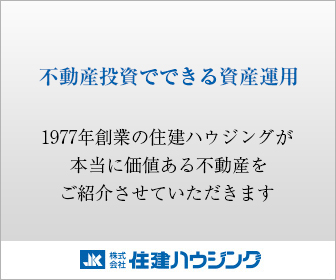
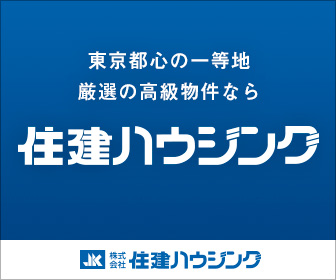



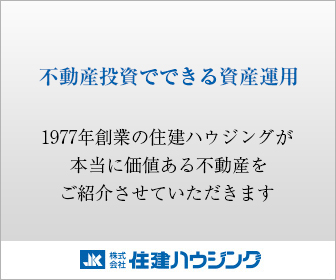




















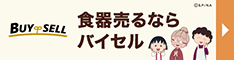
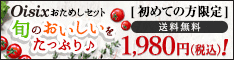










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説