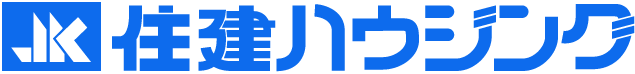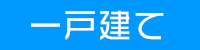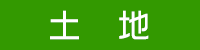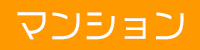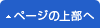住宅の買い時を見極めるための金利動向や税制などのまとめサイト
令和6年度税制改正の概要
自民、公明両党は2023年12月14日、2024年度与党税制改正大綱を決定しました。今回の税制改正大綱は、賃上げ促進と国内投資促進を重点的に措置した内容となっており、これらの税制改正が、日本の経済成長と国民生活の向上に寄与することを期待しています。
賃上げ促進については、従来の賃上げ促進税制の控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件を創設。従来の4パーセントに加え、5パーセント、7パーセントの賃上げを促すことで、より一層の賃上げを実現しようとしています。また、赤字決算の中小企業も賃上げに取り組めるよう、新たに繰越控除制度を創設しました。当期の税額から控除できなかった分を5年間繰り越すことで、構造的・持続的な賃上げを後押しします。
国内投資促進については、半導体、電気自動車等、国として長期的な戦略投資が不可欠となる分野を選定し、10年にわたって法人税を減税する「戦略分野投資促進税制」を創設しました。また、特許権や人工知能(AI)分野の著作権で得た所得に対して30パーセントの所得控除を認める「イノベーションボックス税制」も創設しました。これらの制度により、海外に遜色無い制度で無形資産投資を後押しします。
子育て世帯への支援については、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充といった措置が盛り込まれました。
- 賃上げの拡大により、国民の購買力向上や経済成長の加速が期待
- 国内投資の促進により、雇用の創出や技術革新の進展が期待
- 子育て世帯への支援の拡充により、子育て世代の負担軽減や子育て環境の整備が期待
※これらの税制改正は、国会で審議・可決され、施行される必要があります
2024年度税制改正大綱の主な内容
| 定額減税と給付 |
|
|
|---|---|---|
| 扶養控除と子育て支援 |
|
|
| 「賃上げ税制」で中小企業を支援 |
|
|
| 戦略物資・知財生産企業を支援 |
|
|
| 「防衛増税」は先送り |
|
|
| その外の税制 |
|
|
暮らしに係わる主な税制改正
定額減税と給付
所得税3万円、住民税1万円のあわせて一人あたり4万円減税
2024年6月から納税者本人と扶養家族が対象。ただし、年収2000万円超の人を除く
住民税非課税世帯:3万円(23年給付)+7万円給付
所得税を納めていない世帯:10万円給付
上記世帯のうち子育て世帯:子ども(18歳以下)一人あたり5万円を追加給付
- 住民税非課税世帯には、すでに2023年に給付されている3万円に加えて7万円を給付
- 3万円の給付対象ではなかった住民税は納めているが所得税を納めていない世帯にも10万円を給付
- 上記世帯のうち、18歳以下の子ども一人あたり5万円を追加給付
これらの給付時期は、2024年2月から3月にかけて始まる予定
扶養控除と子育て支援
所得税の課税対象からの控除額を年間38万円から25万円、住民税の控除額を年間33万円から12万円に引き下げ
政府は2024年度から所得にかかわらず、児童手当の対象を18歳以下の高校生などに拡大する方針です。
一方で、こうした扶養する親などの扶養控除を引き下げます(所得税は2026年分から、住民税は2027年度分から適用予定)。
なお、控除の縮小に伴う税負担の増加は、年間12万円受け取れる児童手当を下回るため、実質手取りが増える設計としています。
子どものいる世帯39歳以下の若い世帯については、住宅ローン減税の対象となる借入額の上限の引き下げを見送り
2024年から住宅ローン減税の対象となる借入額の上限が引き下げられますが、子どものいる世帯や夫婦のどちらかが39歳以下の世帯については、下記の上限の引き下げを見送り、2023年現在の水準を維持します。
【住宅ローン減税の借入額の上限の引き下げ】
- 省エネや耐震性にすぐれた「長期優良住宅」:5000万円→4500万円
- 消費エネルギー実質ゼロの水準を満たした住宅:4500万円→3500万円
- 省エネ基準に適合した住宅:4000万円→3000万円
生命保険の支払額の一部を所得税の課税対象から差し引く制度の拡充
遺族保障の枠の上限額を現在の4万円から6万円に引き上げ
ひとり親控除の条件の拡大と控除額の拡充
年間の課税所得の制限を500万円から1000万円まで引き上げ、さらに、所得税の課税対象からの控除額を35万円から38万円に拡大
次のページで、住宅に係る税制改正についてまとめました。 → 住宅優遇制度一覧

 0120-172-111
0120-172-111