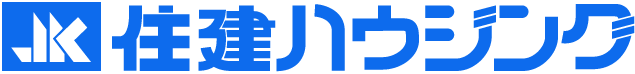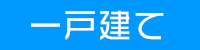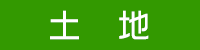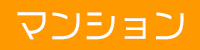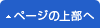住宅の買い時を見極めるための金利動向や税制などのまとめサイト
認定長期優良住宅に係る特例措置
2026(令和8)年4月1日~2031(令和13)年3月31日までの入居
※2026年度改正で5年延長
省エネ性・耐震性・耐久性・可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の令和6年度の認定戸数は145,073戸、ストック数は約174万戸でした。政府は約250万戸(令和12年度)を目標としており、その普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。また、既存(中古)の認定長期優良住宅を取得した場合、所得税(住宅ローン減税のみ)が軽減されます。
なお、所得税、登録免許税は特例措置の適用期限が異なります。期限や減税内容については下記リンク先をご確認ください。
- 所得税(住宅ローン減税・投資型減税)→「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)2026」
- 登録免許税→「登録免許税の軽減2026」
認定長期優良住宅に係る特例措置の内容
認定長期優良住宅に係る特例措置
課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
一般住宅:1,200万円 → 長期優良住宅:1,300万円
- 都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
- 床面積が40㎡以上、240㎡以下であること ※2026年改正より床面積要件の下限が50㎡から緩和
- 一定のハザードエリア内に所在する住宅は対象外
適用を受けるための主な要件
新築一般住宅特例(1/2を減額)の適用期間を延長
・戸建て:3年間 → 5年間
・マンション:5年間 → 7年間
- 床面積が40㎡以上、280㎡以下であること ※2026年改正より床面積要件の下限が50㎡から緩和
- 一定のハザードエリア内に所在する住宅は対象外
適用を受けるための主な要件
認定住宅と一般住宅との税制優遇比較
長期優良住宅や低炭素住宅に認定されると、様々な優遇制度において一般住宅以上の優遇を受けることができます。
| 一般住宅 | 認定低炭素住宅 | 認定長期優良住宅 | |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン控除の対象ローン限度額 ※2024年、2025年入居の場合 |
0円 または2,000万円(2023年中の建築確認が必要です) |
4,500万円 | |
| 所得税控除(投資型減税) ※自己資金購入など住宅ローン減税が利用不可時 |
なし | 標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%相当額を控除 |
|
| 登録免許税(所有権保存登記) 本則0.4% |
0.15% | 0.1% | |
| 登録免許税(所有権移転登記) 本則2.0% |
0.3% | 0.1% | 0.2%【一戸建て】 0.1%【マンション】 |
| 不動産取得税 | 課税標準からの控除額 1200万円 |
課税標準からの控除額 1300万円 |
|
| 固定資産税 | 1/2を減額 ※新築住宅の居住部分120㎡相当まで 【戸建て】新築後3年間 【マンション】新築後7年間 |
1/2を減額 ※新築住宅の居住部分120㎡相当まで 【戸建て】新築後5年間 【マンション】新築後7年間 |
|
| フラット35 | フラット35 | フラット35S金利Aプラン | |
長期優良住宅と低炭素住宅について
長期優良住宅とは
「長期優良住宅」とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のこと。具体的には、国が定めた基準を満たし所管行政庁に申請した上で、長期優良住宅の認定を受けた住宅のことです。「長期優良住宅普及促進法」が2009年6月に施行され、耐久性や耐震性、維持管理体制などの基準が定められました。
| 長期優良住宅に認定されるための条件 | |
|---|---|
| 劣化対策 | 少なくとも100年程度は、構造躯体が使用できること |
| 耐震性 | 建築基準法レベルの1.25倍の地震力でも倒壊しないことなど |
| 維持管理・更新の容易性 | 内装・設備の維持管理が容易であること |
| 可変性 | 将来の間取り変更に必要な躯体天井高を確保すること |
| バリアフリー性 | 共用廊下などに改修に必要なスペースが確保されていること |
| 省エネルギー性 | 次世代省エネルギー基準に適合すること |
| 住戸面積 | 専有面積55㎡以上(地域により40㎡を下限に変更可) |
| 維持保全計画 | 少なくとも10年ごとに点検を実施すること |
低炭素住宅とは
「低炭素住宅」とは、二酸化炭素の排出を抑えるための対策が取られた、環境にやさしい住宅のことです。都市における低炭素化を促進し、持続可能な社会の実現を目指すことを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)が平成24年12月に施行されました。この法律に基づきスタートした制度が「低炭素建築物認定制度」です。都道府県または市(区)から低炭素住宅と認定されることで、様々な優遇制度が受けられます。
| 低炭素住宅に認定されるための条件 | ||
|---|---|---|
| (1)省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を備えていること、かつ低炭素化促進のための対策がとられていること | ||
定量的評価項目 <基準クリア必須> |
外皮の熱性能 | 省エネルギー法で定められる省エネ基準と同等以上の断熱性・日射遮蔽性が確保されていること |
| 一次エネルギー消費量 | 省エネルギー法の省エネ基準よりも、一次エネルギー消費量を10%以上削減していること | |
選択的項目 <2つ以上選択> |
節水対策 | ①節水に役立つ機器の設置(節水便器や食洗器など) ②雨水・井戸水または雑排水を利用する為の設備の導入 |
| エネルギーマネジメント | ③HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の設置 ④太陽光などの再生可能エネルギーによる発電設備と、それに連携した定置型蓄電池の設置 |
|
| ヒートアイランド対策 | ⑤敷地・屋上・壁面の緑化など一定のヒートアイランド対策の実施 | |
| 建築物(躯体)の低炭素化 | ⑥住宅の劣化を軽減する措置が取られている ⑦木造住宅である ⑧構造耐力上主要な部分に、高炉セメントまたはフライアッシュセメントを使用している |
|
| (2)都市の低炭素化促進のための基本方針に照らし合わせて適切であること | ||
| (3)資金計画が適切であること | ||
長期優良住宅は構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性など、省エネルギー性以外にもクリアすべき基準が多くありますが、低炭素住宅はクリアすべき基準が省エネルギー性に特化しているため、長期優良住宅より低炭素住宅の方が認定取得のハードルは低いと言えます。それでも、上記のように低炭素住宅は長期優良住宅と同様な優遇をいくつか受けることが可能です。

 0120-172-111
0120-172-111