地球温暖化対策として、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「2050年カーボンニュートラルの実現」を目指しています。これは、人為的に生み出される二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、人為的な植林・森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味します。
そこで政府は、脱炭素社会に向けた良質な住宅ストックの形成を図るため、長寿命でライフサイクルCO2排出量が少ない【長期優良住宅】や高度な省エネ性能を有する【低炭素住宅】の普及を促進するため、これらの住宅に減税や金利優遇などのメリットを設けています。
この二つの住宅の違いは、【長期優良住宅】が耐震性やバリアフリー化など総合的かつ長期的な視野にたった住宅を指すのに対し、【低炭素住宅】は省エネに特化した住宅を指します。
では、具体的に【長期優良住宅】、【低炭素住宅】とはどのような住宅で、認定されるとどのようなメリットがあるのでしょうか。
1.長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態を保てるように講じられた質の高い住宅のことで、2011年6月に新築を対象とした認定が開始され、2016年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。長期にわたり良好な状態を保つため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性にそれぞれ基準が定められています。
長期優良住宅の認定基準
- 1. 劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること - 2. 耐震性
極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること - 3. 省エネルギー
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること - 4. 維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること - 5. 可変性(共同住宅・長屋)
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること - 6. バリアフリー性(共同住宅)
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共同廊下等に必要なスペースが確保されていること - 7. 居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること - 8. 住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること - 9. 維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること - 10. 災害配慮
自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること
【長期優良住宅(新築)の認定基準[概要]】
| 性能項目等 | 新築基準の概要 | 一戸建て住宅 | 共同住宅等 | |
|---|---|---|---|---|
| 劣化対策 | 劣化対策等級(構造躯体等) 等級3 かつ 構造の種類に応じた基準 | 〇 | 〇 | |
| 木造 | 床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など | |||
| 鉄骨造 | 柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置または、上記木造の基準 | |||
| 鉄筋コンクリート造 | 水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増す | |||
| 耐震性 |
耐震等級(倒壊等防止)等級2 または 耐震等級(倒壊等防止)等級1 かつ 安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合は1/40)以下 または 品確法に定める免震建築物 |
〇 | 〇 | |
| 省エネルギー性 | 断熱等性能等級 等級4 | 〇 | 〇 | |
| 維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級(専用配管) 等級3 | 〇 | 〇 | |
| 共同住宅等のみ適用 |
・維持管理対策等級(共同配管) 等級3 ・更新対策(共用排水管) 等級3 |
|||
| 可変性 | 躯体天井高さ2,650mm以上 | ― | 〇 共同住宅及び長屋に適用 |
|
| バリアフリー性 |
高齢者等配慮対策等級(共用部分) 等級3 ※一部の基準を除く |
― | 〇 | |
| 居住環境 |
地区計画、景観計画、条例による街並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。 ※申請先の所管行政庁に確認が必要 |
〇 | 〇 | |
| 住戸面積 | 一戸建ての住宅 75㎡以上 |
※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積) ※地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある |
〇 | 〇 |
| 共同住宅等 55㎡以上 | ||||
| 維持保全計画 | 以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定 | 〇 | 〇 | |
|
・住宅の向上耐力上主要な部分 ・住宅の雨水の浸入を防止する部分 ・住宅に設ける給水又は排水のための設備 [政令で定めるものについて仕様ならびに点検の項目および時期を設定] |
||||
| 災害配慮 |
災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる ※申請先の所管行政庁に確認が必要 |
〇 | 〇 | |
【長期優良住宅(増築・改築)の認定基準[概要]】
| 性能項目等 | 新築基準の概要 | 一戸建て住宅 | 共同住宅等 | |
|---|---|---|---|---|
| 劣化対策 | 劣化対策等級(構造躯体等) 等級3 かつ 構造の種類に応じた基準 | 〇 | 〇 | |
| 木造 | 床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など (一定の条件を満たす場合は床下空間の有効高さ確保を要しない) |
|||
| 鉄骨造 | 柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置または、上記木造の基準 | |||
| 鉄筋コンクリート造 | 水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増す (中性化深さの測定によることも可能) |
|||
| 耐震性 |
耐震等級(倒壊等防止)等級1(新耐震基準相当) または、品確法に定める免震建築物 |
〇 | 〇 | |
| 省エネルギー性 |
断熱等性能等級 等級4 または 断熱等性能等級 等級3 かつ 一次エネルギー消費量等級 等級4 |
〇 | 〇 | |
| 維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級(専用配管) 等級3 | 〇 | 〇 | |
| 共同住宅等のみ適用 |
・維持管理対策等級(共同配管) 等級3 ・更新対策(共用排水管) 等級3 |
|||
| ※一部の基準において将来的な更新を計画に位置付ける場合、当該基準を適用しない | ||||
| 可変性 | 躯体天井高さ2,650mm以上 または 居室天井高さ2,400mm以上 | ― | 〇 共同住宅及び長屋に適用 |
|
| バリアフリー性 |
高齢者等配慮対策等級(共用部分) 等級3 ※一部の基準を除く |
― | 〇 | |
| 居住環境 |
地区計画、景観計画、条例による街並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。 ※申請先の所管行政庁に確認が必要 |
〇 | 〇 | |
| 住戸面積 | 一戸建ての住宅 75㎡以上 |
※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積) ※地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある |
〇 | 〇 |
| 共同住宅等 55㎡以上 | ||||
| 維持保全計画 | 以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定 | 〇 | 〇 | |
|
・住宅の向上耐力上主要な部分 ・住宅の雨水の浸入を防止する部分 ・住宅に設ける給水又は排水のための設備 [政令で定めるものについて仕様ならびに点検の項目および時期を設定] |
||||
| 災害配慮 |
災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる ※申請先の所管行政庁に確認が必要 |
〇 | 〇 | |
2.長期優良住宅のメリット
1.税制優遇
年末ローン残高の控除限度額が引き上げられ、13年間における所得税と住民税からの最大控除額が一般住宅だと273万円だが、長期優良住宅ならば455万円に増えます。
※2023年12月31日までの入居の場合
ローンを使用しない場合は投資型減税の一択になります。
長期優良住宅の認定を受けるための標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%を、その年の所得税から控除。
※2023年12月31日までの入居の場合。住宅ローン減税との併用不可
一般住宅より税率が引き下げられる
保存登記 0.15%→0.1%
移転登記 一戸建て 0.3%→0.2%
マンション 0.3%→0.1%
※2024年3月31日までに登記申請した場合
税額が1/2減額される特例の適用期間が延長される
一戸建て 1~3年間 → 1~5年間
マンション 1~5年間 → 1~7年間
※2024年3月31日までに新築した場合
2.ローン金利の引き下げ
試算例:借入額3000万円(融資率9割以下)、借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、借入金利1.30%の場合
| メニュー | 返済期間 | 借入金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 | フラット35との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラット35 | 全期間 | 年1.30% | 88,944円 | 37,356,564円 | ― |
| フラット35S | 当初10年目 | 年1.05% | 85,386円 | 36,636,926円 | ▲719,638円 |
| 11年目以降 | 年1.30% | 87,969円 |
3.補助金
国土交通省の採択を受けた施工事業者グループが建てた省エネルギー性や耐久性などに優れた新築・中古の木造住宅(低炭素住宅、長期優良住宅・ZEH住宅【ネット・ゼロ・エネルギー住宅】など)に対して補助金が交付される制度です。
なお、補助は建築の依頼する発注者ではなく、採択を受けたグループに対して行われ、発注者はグループを通じて間接的に補助が受けられる仕組みです。
令和3年度住宅タイプ別の補助上限額(記事掲載時点では令和4年度について未発表)
| 対象となる住宅のタイプ | 補助額上限 |
|---|---|
| ①長期優良住宅 | 110万円 |
| ②高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅) | 70万円 |
| ③ゼロ・エネルギー住宅 | 140万円 |
| ④省エネ改修型 | 定額50万円 |
3.低炭素住宅とは

低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出を抑えるための対策が取られた、環境にやさしい住宅のことで、都道府県または市・区から低炭素住宅と認定されると、税制優遇や光熱費節約などの様々なメリットがあります。
この制度は、2012年12月に「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)が施行され、これに基づき始まった「低炭素建築物認定制度」によります。
低炭素住宅の要件としては、改正省エネ基準から一次エネルギー消費量を10%削減および省エネ基準と同等以上の断熱性能の確保となっています。
認定を受けるための3つの必須基準
- 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を備えていること、かつ低炭素化促進のための対策がとられていること
- 都市の低炭素化促進のための基本方針に照らし合わせて適切であること
- 資金計画が適切であること
上記1については、さらに「定量的評価項目」と「選択的項目」に分かれています。
定量的評価項目とは、認定の為にクリアすべき必須基準であり、「外皮の熱性能」と「一次エネルギー消費量」についての基準です。
外皮の熱性能
省エネルギー法で定められる省エネ基準と同等以上の断熱性・日射遮蔽性が確保されていること
一次エネルギー消費量
省エネルギー法の省エネ基準よりも、一次エネルギー消費量を10%以上削減していること
定量的評価項目に加えて、次にあげる住宅の低炭素化のための措置のうち、2つ以上を選択する必要があります
節水対策
①節水に役立つ機器を設置している(節水便器や食器洗いの機の採用など)
②雨水・井戸水または雑排水を利用するための設備を導入している
エネルギーマネジメント
③HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を設置している
④太陽光などの再生可能エネルギーによる発電設備と、それに連係した定置型蓄電池を設置している
ヒートアイランド対策
⑤敷地・屋上・壁面の緑化など一定のヒートアイランド対策が行われている
建築物(躯体)の低炭素化
⑥住宅の劣化を軽減する措置が取られている
⑦木造住宅である
⑧構造耐力上主要な部分に、高炉セメントまたはフライアッシュセメントを使用している
4.低炭素住宅のメリット
1.税制優遇
年末ローン残高の控除限度額が引き上げられ、13年間における所得税と住民税からの最大控除額が一般住宅だと273万円だが、低炭素住宅ならば455万円に増えます。
※2023年12月31日までの入居の場合
ローンを使用しない場合は投資型減税の一択になります。
低炭素住宅の認定を受けるための標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%を、その年の所得税から控除。
※2023年12月31日までの入居の場合。住宅ローン減税との併用不可
2.ローン金利の引き下げ
試算例:借入額3000万円(融資率9割以下)、借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、借入金利1.30%の場合
| メニュー | 返済期間 | 借入金利 | 毎月の返済額 | 総返済額 | フラット35との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラット35 | 全期間 | 年1.30% | 88,944円 | 37,356,564円 | ― |
| フラット35S | 当初10年目 | 年1.05% | 85,386円 | 36,636,926円 | ▲719,638円 |
| 11年目以降 | 年1.30% | 87,969円 |
3.容積率の緩和
低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連係した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません。ただし、延べ面積の1/20を限度とします。
4.補助金
低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連係した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません。ただし、延べ面積の1/20を限度とします。
国土交通省の採択を受けた施工事業者グループが建てた省エネルギー性や耐久性などに優れた新築・中古の木造住宅(低炭素住宅、長期優良住宅・ZEH住宅【ネット・ゼロ・エネルギー住宅】など)に対して補助金が交付される制度です。
なお、補助は建築の依頼する発注者ではなく、採択を受けたグループに対して行われ、発注者はグループを通じて間接的に補助が受けられる仕組みです。
令和3年度住宅タイプ別の補助上限額(記事掲載時点では令和4年度について未発表)
|
対象となる住宅のタイプ |
補助額上限 |
|---|---|
|
①長期優良住宅 |
110万円 |
|
②高度省エネ型(認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅) |
70万円 |
|
③ゼロ・エネルギー住宅 |
140万円 |
|
④省エネ改修型 |
定額50万円 |
5.認定低炭素住宅が狙い目
長期優良住宅と低炭素住宅には同様のメリットを共有する部分もありますが、認定基準には違いがあります。
一戸建ての長期優良住宅を新築する場合、「劣化対策」、「耐震性」、「維持管理・更新の容易性」、「省エネルギー性」などの項目それぞれについて認定基準を満たす必要がありますが、低炭素住宅の場合のクリアすべき基準は、「省エネルギー性」および「低炭素化のための措置」のみで、認定取得のハードルが低いと言えます。
都市の低炭素化の促進のためにも、住まいの建築、購入をお考えの方は、是非これらの認定制度をご検討ください。
投稿者プロフィール
-
「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。
不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。






















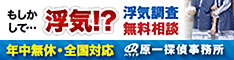
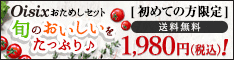







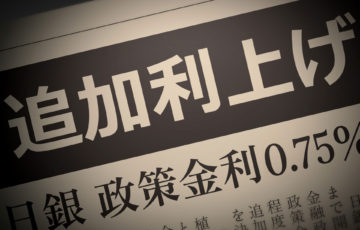


 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

