土地の価格には、目的や算定方法が異なる様々な種類があります。特に重要なのが、「実勢価格」、「公示地価」、「基準地価」、「路線価」です。それぞれの特徴と使い分けを理解しておくと、不動産の売買や相続の際に役立ちます。
土地の価格 主要な4つの指標
土地の価格を表す際、「実勢価格」、「公示地価」、「基準地価」、「路線価」と使用される場面によって異なり、同じ場所を指す価格でありながらそれぞれ金額も異なります。ここでは、それぞれの意味や役割についてポイントをまとめました。
| 実勢価格 | 市場で実際に成立した”リアル”な価格。 売買を考えるときに最も重要。 |
売主と買主の合意で決まる 個別条件(形状、接道、用途)で変動 |
|---|---|---|
| 公示地価 | 国土交通省が毎年公表する標準地の価格。 公共用地取得や相場確認の目安。 |
基準日:1月1日、毎年3月発表 鑑定士が評価 |
| 基準地価 | 都道府県が毎年公表する基準価格。 公示地価の補完として使われます。 |
基準日:7月1日、毎年9月発表 地価の最新動向を把握するのに便利 |
| 路線価 | 国税庁が道路ごとに設定する1㎡当たりの価格。 主に税務で使う基準。 |
基準日:1月1日、毎年7月頃発表 相続税・贈与税の計算に使用 |
実勢価格(じっせいかかく)
実勢価格とは、実際に不動産市場で取引が成立した価格のことです。別名「時価」とも呼ばれます。
金額は売り手と買い手の交渉によって決まり、不動産を売買する際の目安とされます。
一般的に、実勢価格は公示地価の1.1~1.2倍程度が目安とされていますが、立地や建物の状態、需要と供給のバランス、景気など様々な要因によって変動し、必ずしも公的な価格と一致するわけではありません。
土地価格の基本「公示地価(こうじちか)」
公示地価は、国土交通省の土地鑑定委員会が「地価公示法」に基づいて公表する土地の適正な価格です。全国の約26,000地点の「標準地」について、毎年1月1日時点の価格を3月に公表します。この「公示地価」が土地の基本的な価格となり、土地取引の目安とされます。
土地の値段の決め方
公示対象の標準地を評価するのは、土地鑑定士の仕事です。まず、2人以上の不動産鑑定士が評価員として、それぞれ別々に標準地とその周辺の土地の取引事例や収益の見通しなどを調査・分析し、標準地の鑑定評価を行い、更地としての1平方メートルあたりの価格を算出します。こうして得られた地価や土地取引にまつわる情報を、国土交通省の土地鑑定委員会に報告し、最終的な公示価格が決定されます。
使用する場面
- 土地の取引価格の指標として利用される
- 公共事業用地の買収価格の算定基準となる
- 銀行が担保評価をする際の基準として用いられることも多い
基準地価(きじゅんちか)
基準地価は、都道府県が公表する土地の価格で、公示地価を補完する役割があります。毎年7月1日時点の価格を9月に公表します。
なお、基準地価は「都道府県基準値標準価格」が正式名称です。
土地の値段の決め方
各都道府県の知事が、不動産鑑定士の鑑定を参考に決定します。
使用する場面
- 公示地価の空白地域や、都市計画区域外の土地を含む全国の約2万地点が対象
- 半年ごとの地価変動を把握する速報値として、公示地価と合わせて利用されることがある
路線価(ろせんか)
路線価は、相続税や贈与税を計算する際に使われる土地の価格です。国税庁が公表し、毎年1月1日時点の価格を7月に公表します。
土地の値段の決め方
国税庁が定めます。
使用する場面
- 相続税や贈与税の算定に利用される
- 路線価は、公示地価の約80%の水準に設定されているのが目安
- 道路に面した土地の1平方メートルあたりの価格として、道路上に千円単位の数字で表示される
違いのまとめとそれぞれの関係性
これらの価格はそれぞれ異なる目的で使われますが、互いに関連しています。
| 実勢価格 | 公示地価 | 基準地価 | 路線価 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 相続税路線価 | 固定資産税路線価 | ||||
| 価格を決める人 | 売り手・買い手 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 全国市町村 23区は東京都 |
| 主な用途 | 実際の取引 | 土地取引の指標 銀行の担保評価 |
公示地価の補完 | 相続税の計算 贈与税の計算 |
固定資産税 登録免許税 不動産取得税等の計算 |
| 基準日 | 取引成立時 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | |
| 価格水準(目安) | 公示地価の1.1~1.2倍 | 100%(基準) | 公示地価と同水準 | 公示地価の約80% | 公示地価の約70% |
地価の変動は、一般的に「路線価(約80%) → 公示地価(100%) → 実勢価格(110%~)」という関係で理解すると分かりやすいでしょう。つまり、公示地価が土地の価格を評価する最上位の基準です。それぞれの価格は、異なる角度から土地の価値を評価しており、目的に応じて使い分けることが大切です。
また、路線価は課税のための評価基準として「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の二つがあります。前者は国税庁が、後者は全国の市町村(東京23区は東京都)が実施機関です。相続税路線価は公示価格の8割程度、固定資産税路線価は公示価格の7割程度をめどとしています。
土地の値段はなぜ上下するのか?

土地の値段(地価)が上がったり下がったりするのは、株や商品と同じく「需要と供給のバランス」に大きく左右されます。ただし、土地は「唯一無二」で「場所を動かせない」という特徴があるため、特有の要因もあります。主な理由を整理すると次のようになります。
1.需要と供給のバランス
- 需要が高まると値上がり⬆
- 需要が減ると値下がり⬇
新駅の開業や再開発、商業施設の進出などで住みたい・買いたい人が増えると、土地価格は上昇します。
人口減少や周辺環境の悪化、交通の不便さなどで買い手が減ると下がります。
2.経済の状況
- 景気が良いと上昇⬆
- 景気が悪いと下落⬇
企業の投資意欲や住宅購入の動きが活発になり、土地需要が増します。
不動産投資が控えられ、住宅ローン需要も減るため地価が下がります。
3.金利の動向
- 低金利→上昇要因⬆
- 高金利→下落要因⬇
住宅ローンが組みやすくなり、土地需要が高まります。
借入コストが増え、土地購入が難しくなり価格が下がりやすくなります。
4.政策や規制
- 固定資産税や相続税、住宅ローン減税などの制度変更。⬆⬇
- 用途地域の変更(住宅地から商業地への転用など)や都市計画。⬆⬇
5.インフラや街づくり
- 新駅・高速道路・空港などの整備でアクセスが良くなると値上がり。⬆
- 再開発で商業施設や公園ができると人気が出て価格が上がる。⬆
6.社会的要因・地域特性
- 治安や学区、ブランドイメージ(「◯◯区に住みたい」など)。⬆⬇
- 災害リスク(地震、洪水、土砂災害エリア)はマイナス要因。⬇
- 外国人投資家の動きや観光需要なども影響。⬆⬇
土地の値段は「経済(景気・金利)」+「都市計画や再開発」+「地域の人気や安全性」の組み合わせで決まります。言い換えると、人が「そこに住みたい・投資したい」と思うかどうかが一番のカギです。
土地価格の変動が暮らしに与える影響
土地価格の変動は、私たちの生活の様々な側面に直接的・間接的に大きな影響を与えます。地価の上昇と下落、それぞれの側面から見ていきましょう。
地価が上昇すると、一般的に好景気と結びつけられることが多いですが、メリットとデメリットの両方があります。
メリット
- 資産価値の向上
- 担保価値の向上
- 税収の増加
土地や住宅を所有している人にとっては、資産価値が上がり、売却時に高い価格で売れる可能性が高まります。
土地の担保価値が上がるため、金融機関から融資を受けやすくなります。これにより、新たな投資や事業展開がしやすくなる場合があります。
固定資産税や相続税の評価額が上がるため、国や地方自治体の税収が増加します。これにより、公共サービスの充実に繋がる可能性があります。
デメリット
- 不動産取得の困難化
- 税負担の増加
- 家賃の上昇
- 経済の不安定化
価額が上昇するため、土地や住宅の購入を検討している人にとっては、より高額な資金が必要となります。
特に、若い世代や年収が低い層にとっては、マイホームを持つことが難しくなる場合があります。
不動産を所有している人にとって、固定資産税や都市計画税、相続税などの税金が増加します。
特に、相続する予定の土地がある場合、評価額の上昇により相続税の負担が大きくなる可能性があります。
地価の上昇は、賃貸住宅の家賃にも影響を与えることがあります。これにより、家賃を支払って生活している人々の生活費が増加し、家計を圧迫する可能性があります。
急激な地価高騰は「バブル」を招き、経済全体が不安定になるリスクがあります。
地価が実体経済からかけ離れて上昇し、その後暴落すると、不動産を担保にした不良債権が大量に発生し、金融システムに大きな打撃を与えることになります。
地価が下落すると、一見、土地や住宅が安く手に入るメリットがあるように思えますが、社会全体に様々なマイナスの影響を与えることが多いです。
メリット
- 不動産取得の容易化
- 税負担の軽減
土地や住宅の価格が下がるため、購入を検討している人にとっては、手の届きやすい価格帯になります。
固定資産税などの税金が下がるため、不動産を所有している人の税負担が軽減されます。
デメリット
- 資産価値の目減り
- 金融機関への影響
- 消費の停滞
- 地域格差の拡大
土地や住宅を所有している人にとって、資産価値が目減りします。
特に、住宅ローンを組んでいる場合、ローンの残高が不動産の価値を上回る「オーバーローン」の状態に陥るリスクが高まります。
土地の担保価値が下落するため、金融機関は貸し出しに慎重になります。これにより、企業の資金調達が難しくなり、設備投資や事業活動が停滞する可能性があります。
また、ローンの返済が滞ると不良債権が増え、金融システムの安定性が損なわれるリスクもあります。
資産価値の目減りにより、人々が消費を抑え、経済全体の活力が失われる「逆資産効果」が生じる可能性があります。
地価はすべての地域で一様に変動するわけではありません。近年では、利便性の高い都心部や再開発が進む地域では地価が上昇する一方、人口減少が進む地方では地価が下落する「二極化」が顕著になっています。
この格差は、地域経済の活性度や住民の豊かさの差を広げる要因となります。
土地価格の変動は、単に不動産の売買価格が変わるだけでなく、個人の家計、企業の経済活動、ひいては国や地域の財政にまで影響を及ぼす非常に重要な指標です。
- 地価上昇は、所有者や経済全体にメリットがある反面、購入者や賃貸居住者の負担を増やす側面があります。
- 地価下落は、購入者にはメリットがある一方、所有者の資産価値を下げ、経済全体を停滞させるリスクがあります。
そのため、地価の動向は、自身のライフプラン(住宅購入、相続など)を考える上で、また、社会や経済の動きを理解する上で、常に注目しておくべき重要な要素と言えるでしょう。
投稿者プロフィール
- 「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや住まいに関する情報を発信するWEBサイトです。1977年創業の不動産仲介会社住建ハウジングが運営しています。地元密着の視点で、リアルな東京生活をお届けします。























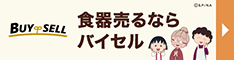











 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
