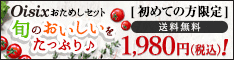住宅ローンとは
住宅ローンとは、住宅(新築・中古・マンション・戸建てなど)を購入するために金融機関から借りる長期の資金です。
通常は20〜35年程度かけて、利息をつけて毎月返済していきます。
住宅ローンは、各金融機関にて様々な種類のサービスが用意されています。大きく分けると、金利の選択肢が多い『民間ローン』と、固定金利で最長35年間借りられる『フラット35』があります。
銀行などが扱う民間ローンは、金利のタイプや引き下げ内容などが金融機関により様々です。
フラット35の方は、住宅金融支援機構と民間の提携によるローンで、金利は窓口となる金融機関が毎月決めています。ただし、対象となる住宅には広さや質などの条件があり、必ずしも利用できるとは限りません。
また、住宅ローンは生命保険会社や信用金庫も取り扱っており、自営業者でも借りやすいケースがあります。他にも、勤務先で財形貯蓄をしている人ならば、公的な財形住宅融資を利用することも可能です。
基本の仕組み
1.借入額
住宅購入価格から自己資金(頭金)を引いた金額が目安。
例:8,000万円の家を購入、頭金を800万円とした場合、借入額は7,200万円
2.返済期間
一般的には「35年ローン」が主流です。
期間を短くすると利息が減る反面、月々の返済額が増えます。
3.金利
借入時に「固定」か「変動」かを選びます(後述参照)。
4.返済方法
主に2種類あります。
- 元利均等返済:毎月の返済額が一定(多くの人が選択)
- 元金均等返済:元金を一定に返す方式(初期の負担が重いが総返済額が少ない)
3つの金利タイプの違い
住宅ローン金利は大きく分けて「固定型」「変動型」「固定期間選択型」の3タイプあります。フラット35は固定型、銀行など民間ローンは変動型と固定期間選択型が基本です。
固定型は全期間の金利が決まってるため、途中で予想以上に金利が上がることはありません。一方、変動型や固定期間選択型は低金利のままなら有利ですが、借りてから金利が予想以上に上昇して返済負担が重くなるリスクがあります。
| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 固定金利型 | 借入時の金利が完済まで一定 | 将来の返済額が確定して安心 | 借入時の金利が高め |
| 変動金利型 | 市場金利に合わせて定期的に変動 | 金利が低い時はお得 | 将来金利が上がるリスク |
| 固定期間選択型 | 5年・10年など一定期間固定、その後変動 | 当初期間は安定 | 期間終了後に金利上昇リスク |
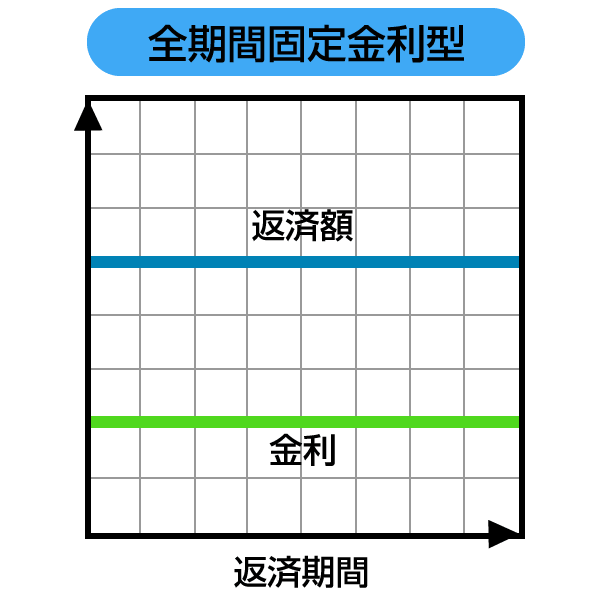 |
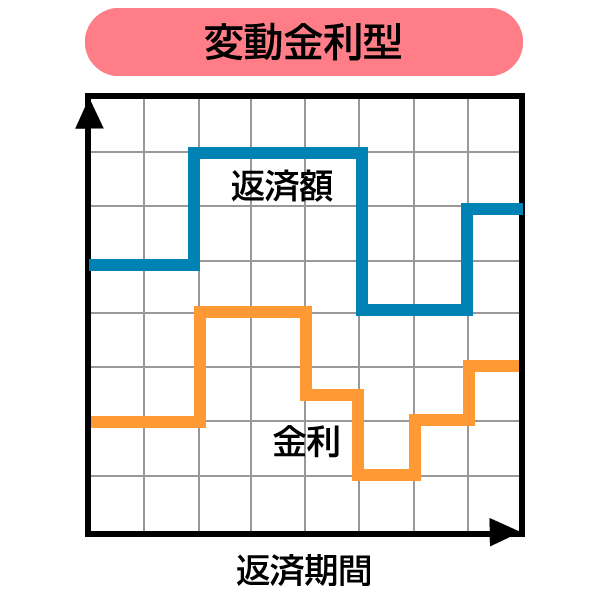 |
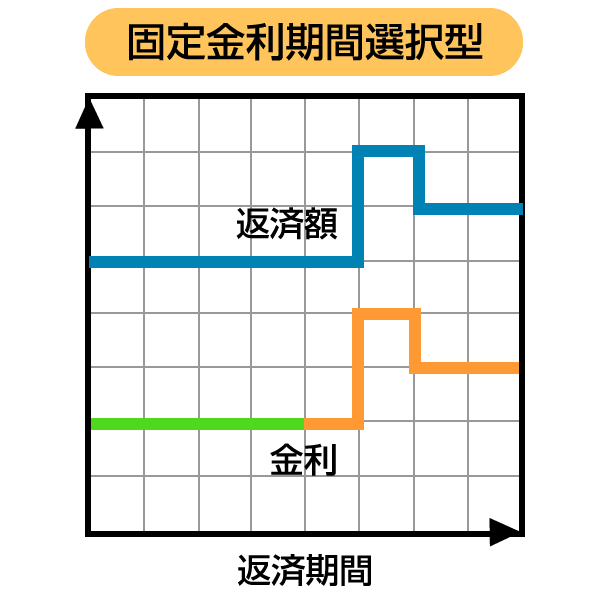 |
|---|---|---|
| 返済期間を通して金利が固定。 フラット35や一部民間金融機関が取り扱い。途中で金利が上がる2段階固定金利型もある。 |
定期的に金利が見直される。 ほとんどの金融機関で年2回金利を見直し、返済額は5年に一度見直される。 |
3年、5年、10年など一定期間だけ金利を固定する。 固定期間終了時にはその時点での金利で、変動金利や異なる固定期間の金利を選ぶこともできる。 |
主な住宅ローンの種類
| 種類 | 提供機関 | 特徴 |
|---|---|---|
| 民間銀行ローン | 銀行・信用金庫など | 変動・固定など自由度が高い。 金利優遇も多い。 |
| フラット35 | 住宅金融支援機構+民間金融機関 | 最長35年固定金利。 返済計画を立てやすい。 |
| 財形住宅融資 | 勤務先経由の財形貯蓄利用 | 条件を満たせば低金利。 |
| 公的融資 (自治体など) |
自治体・公庫など | 特定の条件(子育て・省エネ住宅など)で金利優遇あり。 |
借りる前に確認すべきポイント
1.返済負担率
返済額が年収の25~30%以内が目安
(例)年収600万円→月々返済上限12~15万円程度
2.頭金
物件価格の10~20%程度を自己資金で用意すると、審査に通りやすくなります。
3.諸費用
登記費用・火災保険・仲介手数料などで、購入価格の5~8%程度かかります。
4.団体信用生命保険(団信)
ローン契約者が無くなった場合などに、残りのローンが完済される保険。
銀行ローンでは、ほぼ加入必須です。
金利上昇に備えるために考慮すべきこと
- 変動金利を選ぶ場合は、将来金利が1〜2%上がった場合のシミュレーションをしておく。
- ボーナス返済を組み込みすぎない。
- 返済額に余裕をもって「生活費+貯蓄+返済」が両立できるように。
安心の長期固定金利「フラット35」
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関の提携による長期固定金利の住宅ローンです。都市銀行や主要な地方銀行のほかノンバンクなども取り扱います。
返済期間は15年以上35年以内で1年単位で設定でき、20年以内だと金利が0.2%程度低くなります。融資の対象は新築住宅と中古住宅、ローンの借り換えです。
利用の条件
- 年収に占める返済額の割合が一定の基準以下であること
- 住宅の広さや品質に一定の基準
利用するには、フラット35以外の借入金を含めたすべての年間返済額の年収に占める割合が、一定の基準を満たす必要あり。
申し込み本人だけの年収では基準を満たせない場合は、配偶者など同居家族1人の年収を合算することも可能。合算できるのは収入合算(配偶者など)の年収の全額まで。ただし、合算する額が収入合算者の年収の50%を超える場合は、返済期間が短くなる場合あり。
融資対象となる住宅は、1億円以下の一戸建てとマンションです。床面積は一戸建てが70㎡以上、マンションが30㎡以上。また、住宅の耐久性などについては技術基準が設けられています。
なお、建築確認日が原則として1981年5月31日以前の中古住宅の場合は、住宅金融支援機構の定める耐震評価基準に適合している必要あり。
金利は全期間固定型
金利は全期間固定型ですが、一部の金融機関では11年目から金利が上がる2段階固定型となります。金利水準は金融機関により異なり、新規貸出金利は毎月見直されます。
フラット35では融資を実行するときの金利が適用されます。そのため、未完成新築マンションの申し込みから融資実行までの期間が長い場合は金利の変化に注意が必要です。
保証料や繰り上げ返済手数料が無料
フラット35の申し込みは、扱っている金融機関で年間を通して申し込めます。他の民間融資や財形融資と併せて借りることも可能です。また、借りるときの保証料が不要で、繰り上げ返済手数料も一定金額以上で無料になる点もメリットです。
なお、フラット35の申し込みの際には、住宅が基準を満たしているか適合証明機関に検査が必要で、手数料が新築一戸建てで2~3万円ほどかかります。
さらに、借主が死亡した場合ローンの返済が免除になる団体信用生命保険(団信)に加入するのが一般的です。都銀の住宅ローンなどでは保険料は無料ですが、フラット35では保険料が必要です。
固定金利と変動金利どちらを選ぶべきか?
日本銀行は2024年にマイナス金利政策を解除し、少しずつ金利を引き上げる「正常化」段階に入りました。今後じわじわと金利は上がる可能性がありますが、依然として住宅ローン金利は低水準です。
- 変動金利:0.3~0.6%程度
- 10年固定金利:1.0~1.3%程度
- フラット35(全期間固定):1.7~1.9%程度
今のように金利が低い水準にあるときは、10年固定や全期間固定など固定期間が長いものも利用しやすくおすすめです。とくに10年固定は金融機関の競争が激しく、利用者獲得のため金利が低水準になる魅力があります。また、一定基準を満たす住宅ならば、「フラット35」の金利優遇幅が拡大された「フラット35S」が利用できます(次ページで紹介)。
今もっとも低金利の変動金利を利用すれば、さらに月々の返済額を抑えることができます。しかし、変動金利は金利上昇のリスクがあり、金利が上昇すると総返済額も増えます。金利が上昇し始めたら固定に切り替えるという選択肢もありますが、金利は変動よりも固定のほうが先に上昇することが多いため、切り替えようと思ったときには、家の購入時より上昇した固定金利でローンを組み直しすることになりかねません。
ローンを有利に返済するためには、金利や返済期間をミックスして借りるのも有効です。その際、一方を「短く少なく」借り、繰上げ返済などで、それを早めに完済させることがポイントです。そうすれば、お子様の高校・大学進学などで支出が増える時期までに一方のローンを完済でき、家計が楽になります。
| タイプ | 現在の金利水準 | メリット | リスク/注意点 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 変動金利型 | 約0.4〜0.6% | 今もっとも低金利で月々が安い | 将来の金利上昇リスク | 短期間で繰上返済予定 収入に余裕がある人 |
| 固定期間選択型 (10年固定など) |
約1.0〜1.3% | 当面10年は安心 | 10年後に金利上昇する可能性 | 子育て中、支出が読みにくい時期の人 |
| 全期間固定型 (フラット35など) |
約1.7〜1.9% | 完済まで返済額が変わらない | 金利がやや高め | 長期的に安定を重視する人 |
ケース別おすすめ(2025年版)
ケース①:共働きで今後も安定収入が見込める
おすすめ:変動金利
-
理由:
- 今の金利水準が低い
- 将来金利が上がっても、共働きで対応しやすい
- 早期繰上返済がしやすければ、利息負担を最小限にできる
-
注意点:
- 将来金利が1~2%上昇しても返済できるか試算しておく
ケース②:子育て中で教育費など支出が増える時期
おすすめ:10年固定金利型
-
理由:
- 当面10年間は家計を安定させやすい
- 10年後、教育費のピークが過ぎた後に見直し可能
-
注意点:
- 固定期間終了後に金利が上がる場合があるので、その時点で繰上返済や借換えを検討
ケース③:単収入・今後の収入変動が不安
おすすめ:全期間固定型(フラット35)
-
理由:
- 金利上昇リスクがなく、返済額がずっと一定
- 将来の安心を最優先にできる。
-
注意点:
- 月々の返済額がやや高くなるため、借入額を抑える工夫が必要
ケース④:転勤や売却の可能性がある(10年以内に引越すかも)
おすすめ:変動金利型または短期固定型(3〜5年)
-
理由:
- 短期間で完済・売却予定なら、低金利の恩恵を最大化できる
- 金利上昇リスクにさらされる期間が短い
-
注意点:
- 転居・売却時の残債に注意(家の価格下落や手数料でマイナスになる場合も)
【参考】夫婦ならばペアローンもあり
共働きの夫婦ならば、それぞれでローンを組む「ペアローン」や、どちらか一方をメインとして借りる「収入合算」という方法があります。収入合算はさらに、連帯債務と連帯保証に分けられます。
| ペアローン | 収入合算 | ||
|---|---|---|---|
| 連帯債務 | 連帯保証 | ||
| 利用可能範囲 |
夫婦で別々のローンを借りる。 2種類の住宅ローンが可能 |
2人の収入を足して借入額を増やせる。主債務者は夫で妻は連帯債務者となるが、共に平等に返済義務を負う | 2人の収入を足して借入額を増やせるが、借りるのは夫のみで妻は連帯保証人となる。妻は夫(主債務者)が返済不能時に返済義務を負う |
| 住宅ローン控除 | 夫と妻の2人分利用可能 | 夫と妻の2人分利用可能 | 夫1人分のみ利用可能 |
| 対応できるローンの種類 | 民間ローン、「民間ローン+フラット35(原則同じ金融機関)」 | フラット35、民間ローンの一部 | 多くの民間ローン |
| 事務手数料 | 夫と妻の2人分 | 夫の1人分のみ | 夫の1人分のみ |
| 団体信用生命 | 死亡した人の返済分だけ免除 | 連帯債務者の死亡時は返済免除ならず(※1) | 連帯保証人の死亡時は返済免除ならず |
| 所有権 | 夫と妻それぞれの共有名義 | 夫と妻それぞれの共有名義 | 夫のみの名義(自己資金分は別途) |
※上図は夫が主となり借りるケースを想定
※1 連帯債務者死亡時も返済免除になる連生型の団体信用生命保険もある
投稿者プロフィール
- 「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや住まいに関する情報を発信するWEBサイトです。1977年創業の不動産仲介会社住建ハウジングが運営しています。地元密着の視点で、リアルな東京生活をお届けします。


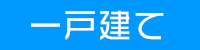
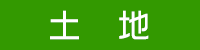
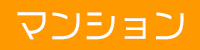





















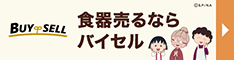
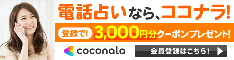









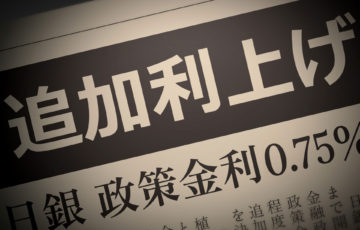
 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説