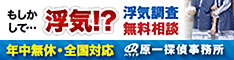2024年3月、日本銀行は長年続いた大規模な金融緩和策の柱となってきた「マイナス金利政策」を解除し、金利を引き上げることを決めました。この歴史的な政策転換は、住宅ローン金利にどのような影響を与え、マイホーム購入を検討している人にとってどのような意味を持つのでしょうか?
金利上昇の仕組み
住宅ローン金利は大きく分けて固定金利と変動金利の2種類があります。それぞれの金利上昇の仕組みについては次の通りです。
1.固定金利
住宅ローンの金利が契約期間中に一定の割合で固定され、返済期間中に金利が変わらないタイプです。 例えば、30年の固定金利ローンを組んだ場合、金利は契約期間中に変動せず、毎月の返済額も一定です。
固定金利を決める要素
- 長期金利: 将来の金利水準に対する市場の期待を反映した金利です。
- 金融機関の金利リスクプレミアム: 金融機関が金利変動リスクを補う為に上乗せする金利です。
- その他の要素: 金融機関の経営状況、競争状況など
金利上昇時の影響
契約時に設定された金利で返済し続けるため、金利上昇の影響を受けません。ただし、新規の借り入れでは、金利上昇の影響を受け、金利が高めに設定される可能性があります。
| メリット | 金利上昇リスクがない 毎月の返済額が一定で家計管理がしやすい |
|---|---|
| デメリット | 金利が低い時期に比べて金利が高めに設定される 途中で金利の見直しや借り換えができない |
2.変動金利
金利が市場の金利指標(例:日銀政策金利、短期国債金利)に連動して変動するタイプです。例えば、変動金利ローンを組んだ場合、金利は定期的に変動し、金利指標が上昇すると返済額も増加します。
変動金利を決める要素
- 短期金利: 日銀の金融政策によって決定される金利です。
- 金融機関の金利スプレッド: 金融機関が利益のために上乗せする金利です。
金利上昇時の影響
金利上昇の影響を受け、毎月の返済額が増加します。逆に、金利が下がれば毎月の返済額が減少します。
| メリット | 金利が低い時期は返済負担が軽い 途中で金利の見直しや借り換えができる |
|---|---|
| デメリット | 金利上昇リスクがある 毎月の返済額が変動するため家計管理が難しい |
金利上昇は避けられないのか?
金利が変動する要因は、主に日銀の政策金利と市場の需給バランスによります。日銀の政策金利が上昇すると、銀行の借入金利も上昇する可能性があり、景気の好転やインフレ期待が高まると金利が上昇する傾向があります。
日銀は、マイナス金利政策を解除し、短期金利の操作を主な政策手段とするとしています。具体的には、日銀当座預金に適用する金利を0.1%とすることで、金融機関どうしが短期市場で資金をやり取りする際の金利「無担保コールレート※」を0%から0.1%程度で推移するよう促します。
※コールレート:日銀が金融政策の操作目標(あるいは誘導目標)として用いている短期金利
現在の日本の経済状況は依然として脆弱であり、急激な金利上昇は景気回復を阻害する可能性があります。そのため、日銀は金利上昇を緩やかに推移させるように努めると予想されます。短期金利は上昇し、変動金利型の住宅ローン金利も今後上昇していく可能性は高いですが、日銀は穏やかな政策転換を図ろうとするため、変動金利への影響は軽微なものと考えられます。
固定金利への影響は限定的?
住宅ローンを固定金利で組む方にとっては、長期金利がどこまで上がるかが重要です。固定金利型の金利は短期金利の影響を受けにくいため、日銀のマイナス金利解除による直接的な影響は限定的と考えられます。しかし、長期金利の上昇により、将来的には固定金利も上昇していく可能性は否定できません。しかし、日銀は金融市場の安定を維持するため、長期金利の上昇を抑制する措置を講じています。
日銀は、2016年9月に導入し、短期金利に加えて長期金利を低く抑え込んできた長短金利操作=イールドカーブ・コントロールと呼ばれる金融政策の枠組みを終了します。ただ、これまでと同じ程度の国債の買い入れは継続し、長期金利が急激に上昇する場合には、機動的に国債の買い入れ額を増額したり、指定した利回りで国債を無制限に買い入れる指値オペと呼ばれる措置を実施したりするとしています。よって、長期金利がすぐに大きく上昇する可能性は低いと言えます。
マイホーム購入を検討している人は?
金利上昇はマイホーム購入のハードルを上げる可能性があります。しかし、上記の通り、金利上昇は緩やかに推移すると予想されているため、急激な変化が起こる可能性は少ないでしょう。現状では、多くの専門家が、「住宅ローン金利が急激に上昇する可能性は低い」と指摘しています。
金利上昇リスクへの対策
金利上昇への対策としては、以下のような方法が考えられます。
- 固定金利型への借り換え: 金利上昇が懸念される場合は、固定金利型への借換えを検討する。
- 繰り上げ返済: 余裕資金があれば、繰り上げ返済を行い、返済負担を軽減する。
- 金利上昇リスクのヘッジ: 金利上昇リスクをヘッジする金融商品を活用する。
なお、ほとんどの金融機関には、金利を急激に上げないようにする緩和措置があります。
例えば、金利が上がっても5年間は毎月の返済額が変わらないとか、返済額は上げても125%までというように上限が設けられていたりします。つまり、既に住宅ローンを組んでいる人は、急にローン返済の負担が増え、家計を圧迫しないような仕組みで守られている可能性があります。
マイホーム購入には慎重な判断が大切ですが
金利の変動は予測できないため、借り入れ前に自身の経済状況やリスク許容度を考慮し、適切な選択をすることが重要です。しかし、様子見をしている間に金利が上昇し、不動産価格も手に届かないところまで上がってしまう可能性があります。もし、住みたい家が今あるのであれば、なるべく早く購入を決断する方が良いでしょう。
最終的な金利の影響は、日銀の政策決定や市場の状況によって異なりますので、最新の情報を金融機関や不動産会社などで確認することをお勧めいたします。
投稿者プロフィール
- 監修者
-
宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士
1996年より大手不動産デベロッパー勤務。首都圏の新築マンション販売のプロジェクトマネージャーに従事。多くの物件の担当し、引き渡しまで一気通貫で経験。
その後ベンチャー系広告代理店にて不動産系クライアントのインターネット集客の支援を行う。
現在は広告代理業と併せ、老舗不動産会社として地域ニーズに合わせた事業を展開。20年以上にわたり住建ハウジングと共同でマーケティング活動を行う。


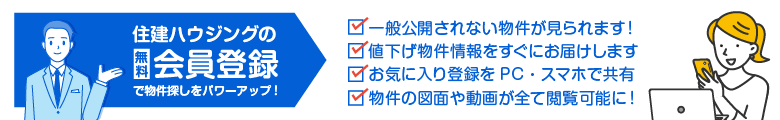




















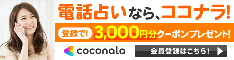
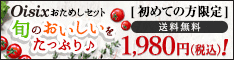










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説