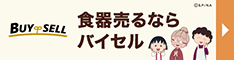相続税の増税による負担の増加
2015年の税制改正では、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、税率構造も見直されたため、実質的に増税となりました。これにより、以前は相続税の対象にならなかった層にも納税義務が発生するケースが増えました。これまで課税対象者は相続全体の4%程度と言われていましたが、相続税の基礎控除が4割縮小になることで、相続税を支払う必要のある人が大幅に増えています。特に、地価の高い東京都区部では、他地区に比べて増加傾向が顕著です。将来、資産価値の高い不動産を相続する可能性のある場合は注意が必要です。
相続税の主な改正点(2015年1月1日から)
(1)基礎控除額の引き下げ【増税⇧】
相続税の計算で最も重要な変更点の一つは、基礎控除額が大幅に引き下げられたことです。
- 改正前: 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
- 改正後: 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、改正前の基礎控除額は8,000万円(5,000万円 + 1,000万円 × 3人)でしたが、改正後は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)に減少しました。この引き下げにより、特に首都圏や都市部に不動産を所有する世帯は、以前よりも相続税の課税対象になりやすくなりました。
相続税基礎控除額 =3000万円+( 600万円×法定相続人の数)
(2)最高税率の引き上げと税率区分の見直し【増税⇧】
基礎控除額の引き下げに加えて、税率構造も見直され、高額な遺産に対する税率が引き上げられました。
相続財産額(法定相続分に基づく取得金額)が2億円~3億円の場合は40%から45%にアップ、6億円超の場合は50%から55%まで引き上げられました。これにより、高額な遺産を相続する場合の税負担がさらに重くなりました。
| 各人の 課税遺産総額 |
平成26年12月31日まで (~2014.12.31) |
平成27年1月1日から (2015.1.1~) |
||
|---|---|---|---|---|
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 1000万円以下 | 10% | – | 10% | – |
| 1000万円超 3000万円以下 |
15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超 5000万円以下 |
20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超 1億円以下 |
30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 |
40% | 1700 万円 |
40% | 1700万円 |
| 2億円超 3億円以下 |
45%↑ | 2700万円 | ||
| 3億円超 6億円以下 |
50% | 4700 万円 |
50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55%↑ | 7200万円 | ||
参照元:国税庁「No.4155 相続税の税率」
(3)控除額、条件の緩和措置【減税⇩】
負担が増える改正がある一方で減税もあります。基礎控除額の引き下げによる課税対象者の大幅増に対する緩和措置として、未成年者控除と障碍者控除の控除額が、1年につき6万円から10万円に引き上げられました。
また、土地の評価額を80%も減額できる小規模宅地等の特例の限度面積が、上限240平方メートルから330平方メートル(約100坪)に拡大。さらに多くの納税者が、 税負担を減らす効果の大きなこの特例の恩恵を受けられるようになりました。
改正による影響とメリット
影響:課税対象者の増加
最も大きな影響は、相続税の課税対象者が増えたことです。改正前は、相続のうち課税対象となる割合(課税割合)は全体の4%程度でしたが、改正後は8%〜9%程度まで上昇しました。特に、これまで相続税とは無縁だと思われていた一般的なサラリーマン家庭でも、持ち家や金融資産の合計額によっては、納税が必要になるケースが増加しました。
メリット:生前贈与の促進
相続税の増税は、多くの人々に相続対策の重要性を認識させました。その結果、節税対策として生前贈与への関心が高まりました。
例えば、暦年贈与(年間110万円までの贈与が非課税)や、相続時精算課税制度(生涯で2,500万円までの贈与を非課税とし、相続時に精算する制度)などの活用が以前より積極的に検討されるようになりました。
また、小規模宅地等の特例といった節税制度への関心も高まり、専門家(税理士など)に相談する人が増え、相続に関する知識が広まるきっかけにもなりました。
相続税はどのくらいかかるのか?
(1)相続人になる人と相続割合
亡くなった人の財産を引き継ぐことを「相続」といい、相続人になる人の順位と相続割合(法定相続分)が決まっています。配偶者は常に相続人となり、法定相続割合は遺産の半分を相続します。そして、残りの半分を子どもたちの人数で均等に分けます。
また、被相続人(故人)に配偶者がいる場合を「一次相続」、その配偶者が亡くなり、相続人が子どもだけとなった場合を「二次相続」と言います。
民法の規定では以下のとおりです(法定相続人が妻と子ども2人の場合)。
- 妻:1/2
- 子ども(2人):残りの1/2を均等に分ける

なお、法定相続分はあくまで「目安」で、遺言や相続人同士の協議で自由に分け方を決められます。ただし、遺留分(最低限の取り分)は、子どもも1/8ずつ、妻は1/4が保証されています。
もし、不動産や株式など分けにくい財産がある場合は、「代償分割」や「換価分割」を使います。
(2)相続税の計算方法
相続税の計算式は次のとおりです。
相続税額 = (課税遺産総額 × 税率) - 控除額
まず、課税遺産総額を決めるために、相続税を計算する上で最も重要な「基礎控除額」を計算します。基礎控除額とは、この金額までは相続税がかからないという非課税枠のことです。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
次に、「課税遺産総額」を算出します。課税遺産総額は相続財産から「基礎控除額」を引いた金額です。
- 課税遺産総額 = 相続財産 ー 基礎控除額
相続財産に含まれるのは、被相続人が所有していた預貯金や現金・株式などの金融資産のほか、不動産や会員権など換金できるものが対象です。それ以外に、みなし相続財産となる死亡保険金や死亡退職金なども、一定の非課税額を除いた分が対象となります。なお、相続財産から差し引けるものは、仏壇や仏具などの非課税財産、借金などがこれに該当します。
(3)相続税の計算例
例えば、遺産総額が1億円で、相続人が妻と子供二人のケースを考えます。
1.法定相続分
民法の規定では以下のとおりです。
- 妻:1/2
- 子ども(2人):残りの1/2を均等に分ける
2.基礎控除の計算
まず、相続税を計算する上で最も重要な「基礎控除額」を計算します。基礎控除額とは、この金額までは相続税がかからないという非課税枠のことです。
- 基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
- 法定相続人の数:3人(妻と子ども2人)
- 基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
今回のケースでは、
3.課税遺産総額
基礎控除額がわかったので、次に相続税がかかる「課税遺産総額」を計算します。これは、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額です。
- 遺産総額:1億円
- 基礎控除額:4,800万円
- 課税遺産総額:1億円-4,800万円=5,200万円
この5,200万円が、相続税の計算対象となる金額です。
4.各人の法定相続分に応じた課税対象額
課税遺産総額5,200万円を、法定相続分で配分して、それぞれの相続税額を計算します。
- 妻:5,200万円×1/2=2,600万円
- 子どもA:5,200万円×1/4=1,300万円
- 子どもB:5,200万円×1/4=1,300万円
5.相続税の速算表(抜粋)
それぞれの課税対象額に税率をかけます。相続税の速算表(抜粋)は以下の通りです。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
6.各人の税額(相続税の総額を求める手順)
4の速算表より、各人の税額を計算します。
- 妻:2,600万円 → (1,600万×15%-50万)=340万円
- 子どもA:1,300万円 → 1,300万円×15%-50万円=145万円
- 子どもB:1,300万円 → 1,300万円×15%-50万円=145万円
相続税の総額:340万円+145万円+145万円=630万円
この合計が、本来納めるべき相続税の総額となります。
7.配分(実際の相続税負担)
相続税は相続した割合に応じて負担します。
- 妻:630万円 ×(5,000万円÷10,000万円)=315万円
- 子どもA:630万円 ×(2,500万円÷10,000万円)=157.5万円
- 子どもB:630万円 ×(2,500万円÷10,000万円)=157.5万円
8.配偶者の税額軽減特例の適用
実際には妻には「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」があります。
- 配偶者は 1億6,000万円 or 法定相続分までの取得には税金がかかりません。
- 今回、妻の相続分は5,000万円(法定相続分)なので、妻の相続税は0円。
すると、相続税は 子供2人分のみになります。
- 子どもA:157.5万円
- 子どもB:157.5万円
合計:315万円
まとめ
遺産総額1億円、法定相続人が妻と子供2人の場合、本来の相続税総額は630万円ですが、配偶者の税額軽減特例を適用することで、最終的に納税するのは子供たちの分だけとなり、合計315万円の相続税が発生することになります。
しかし、この特例を適用するためには遺産分割協議が完了していること、および相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに申告することが必要です。
なお、この例では受贈者が3人で2対1対1と、法定相続分どおりの配分でしたが、遺産分割の仕方によっては納税額が変わる可能性がありますので、具体的な状況に合わせて専門家(税理士など)に相談することをお勧めします。

配偶者がいる一次相続の場合、配偶者は 『1億6,000万円』または『法定相続分』までの取得は非課税という「配偶者の税額控除の特例」があります。これは、配偶者の相続税の税額が大幅に軽減できる大変有利な特例ですが、適用の際には注意するべきポイントがあります。
1次相続の際、控除枠を利用して多くの相続財産を非課税で配偶者に相続させても、いずれその配偶者が亡くなり、子どもたちがそれらの財産を相続すれば結局相続税の課税対象になります。つまり、子どもなどの2次相続人にとって、1次相続で配偶者が多く相続することは必ずしも得策であるとはいえません。
残された配偶者が、多額の固有財産を持っている場合には、1次相続での配偶者の相続額を抑えなければ、2次相続の際の相続税の負担が大きくなってしまいます。将来発生する配偶者の相続(2次相続)における相続税まで考えれば、1次相続において配偶者の税額軽減の特例を最大限に適用しない方が、相続税の合計額は少なくなる場合があります。
「相続登記申請」の義務化
所有者不明土地の解消へ向けて、2024年4月1日「相続登記の申請」が義務化されました(※「住所・氏名変更登記申請」も同じく義務化)。
相続によって不動産を取得した相続人は、相続の取得を知った日(あるいは遺産分割が成立した日)から3年以内に、登記申請(物件の名義変更手続き)しなければなりません。正当な理由がなく怠ると、10万円以下の過料が科せられます。
相続登記を怠るケースとしては、親族と共有していた土地など想定外の相続不動産が存在していた場合、突然、相続登記の義務が及ぶことがあります。もちろん登記だけではなく、相続税の課税対象になり、納税義務が発生する場合もありますので注意が必要です。
また、2024年4月1日より前に相続が発生していた不動産についても、「2024年4月1日から3年以内(=2027年3月31日まで)」に申請する必要があります。
次へ⇒ 【2】相続税の節税対策
投稿者プロフィール
- 「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや住まいに関する情報を発信するWEBサイトです。1977年創業の不動産仲介会社住建ハウジングが運営しています。地元密着の視点で、リアルな東京生活をお届けします。

















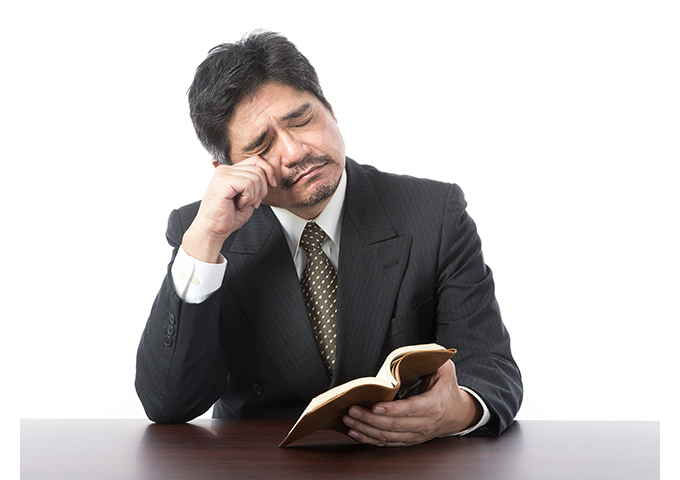







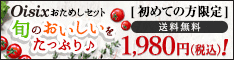
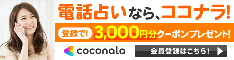










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説