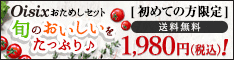住宅購入で親から金銭的な支援を受ける際には「贈与税」のルールを知っておくことが大切です。贈与税の税制度や特例について理解しておくと節税につながります。今回は住宅購入で親から支援を受ける際の、贈与税の概要や特例を適用するための手続きを解説します。
住宅購入で親から支援を受ける時に気をつけたい「贈与税」

住宅購入時に親から支援金を受け取ると贈与された金額によって「贈与税」が発生します。「贈与税」とは、個人から個人へ財産が無償で移転された際に課される税金です。
一般社団法人不動産流通経営協会の調査によると、住宅購入の際に親から支援を受けた世帯の割合(受贈率)は住宅購入者全体の14.2%です。親から支援を受ける人は贈与税の仕組みについて理解しておく必要があります。
贈与税は年間110万円を超える贈与に対して超えた部分に税金が課される仕組みです(暦年課税制度)。たとえば、親から500万円の支援を受けた場合、このうち110万円を超える部分の390万円に対して贈与税が課されます。
年間の贈与額が110万円を下回る場合には贈与税は発生しません。110万円を超えると金額に応じて10%から55%の税が課せられます。
出典:一般社団法人不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査(2022年度)」
贈与税の制度は主に2種類:「暦年課税」と「相続時精算課税」
| 暦年課税 | |
|---|---|
|
適応対応者 |
年間110万円を超える贈与を受けたもの |
|
課税金額 |
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を差し引いた額に金額により所定の税率を乗じた金額 (18歳未満と18歳以上で税率は異なる) |
| 相続時精算課税 | |
|---|---|
|
適応対応者 |
原則として60歳以上の父母または祖父母などから年間110万円を超える贈与を受けた18歳以上の子または孫のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫 |
|
課税金額 |
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除し、さらに限度額2,500万円の特別控除を差し引いた額に一律20パーセントの税率を乗じた金額 |
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。基本的には「暦年課税」が適用されて110万円を超える贈与に対して贈与税が課されるのですが、適用条件に該当する場合には「相続時精算課税」が選択できます。
一度「相続時精算課税」を選択すると、同一関係の贈与税については全て「相続時精算課税」が課され、暦年課税には戻れません。「相続時精算課税」は贈与の段階で2500万円が特別控除で非課税になるものの、贈与者が死亡して相続が発生した際には、生前に贈与した金額に対して相続税を支払わなければなりません。
住宅購入で親から支援を受ける人が知っておきたい特例と制度
ここでは住宅購入で親から支援を受ける人が知っておくべき特例と制度を解説します。条件に当てはまる人であれば、贈与税の負担を抑えられる可能性があるので正しく知っておきましょう。
住宅取得資金贈与の非課税の特例
「住宅取得資金贈与の非課税の特例」とは、親や祖父母から住宅取得などの目的で贈与を受けた場合に一定の条件を満たすと、贈与税が非課税となる制度です。
具体的な条件としては以下が挙げられます。
贈与者が直系尊属である(父母や祖父母)
贈与の目的が自己の居住用住宅の新築や取得、増改築である
受贈者が18歳以上
この特例を利用することで、省エネ等住宅の場合は「1000万円」それ以外の住宅の場合は「500万円」までの贈与が非課税となります。
なお、特例を適用するには、贈与を受けた年の翌年3月確定申告の締め切りまでに税務署に申告する必要があるので注意しましょう。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税」は、以下の条件に当てはまる贈与を受けた場合に、2500万円(特別控除額)までの贈与税の支払いを一時的に猶予できる制度です。
贈与者が60歳以上の直系尊属
受贈者が18歳以上
贈与の段階では2500万円までの金額が非課税となり、2500万円を超える部分に対して一律20%の税率をかけた贈与税を支払います。ただし、贈与者が死亡して相続が発生した際には、贈与を受けた金額を相続税として納税しなければなりません。
基本的には支払う期間の先送りなのですが、贈与税は金額に応じて10%から55%の税率であるため、一定金額までは相続税の方が贈与税よりも税率が低くなります。そのため贈与時点での税負担だけでなく支払う税金の総額も安く抑えられるケースも出てくるでしょう。
ただし、相続時精算課税を一度選択すると同一関係の贈与税については全て「相続時精算課税」が課され、暦年課税には戻れません。選択は慎重に考える必要があります。
適用するには贈与を受けた年の翌年3月の確定申告までに税務署へ申告しなければなりません。
住宅購入で親から支援を受ける人が必要な手続き
住宅購入で親から支援を受ける際に必要な手続きを解説します。手続きの流れを知っておき、期限に余裕をもって申告しましょう。
すべての申告において、申告の内容に応じた申告書とマイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。申告書は税務署や国税庁のHPから入手できます。
「暦年課税」の場合の一般的な贈与税申告の手続き
「暦年課税」を選択した場合は、住宅購入で親から受けた支援金が110万円を超えた場合に、翌年の確定申告で贈与税に関する申告を行います。確定申告書に贈与の内容を記入して、「暦年課税」で贈与税を申告する人用の申告書を選び管轄の税務署に提出しましょう。
「相続時精算課税」を選択する場合の申請手続き
「相続時精算課税」を選択する場合は「相続時精算課税」用の申告書を選んで申告します。さらに追加で「相続時精算課税選択届出書」の記入も必要です。
提出の際には、必要書類としては贈与者の直系卑属(子や孫)であることを証明する「戸籍謄本または抄本」を添付します。戸籍謄本または抄本は時間に余裕をもって入手しておきましょう。
「住宅取得資金贈与の非課税の特例」の申請手続き
「住宅取得資金贈与の非課税の特例」用の申告書に記入の上、以下の書類を添付する必要があります。
戸籍謄本あるいは抄本
源泉徴収票など(合計所得金額を明らかにする書類)
受贈者の戸籍の附票の写し(住所履歴の証明)
登記事項証明書
省エネ等住宅の場合は「住宅性能証明書」など
「住宅取得資金贈与の非課税の特例」と「相続時精算課税」は併用できるため、両方の適用を受ける場合には、それぞれの必要書類を用意しましょう。
確定申告書の提出期限は例年2月1日から3月15日です。提出方法には、オンライン提出(e-Tax)や管轄の税務署への来所、郵送が可能です。e-Taxにおける申告は令和7年3月よりスマホでもできるようになりました。
添付書類や手順について詳しくは下記で確認しておきましょう。
出典:国税庁「贈与税の申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。また、どのように行えばよいのですか。」
住宅購入で親から支援を受ける人が注意しておくこと
住宅購入で親から支援を受ける人が注意すべきポイントを解説します。ポイントを理解した上でどのような選択をするかを決めましょう。
遺産分割時のことを考える
遺産相続には特定の相続人に対して最低限の相続分を取得できる「遺留分」という権利があり、生前贈与の財産も遺留分の対象となる場合があります。
民法では相続開始前「10年以内」の相続人への特別受益にあたる生前贈与は「遺留分」とされます。この特別受益の中に「住宅を購入するための住宅資金を贈与」が含まれています。つまり、親に住宅購入の支援として贈与され、10年以内に親が亡くなった場合、他の相続人はその贈与額から遺留分を請求できるのです。
そのため、支援を受ける際には、親だけでなく家族全体で話し合いを行い、必要であれば遺産分割協議書などで支援金をどのように扱うか明確に決めておくのが望ましいといえるでしょう。兄妹や親族の中で自身のみ支援を受けることがある場合は特に注意が必要です。
特例を併用について考える
住宅購入時に親から支援を受けた際に条件が合えば、税制上の特例を併用して税負担を軽減できます。たとえば「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」と「相続時精算課税制度」は併用可能です。「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」と「住宅ローン減税」との併用もできます。
ただし、特例を併用する際には各制度の適用条件や制限をしっかりと理解しておきましょう。たとえば、相続時精算課税を使うと、同一関係の贈与で暦年課税制度は使えません。
親の家を相続する可能性があるか考える
親の家を相続する可能性の有無についても確認しておきましょう。一般的に住宅を取得した際には不動産取得税や登録免許税がかかります。しかし親の家を相続する場合には不動産取得税はかかりません。登録免許税に関しても固定資産税評価額が基準になるため新築の登録免許税よりも安く済む可能性があります。
また、一度でも自身の持ち家に住んだ後に、親の家を相続すると「小規模宅地等の特例」が使えず、相続税の負担を抑えられません。
新築住宅を援助してもらう場合と親の家を相続する場合の、どちらが節税になるかは個別のケースによりますので、それぞれのメリット・デメリットをよく検討しておきましょう。
住宅購入で親から支援を受けることに関するよくある質問
Q. 贈与を申告しなかった場合はどうなる?
A.
贈与税の申告をせずそのことが判明した場合、払うべき贈与税に加えて「加算税」という税が課せられます。加算税の税率はどのような状況で申告漏れがあったのかによって変わります。最も重い加算税は「重加算税」と呼ばれ、45〜50%の税率です。贈与を意図的に隠ぺいして申告せず、これを税調査により指摘された場合に課せられます。
Q. 住宅取得資金贈与を頭金にしないと非課税にできない?
A.
「住宅取得資金贈与の非課税の特例」を適用する場合、非課税にならない可能性がでてきます。この特例は贈与された資金を住宅購入に使用することが適用の条件です。
「頭金にすべし」と明記されているわけではありませんが、すべての金額を年内に住宅購入に使用すると考えた場合、住宅ローンなどではなく頭金として使用することが最も証明しやすく適当であるといえるでしょう。
家具や電化製品の購入など支援金を他の用途で使用した場合は非課税の対象外になるので注意してください。
Q. 住宅を建てる土地への支援の場合、減税の特例は使用できる?
A.
住宅を建てるための土地を取得するための支援に対しても、減税の特例は使用できます。ただし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築しなければなりません。
Q. 住宅購入で親から支援を受ける人の平均額は?
A.
一般的には、親からの支援額は数百万円から数千万円に及ぶことが多いです。平均的には、新築の場合「1000万円程度」、中古で「600万円程度」となっています。特例を使用して非課税になる金額を把握しつつ、親からの支援がどの程度になるかを確認しておきましょう。
出典:一般社団法人不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査(2022年度)」
住宅購入で親から支援を受けるときは特例を賢く活用しよう!
住宅購入で親から支援を受ける際の贈与税に関する特例を解説しました。「相続時精算課税」や「住宅取得資金贈与の非課税の特例」を活用すると親からの支援にかかる贈与税を金額に応じて非課税にできます。住宅購入において親からの支援を受ける人は適用条件や手続きの方法を把握して、賢く活用してみましょう。
東京都の不動産購入・売却・売買の相談に関しては、住建ハウジングを利用するのがおすすめです。住建ハウジングでは、豊富な経験と実績を活かし、お客様一人ひとりのニーズに合わせた丁寧なサポートを提供しています。お問い合わせや詳細については、下記のリンク先から公式ホームページをご確認ください。不動産に関するさまざまな情報発信も行っています。
投稿者プロフィール
- 監修者
-
宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士
1996年より大手不動産デベロッパー勤務。首都圏の新築マンション販売のプロジェクトマネージャーに従事。多くの物件の担当し、引き渡しまで一気通貫で経験。
その後ベンチャー系広告代理店にて不動産系クライアントのインターネット集客の支援を行う。
現在は広告代理業と併せ、老舗不動産会社として地域ニーズに合わせた事業を展開。20年以上にわたり住建ハウジングと共同でマーケティング活動を行う。





















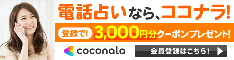
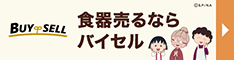










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説