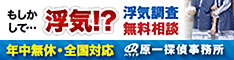2025年の基準地価が9月16日に、国土交通省や各都道府県から公表されました。
基準地価は、毎年7月1日時点の土地の価格を調査したもので、土地取引の指標の一つとされています。
1.全国平均は4年連続の上昇、上昇幅が拡大
全用途の全国平均は前年比+1.5%で、4年連続の上昇となりました。上昇幅は前年の+1.4%を上回り、バブル期(1991年:+3.1%)以降で最大の上昇率となりました。
用途別では商業地・工業地の上昇が顕著
| 用途 | 全国平均の変動率 (前年比) |
傾向 |
|---|---|---|
| 全用途 | +1.5% | 4年連続の上昇で、上昇幅が拡大。 |
| 住宅地 | +1.0% | 都市部や交通利便性の良い地域、リゾート地などで堅調。 |
| 商業地 | +2.8% | インバウンド需要の回復や再開発、店舗・ホテル需要の増加が地価を押し上げ。 |
| 工業地 | +3.4% | EC拡大に伴う物流拠点や製造業の再編により、都市近郊や高速道路沿いのニーズが高まり、用途別で最も高い上昇率。 |
2.三大都市圏と地方圏の動向
三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏):
- 全用途で+4.3%(東京圏+5.3%、大阪圏+3.4%)と、上昇が続いています。
- 特に商業地の上昇幅が大きい傾向が見られます。
- ただし、名古屋圏では前年より上昇幅がやや縮小しています。
地方圏:
- 全用途で+0.4%と、プラス圏を維持しています。
- 地方都市(札幌・仙台・広島・福岡)の上昇は続いていますが、前年と比べると上昇幅が縮小している地点もあります。
- 観光地(北海道、沖縄)や半導体関連企業の進出地域(北海道千歳市など)で地価の高い上昇が目立っています。
3.最高価格地点・上昇率トップ地点
商業地最高価格地点
東京都中央区銀座2丁目「明治屋銀座ビル」(4,690万円/㎡)。20年連続でトップを維持しています。
上昇率トップ(商業地)
北海道千歳市の地点が全国で最も高い上昇率を記録しました。
4.東京で地価が上昇する主な要因
地価が上昇する背景には複数の要因があります。
- 再開発・駅周辺整備の進展
- インバウンド回復・観光需要
- 都市への集中・人口流入
- 低金利・金融緩和環境
- 希少性と規制制限
- 期待先行・ミラーニューメント
都心・駅近くでは建て替えや複合施設化、商業施設併設型開発などが相次ぎ、用途転換・高付加価値化が進んでいます。こうした“改良”は周辺地価を押し上げる効果があります。
コロナ禍後の観光需要回復が都心・観光地の商業地需要を強めています。浅草など観光集客力のある地域は特に目立つ伸びを見せています。
東京都は首都圏の中核として人口・企業・勤労者の集積力が強く、需要の“重心”が東京に偏る流れは継続しています。
借入コストが抑えられる環境は、不動産取得・投資を促す要因になります。資金の不動産流入を後押し。
都心一等地では空地が少なく、新規供給余地が限られているため希少性が価格を支える要素となります。また用途規制・建蔽率・容積率など法規制も上昇幅を“底支え”する役割を果たします。
将来の物価上昇や資産価値維持を見越した「実物資産へのシフト」需要。期待が先んじて買われる動きが出やすい。
また、最新の研究でも、観光が地価上昇に寄与する局面は「スーパースター都市」的な集積地点において顕著になる傾向が指摘されており、東京はまさにその典型例になっている可能性があります。
まとめ
2025年の基準地価は、都市部の再開発やインバウンド需要の回復、物流・産業(特に半導体関連)の需要を背景に、全国的に地価の上昇基調が続いており、特に商業地と工業地が好調です。しかし、地域によっては上昇幅の鈍化や、利便性の低い地域での地価の横ばい・微減も見られ、二極化の傾向も示されています。
投稿者プロフィール
-
「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。
不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。























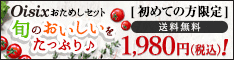
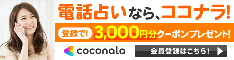










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説