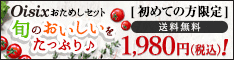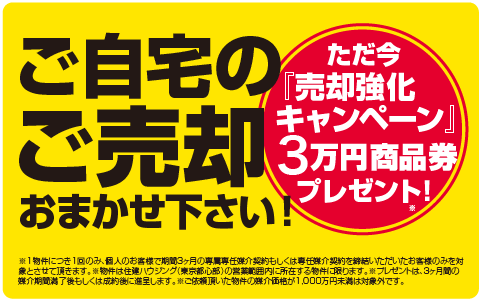不動産を共有名義で所有している場合、売却には共有者全員の同意が必要です。しかし、意見が合わない、連絡が取れないといった理由から、売却が思うように進まないケースも少なくありません。この記事では、共有名義の不動産を円滑に売却するための手続きや注意点、トラブル時の対応策について解説します。共有名義不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
共有名義とは?
不動産の「共有名義」とは、ひとつの物件に対して複数人が共同で所有権を持っている状態を指します。具体的には、土地や建物などの不動産を夫婦やきょうだい、親子など複数の名義人がそれぞれ一定の割合で所有しているケースです。
このような名義の持ち方は、たとえば夫婦で住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合や、親から相続を受けた実家を兄弟で分ける場合などに見られます。共有名義では、各所有者が「共有持分」と呼ばれる持ち分を持ちます。持分は出資額や相続の割合に応じて決まり、登記簿にも明記されます。なお、共有者のことを「共有持分権者」と呼ぶこともあります。
共有名義には、購入時の資金分担を分散できるというメリットがある一方で、単独での意思決定が難しく、税金などの問題でトラブルも生じやすい点には注意が必要です。
不動産を共有する場合は、将来的なリスクも踏まえた上での慎重な判断が求められます。
具体的な注意点
・売却などの意思決定に共有者全員の合意が必要
・相続などをきっかけに共有者が増えることで状況が複雑化しやすい
・共有者の債務トラブルが波及するリスクがある
どこまで確認が必要?共有者の同意を得る必要のある範囲
| 必要な同意の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 単独で可能 | ●建物の修繕や維持管理 ●不法占拠者への対処 ●相続登記の申請 |
| 過半数の同意が必要 | ●短期の賃貸借契約 ●管理会社や清掃業者との契約・変更 |
| 全員の同意が必要 | ●共同資産の売却 ●大規模修繕や増改築などの構造変更 ●抵当権の設定 ●長期の賃貸借契約 |
共有者は、不動産に対して「共有持分権」と呼ばれる権利を持ち、利用や管理、処分などさまざまな判断に関わることができます。ただし、そのすべてを自由に行えるわけではありません。
不動産の取り扱いには、「単独で対応できるもの」から「過半数の同意が必要なもの」、さらには「全員の同意が不可欠なもの」まであり、判断の重さに応じて求められる同意の範囲が異なります。
とくに売却や大規模なリフォームといった不動産の価値に大きく影響する行為には、原則として共有者全員の同意が必要になります。一方で、清掃や修繕といった維持に関わる行動であれば、共有者の一人でも実行可能です。同意の必要性を正しく理解しておくことで、不要なトラブルや手続きのやり直しを防げます。
共有名義の不動産を売却する5つの方法

共有名義の不動産を手放したいけれど、どんな方法があるのか戸惑う方もいるでしょう。 ここでは、状況に応じて検討できる代表的な5つの売却方法について紹介します。
共有者全員で売却する
共有者全員の合意があれば、不動産を一括して第三者への売却ができます。この方法は、市場価格で売れやすく、手続きも比較的シンプルです。
ただし、共有者の一人でも反対すれば成立しないため、全員の意思を揃える必要があります。共有者が多い場合や、遠方に住んでいる人が含まれている場合などは、連絡や同意の取得に手間がかかることもあるでしょう。売却契約や決済には全員の手続きが必要になるため、代表者を1人決めておくと連絡や書類のやり取りが効率化されます。
他の共有者に自分の持ち分を買い取ってもらう
共有名義の持ち分は、他の共有者に買い取ってもらうことで売却できます。とくに不動産を実際に使っている共有者がいれば、交渉がスムーズに進む可能性が高いでしょう。すべての持分を取得した相手は単独名義となり、自由に売却や活用ができます。
ただし、極端に安い価格で売ると贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。また、共有者が複数いる場合は、誰に売るかを事前に話し合っておくことが大切です。不動産会社を通じて正式な契約を交わすことで、トラブルの予防につながります。
買取業者などの第三者に自分の持ち分だけ売却する
共有不動産、とくに土地の場合は、自分の持分だけを第三者に売却することも可能です。ただし、一般の個人が共有持分を購入するケースは少なく、実際には「共有持分買取業者」と呼ばれる専門業者に買い取ってもらうのが一般的です。
この方法は早期売却につながる反面、対象物件を自由に使えないため、売却価格は大きく下がる傾向があります。また、売却後に業者が他の共有者に交渉を持ちかけ、トラブルになることもあるため、事前に共有者へ一報を入れておくと安心です。可能であれば共有者同士での売却を優先することが、後々のトラブル防止と経済的な損失の回避につながります。
持ち分割合によって分筆する
土地の不動産においては、持ち分割合に応じて分筆することも可能です。分筆とは、登記簿上で一つとされている土地を複数の区画に分ける手続きのことを指します。分筆後は、各自が所有権を持つ土地として、自由に売却できます。
ただし、誰がどの区画を所有するかの話し合いや、専門家による測量などが必要となり、一定の手間や費用が発生します。また、分け方によっては日当たりや形状、接道条件などに差が生じ、資産価値が下がるケースもあるため注意が必要です。分筆を検討する際は、まず不動産会社に相談し、メリットとデメリットを把握したうえで判断するのが望ましいでしょう。
リースバックを利用する
共有者全員の合意が難しい場合でも、リースバックを活用することで、自身の持ち分を売却しながらそのまま住み続けられます。リースバックとは、不動産会社に家を売却し、同時に賃貸契約を結ぶことで、引っ越しせずに現金化できる仕組みです。
一時的に資金を得られる反面、継続的な家賃の支払いが発生します。また、所有権は不動産会社に移るため、将来的に契約更新ができないリスクも否定できません。そのため、長期的な資金計画を立てておくことが重要です。
共有名義の不動産を売却する手順
共有名義の不動産を売却するには、通常の売却とは異なる注意点があります。共有者全員の合意や必要書類の準備など、事前に確認すべきことも多く、スムーズに進めるには段取りが必要です。ここでは、共有不動産を売却する際の主な手順をわかりやすく解説します。
1.共有者全員を正しく把握する
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が不可欠です。相続などで共有者が増えている場合もあるため、登記事項証明書などで最新の所有者を確認しておきましょう。所在不明者がいる場合は、家庭裁判所を通じて代理人を立てる「不在者財産管理人制度」の活用も検討できます。
また、売却費用は持ち分に応じて負担するのが一般的ですが、事前に共有者間で話し合っておくと安心です。
2.不動産会社や専門家に査定を依頼する
| 主な査定の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 簡易査定 |
●近隣の取引事例や市場動向をもとに、概算の価格を算出する |
| 訪問査定 | ●実際に現地を訪れて、建物の状態や立地条件から算出する ●媒介契約の締結時に実施されることが一般的 |
| 不動産鑑定評価 | ●国家資格を持つ不動産鑑定士により価格を評価する ●売却に際して、適正な価格が把握できる |
不動産を適正な価格で売却するためには、専門家による査定を受け、市場価値を把握することが大切です。状況に応じて適切な査定方法を選び、市場動向や建物の状態、立地条件といった要素を総合的に判断しましょう。
3.売却を任せる不動産会社と契約する
売却価格や条件に納得できたら、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約を結ぶことで、不動産会社が価格交渉や売却活動を正式に行えます。媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ依頼できる範囲や報告義務が異なります。契約内容をよく確認し、売却方針に合った契約形態を選ぶことが大切です。
不動産の売却は高額な取引となるため、経験豊富な担当者と連携しながら進めることで、トラブルや価格交渉のリスクを軽減できます。媒介契約は売却の土台となる重要なステップです。
4.売却活動を行う
媒介契約を結んだあとは、不動産会社が広告出稿や販売戦略を通じて購入希望者を募る「売却活動」に入ります。購入希望者との接点を増やし、契約に向けた土台を築いていきます。
よりよい条件で売却するには、物件の印象を高める工夫も欠かせません。必要に応じてリフォームを行ったり、内覧対応を丁寧に行ったりすることで、買い手からの評価が高まりやすくなります。不動産会社と連携しながら、適切な販促活動を進めましょう。
5.買い手と売買契約を結ぶ
条件面で合意が得られた場合、購入希望者と正式に売買契約を結びます。契約書には物件の詳細や売買価格、引き渡し日、支払い条件などが明記され、売主・買主双方が署名・押印することで成立します。
不動産会社の仲介がある場合でも、契約後のトラブルを防ぐには、重要事項説明書や契約内容を事前に確認し、不明点は事前に解消しておくことが大切です。とくに、手付金や残代金の支払い条件については慎重に確認しましょう。
6.決済や登記手続き、確定申告を行う
売買契約を結んだあとは、決済や登記手続き、確定申告といった一連の手続きを進めます。取引金額や提出書類が多く複雑なため、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。
また、不動産売却による譲渡益がある場合には、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要となるため早めの準備を心がけましょう。
共有名義の不動産を売却する際に必要な書類

| 必要な書類 | 概要 |
|---|---|
| 物件の登記簿謄本 | 土地や建物の権利関係を示す公的書類 |
| 売却に関する契約書 | 不動産会社との媒介契約書や買主との売買契約書 |
| 共有者全員分の身分証明書 | 契約手続きに必要な本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
| 共有者全員の印鑑登録証明書 | 実印を証明する書類 |
| 譲渡所得税の申告に必要な書類 | 取得費用や売却費用を示す領収書・契約書など |
| 確定申告で必要な書類 | 譲渡所得の申告に使用する確定申告書や計算明細など |
共有名義の不動産を売却するには、登記簿謄本や契約書、身分証明書など、あらかじめ複数の書類を準備しておく必要があります。とくに、共有者全員分の身分証明書や印鑑証明書に加え、売却後に必要となる譲渡所得税・確定申告のための書類も忘れずに確認しておきましょう。
馴染みのない書類も多く、少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、あらかじめ準備しておくことで、手続きをスムーズに進められます。
共有名義の不動産を売却する前後でかかる費用
| 不動産の売却状況 | 費用の種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 売却前 | 仲介手数料 | 不動産会社に依頼する際の手数料 |
| 測量費用 | 土地の境界・面積を確定するための測量費 | |
| 登記費用 | 権利関係の変更登記における費用 | |
| 修繕・解体費用 | リフォームや建物の解体にかかる税金 | |
| 売却後 | 譲渡所得税・住民税 | 売却益が出た場合に課税される税金 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙の費用 | |
| 登記免許税 | 登記手続き時にかかる税金 |
共有名義の不動産を売却する際には、売却前後でさまざまな費用が発生します。仲介手数料や測量費用に加え、譲渡益が出れば税金もかかります。また、税金や手数料の負担は共有者の持ち分に応じて分けられるのが一般的です。想定外の出費を避けるためにも、事前に必要な費用を確認しておきましょう。
不動産の共有は避けられる?3つの分割方法
| 分割方法 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 換価分割 | 相続財産を売却し、その売却代金を相続人同士で分割する |
| 現物分割 | 不動産などの相続財産を現物のまま相続人同士で分割する |
| 代償分割 | 特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金などを支払う |
不動産を共有名義で所有すると、将来的に売却や管理をめぐる合意形成が難しくなり、トラブルを招くおそれがあります。こうしたリスクを避けるための資産分割の方法として、換価分割・現物分割・代償分割の3つの分割手法が存在します。
代表的な方法は、売却して現金を分ける「換価分割」、不動産を現物のまま分ける「現物分割」、取得者が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」の3つ。それぞれに、平等性・公平性・資金面での特徴があり、財産の内容や相続人の事情に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
東京の不動産売却は住建ハウジングにお任せください

不動産売却を成功させるには、信頼できるパートナー選びが欠かせません。住建ハウジングは、東京23区を中心に地域密着で展開する不動産会社として、豊富な物件情報と高い営業力を強みに、多くの売却実績を築いてきました。売却はもちろん、住み替え・相続・投資など幅広いニーズにも柔軟に対応可能です。
実際に住建ハウジングで「希望通りの売却が実現した」と語るお客様の声を紹介します。

台東区の一棟ビルを売却されたI様の声
相続で受け継いだ一棟ビルを住建ハウジングに依頼し、半年で希望通りの高値で売却できました。情報力と対応力が群を抜いて素晴らしく、相続物件の売却でも親身に相談に乗ってくれました。今後もぜひ依頼したいです。

新宿区の一戸建てを売却されたF様の声
神楽坂のシェアハウスを住建ハウジングに依頼し、予想価格よりも高く1週間で売却が成立しました。スピーディーな売却活動と誠実な対応、チームワークの良さ、何より高値で売却ができたことで大変満足しています。

墨田区のマンションを売却されたS様の声
新居購入時の担当者の親切な対応がきっかけで旧宅売却も依頼しました。
情報収集も早く、何かあれば電話したらすぐに動いてくれるので安心して任せることができて、結果として1年かけて希望価格に近い価格で売却できました。
共有名義の不動産売却についてよくある質問
Q.共有者が遠方にいる場合はどうしたらよい?
A.共有者が遠方に住んでいるなど現地に赴くのが困難な場合は、信頼できる代理人を立て、委任状と本人確認書類を整えることで売却手続きを代行してもらうことが可能です。また近年の法改正により、郵送やオンラインで対応できる場面も増えていることで、柔軟な進行が期待できます。
Q.共有者同士が不仲な場合はどうするべき?
A.第三者を介して冷静な協議を進めるか、調整が困難な場合は法的手続きを検討します。とくに不動産コンサルタントや弁護士など専門家の関与により、冷静かつ客観的な話し合いが期待できます。それでも、協議がまとまらない場合は裁判所に共有物分割請求を行うこともできますが、法的手続きは負担も大きいため、最終手段とするのが一般的です。
Q.共有者が売却に同意しない場合の対処法は?
A.共有者の意見や不安に耳を傾け、丁寧に理由を確認したうえで、売却のメリットや今後の方針を具体的に説明することで、話し合いを進めていきます。 それでも折り合いがつかない場合は、やむを得ず法的手続きを検討することになりますが、金銭面・心情面の両面からも話し合いによる解決が望ましいです。
Q.勝手に共有名義の不動産を売却されてしまったらどうする?
A.売却の有効性を確認し、違法な売却であれば無効契約であることを主張し損害賠償請求を検討します。全員の同意がなければ原則無効であり、違法な売却であれば契約の無効や損害賠償請求が可能です。解体などを防ぐためにも、早急な対応が重要です。
共有名義の不安を解消する第一歩は、専門家への相談から
共有名義の不動産売却は、共有者間の同意形成や法的手続きが必要となる場面もあるため、事前に対応方法を知っておくことが重要です。高額な取引となることからトラブルを避け、円滑な売却を実現するためにも、早期の準備と専門家のサポートが鍵となります。
東京都の不動産購入・売却・売買の相談に関しては、住建ハウジングを利用するのがおすすめです。住建ハウジングでは、共有名義など複雑な案件にも経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。お問い合わせや詳細については、下記のリンク先から公式ホームページをご確認ください。不動産売却に関するさまざまな情報発信も行っています。
投稿者プロフィール
- 監修者
-
宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士
1996年より大手不動産デベロッパー勤務。首都圏の新築マンション販売のプロジェクトマネージャーに従事。多くの物件の担当し、引き渡しまで一気通貫で経験。
その後ベンチャー系広告代理店にて不動産系クライアントのインターネット集客の支援を行う。
現在は広告代理業と併せ、老舗不動産会社として地域ニーズに合わせた事業を展開。20年以上にわたり住建ハウジングと共同でマーケティング活動を行う。












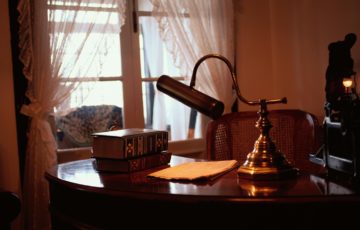










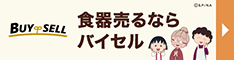
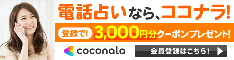







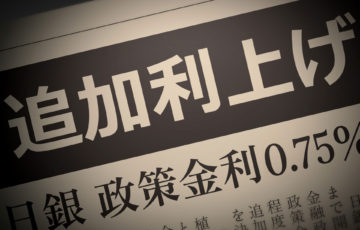


 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説