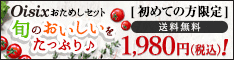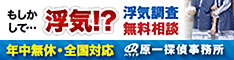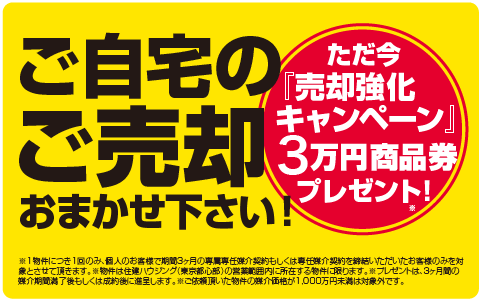「穴を掘ったら地中からお宝が出てきた!」なんて話は、実話・創作問わず誰でも一度は聞いたことがあると思います。日本では、貝塚、古墳、土器、石器などの遺物がある土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」といい、すでに埋蔵文化財の存在が確認されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。土地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかは市区町村の教育委員会が作成している遺跡地図・遺跡台帳で調査できます。文化庁の発表によると、埋蔵文化財包蔵地は全国に約46万ヵ所あり、毎年9,000件程度の発掘調査が行われています。
もしも、購入した土地が埋蔵文化財包蔵地に含まれていた場合、自分の土地から何か貴重なお宝が発見されるかもと期待してしまうかもしれません。しかし、埋蔵文化財包蔵地に家を建てるためには事前に届け出が必要だったり、調査のために工事を中断させられたりするなど、予定通りに家が建てられなくなるリスクもあることを覚悟しなければなりません。
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等を、また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行う。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き、発見者が所轄の警察署へ提出すること。
1.対象地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」にある場合
建築工事の規模に関係なく工事着手60日前までに教育委員会への届けが必要です。届け出をすると「現地調査」、「試掘(しくつ)」が実施されます。
また、自治体によっては、周知の埋蔵文化財包蔵地に近接する場所でも届け出が必要な場合があります。
2.工事が埋蔵文化財に影響すると判断された場合
上記の試掘によって遺跡が確認されたり、工事の影響があると判断されたりしてしまうと、工事自体の計画を変更するか、工事着手前に本格的な「発掘調査」を行い、文化財の記録を残すことが義務付けられます。この場合、発掘費用は開発者(通常、土地所有者)負担となり、工期も大幅に遅れることになります。
なお、個人が営利目的ではなく行う住宅建設等、事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、国庫補助等、公費により実施される制度があります。
3.出土品の取り扱い
文化財保護法により、出土品は所管の警察署長に提出する必要があります。これが文化財らしいと認められる場合、都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑定を行います。そして、文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは原則として都道府県に帰属されます。
4.埋蔵文化財包蔵地に建つ家を売却する際のリスク
- 売却価格が下がる。
- 買主が見つかりにくい。
将来の建て替え時に再度調査が必要になるなどリスクがあるため買主が見つかりにくい。買主がいたとしても、「60日以上前の届出」の義務や「発掘調査の指示による工事の遅延」のリスクなどにより買主から値下げを求められる可能性もあります。
5.まずはプロにご相談を
埋蔵文化財包蔵地の購入にはリスクがあります。しかし、その立地が希望通りの条件を満たしているならば簡単には諦めることができないかもしれません。
埋蔵文化財包蔵地の不動産を購入する場合は、不動産会社にしっかり調査や説明をしてもらい、発掘調査が必要になった場合の段取りや将来売却する際の事など、不安材料を一つずつ解消してから、十分に納得した上で購入を決めた方が良いでしょう。
住建ハウジングが売却に強い3つの理由
- 理由1 東京都内にこだわり続けた揺るぎない実績
- 理由2 物件の魅力を最大限に引き出すノウハウ
- 理由3 業界トップクラスの集客力とネット番組の圧倒的な反響
60秒でカンタン!問い合わせ【無料査定】
査定対象は東京都心部のみとなります
投稿者プロフィール
-
「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。
不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。



 0120-172-111
0120-172-111











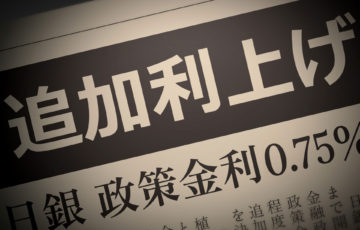








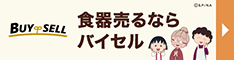








 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説