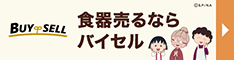働き方の多様化により、テレワークやノマドワーカーなど、自宅を事務所として仕事をする人が増えています。また、弁護士や行政書士など士業を営む方々も、自宅を自宅兼事務所として多く活用されています。この記事では、自宅兼事務所を構える場合のメリット・デメリット、手続き方法、注意点について解説します。自宅で事業をはじめる際の参考にしてください。
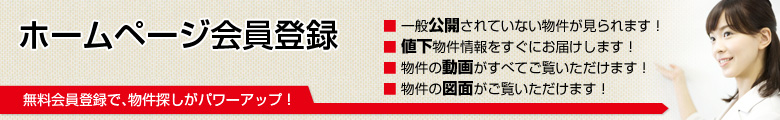
個人事業主か法人か
自宅を事務所として使用する場合、個人事業主の場合と法人の場合で違いがあります。どちらを選ぶかは、事業規模、将来の展望、節税対策など、様々な要素を考慮して決める必要があります。
自宅を事務所として使用する場合の個人事業主と法人の違い
| 区分 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 経費の扱い | 事業に使用した部分の家賃、水道光熱費などを家事按分して経費計上。 | 法人との賃貸借契約を結び、家賃を支払うことで全額経費化可能。ただし、役員個人には不動産所得が発生。 |
| 固定資産税 | 事業に使用した部分の固定資産税を按分して経費計上。 | 法人名義で固定資産税を支払い、全額経費化可能。 |
| 減価償却費 | 事業に使用した部分の建物の減価償却費を按分して経費計上。 | 法人名義で減価償却費を計算し、全額経費化可能。 |
| その他経費 | 通信費、消耗品費など、事業に関連する経費は全額経費計上可能。 | 個人事業主と同様、事業に関連する経費は全額経費計上可能。 |
| 所得税 | 事業所得に対して所得税が課される。 | 法人税が課される |
個人事業主を選ぶ場合、手続きが比較的簡単で柔軟な経営が可能ですが、法人の場合は、法人財産と個人財産でリスク分散ができ責任範囲が限定的で、資金調達も比較的容易になります。また、節税効果も高くなる可能性があります。
自宅を事務所として使用する場合、個人事業主と法人では経費の扱いなどに大きな違いがあります。どちらを選ぶかによって、税金や経営の仕方が大きく変わるため、慎重に検討することが大切です。
自宅兼事務所のメリットとデメリット
自宅兼事務所のメリットとデメリットについて見てみましょう。
【個人事業主と法人共通】
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
経費を計上できるので、節税につながる: 事務所を自宅に設定すると、さまざまな経費を計上できるため、節税につながります。 時間をかけて通勤しなくてもいい: 自宅兼事務所の場合は、当然のことながら通勤が不要になります。 |
経費の計算に少し時間と手間がかかる: 自宅兼事務所の場合、家賃を床面積比で按分したり、電気代や電話代を作業時間で按分したりと、経費計算に手間と時間がかかります。 プライベートと仕事の境目があいまいになりがち: 仕事場と居住スペースが同じになるので、オンとオフの境目があいまいになりがちです。 賃貸物件の場合、契約内容違反になってしまう可能性がある: 賃貸物件の場合には、自宅兼事務所としての用途が認められていない場合があります。 |
【個人事業主の場合】
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
設立が簡単: 手続きが比較的簡単で、迅速に事業を開始できる。 経費の柔軟性: 事業に関連する経費は比較的自由な範囲で計上できる。 税制上の優遇: 青色申告など、個人事業主向けの税制上の優遇措置を受けることができる。 |
責任の重み: 事業の成功・失敗がすべて個人に帰属する。 資金調達: 銀行融資を受ける際に、個人資産の担保を求められる場合がある。 |
【法人の場合】
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
責任制限: 事業の債務は原則として法人財産でまかなわれるため、個人の財産への影響が少ない。 資金調達: 銀行融資など、外部からの資金調達がしやすい場合がある。 従業員雇用: 従業員を雇用しやすく、社会保険の加入など、従業員向けの福利厚生制度を整えることができる。 |
設立・維持コスト: 法人設立には費用がかかり、税理士費用など、維持するための費用も必要となる。 手続きの煩雑さ: 法人設立や経理処理など、手続きが煩雑になる。 二重課税: 法人税と個人に支払われる役員報酬に対する所得税の二重課税が発生する場合がある。 |
自宅を事務所として利用するには?
では、実際に自宅を事務所として使用するためには何をすればいいのでしょうか。
自宅兼事務所として使用する物件を新たに探す場合
不動産会社に、自宅兼事務所として使用できる物件がないか相談をしてみましょう。マンションやアパートなどの集合住宅の場合、法人として利用できるかどうかはケースバイケースです。賃貸契約書やマンションの規約をよく確認し、管理会社に相談することが重要です。また、法人として利用する際には、他の入居者への配慮や、税務上の手続きなど、様々な点に注意する必要があります。
他店が既に入居している物件は、自宅兼事務所としての用途が認められやすいでしょう。
同業他社が入居していないかチェックすることも大切です。
住んでいる自宅を事務所として利用する場合
すでに住居として使用している自宅を利用する場合、自宅住所を事業所の住所として役所に開業届を申請します。
不特定多数の顧客の出入りがある場合や看板の設置などを行う場合には、後のトラブル防止のために、近隣の方々に事前に説明し、了承を得るようにしましょう。
また、賃貸物件を自宅兼事務所として利用する場合には、不動産会社への事前の相談が必要です。相談の際には、用途や看板設置の有無、見込みの来客数など詳細も伝えましょう。
事前の通知なく開業した場合には、契約違反による強制退去という事態にもなりかねません。
なお、法人の場合は法人登記が必要です。登記には、定款の作成、資本金の払込み、登記申請など、いくつかの手続きが必要になります。また、事業の目的に「事務所」と記載する必要があります。
青色申告
自宅を事務所とした場合の税控除を受けるためには、確定申告の際に青色申告が必要です。また、その税控除には以下の要件が必要です。
- その費用が業務の遂行のために直接必要であること
- 必要であった部分の金額が計算できること
青色申告は、毎年2月~3月に確定申告の際に行います。
自宅を事務所にする際の注意点
自宅を事務所として使用する際には、気をつけなければならない点があります。
賃貸の場合には契約条件(物件オーナーの意向)に注意
■ 自宅兼事務所として利用していいか
前述の通り、物件によっては事務所としての利用が認められていない場合があるため、必ず事前に契約書に目を通し、物件オーナーに確認しましょう。
■ 社名や看板などを出してもいいか
自宅兼事務所としての利用については問題がない場合でも、大々的に看板を出したり、表札に社名を掲示したりすることが認められないケースもあります。事業活動について、一つひとつもれなく確認することが重要です。
■ 居住用としての契約になるか、事業所としての契約になるか
物件を新たに契約する場合は、居住用としての契約になるか事業所としての契約になるかについて確認しましょう。
事業所としての契約の場合、敷金礼金が居住用の場合と異なる場合があります。
また、事業所としての契約となった場合、家賃に消費税がかかる場合があります。
| 個人事業主 | 法人 |
|---|---|
|
一般的な賃貸契約と同様、敷金は家賃の滞納や部屋の原状回復費用に充てられます。 礼金は、物件の確保に対する対価として支払うケースが多いですが、近年では不要なケースも増えています。 |
法人契約の場合、敷金は高額になる傾向があります。 礼金については、個人事業主と同様ですが、法人契約の場合、より高額になることがあります。 |
経費計上に注意
経費計上の際に注意する点をご紹介します。
■ 違和感のない按分が必要
家賃や光熱費を必要経費として計上する際の按分については、慎重に行う必要があります。
例えば、比率を「事務所」9に対し「自宅」1など明らかに不自然な按分の設定をした場合には、税務署から脱税の疑いをかけられるケースがあります。
■ 住宅ローンは利息部分に注意
住宅ローンの利息部分は、税制優遇が受けられません。
間違って計上してしまうと、後日税務署から指摘が入りますので、住宅ローン支払い中の持ち家を自宅兼事務所に設定される場合には注意してください。
自宅の設備に注意
個人宅を事業所にする場合は、仕事をするための環境が整っていることも重要です。
■ インターネット環境
インターネットの高速通信環境は不可欠です
。効率的に作業を行うために、無線LAN環境を整えておきたいところです。
■ 電話、FAX環境
近年、携帯電話のみで営業や問い合わせ対応をする方も増えてきましたが、業態によっては電話やFAXがあったほうが業務を行いやすいでしょう。
また、コピーやプリントの機能も備えた複合機を導入すると、業務の効率が飛躍的に向上するケースもあります。
まとめ
自宅兼事務所の最大のメリットは経費を計上できる点です。
家賃や固定資産税、光熱費などについても、必要経費として計上することが可能です。
ただし、物件の契約内容によっては制約が生じてしまう場合もあり、最悪のケースでは退去を命じられるケースもあります。
近年では、IT技術の発達などによりテレワークをはじめとしたさまざまな働き方が可能になっています。
手続き方法や注意点を把握し、ご自身にあった事務所を開設しましょう。
東京で住宅をお探しの方はこちらから
購入者の声も動画配信中です
投稿者プロフィール
- 監修者
-
宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士
1996年より大手不動産デベロッパー勤務。首都圏の新築マンション販売のプロジェクトマネージャーに従事。多くの物件の担当し、引き渡しまで一気通貫で経験。
その後ベンチャー系広告代理店にて不動産系クライアントのインターネット集客の支援を行う。
現在は広告代理業と併せ、老舗不動産会社として地域ニーズに合わせた事業を展開。20年以上にわたり住建ハウジングと共同でマーケティング活動を行う。























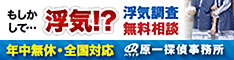










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説