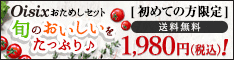住宅購入時に親からの金銭的な支援を受ける際「黙っていても税務署などにバレるのだろうか」と疑問に感じる人は多いでしょう。この記事では税務署が個人間の贈与を把握するケースや、未申告がバレたときにどうなるかについて解説します。贈与税のルールや特例を知って正しくかつ損のない申告を行いましょう。
住宅購入で親からの支援はバレる?
住宅購入時に親が子に「購入資金を援助してあげよう」というのはよくある話です。この資金援助は税法上「贈与」にあたります。贈与とは、個人から個人に無償で資産を譲渡することを指します。この贈与が110万円を超えると超えた分に対して「贈与税」がかかります。
贈与税を払わないために援助を黙って受ければバレないのでは?と考える人もいるでしょう。しかし、税務署は金融機関の記録や不動産の登記情報などから、個人間の資金援助やお金の流れを把握できる仕組みを持っています。そのため基本的には贈与を受けた事実は黙っていてもバレると考えましょう。
現金を手渡しするなら親からの支援はバレない?
金融機関での取引を避けて、手渡しなら税務署にバレないと考える人もいるかもしれません。しかし、たとえ手渡しであっても住宅購入の契約書や決済の記録が残るため資金の出所を疑われることは避けられないでしょう。
特に税務署は住宅購入などの大きな金額の動きを重点的にチェックしています。過去の残高や支出入と住宅購入の記録から「住宅購入資金を親に援助してもらった」と推察するのは難しいことではありません。
数回に分けて振り込んでもらえば親からの支援はバレない?
振込を数回に分けても、金融機関の振込記録や口座の動きは税務署に把握されます(つまりバレます)。贈与税は年単位で課税対象を判断しているため、1年間に受け取った金額の総額が110万円を超える場合、贈与税の対象とみなされるでしょう。
では、年をまたいで110万円以下を毎年贈与するケースはどうでしょうか。このケースは基本的には贈与税の対象とは見なされません。 ただし、税務署が「1000万円の贈与を10年に渡り分割している」などと判断した場合は「定期贈与」と見なされ一括課税されるリスクがあります。対策としては毎回の贈与ごとに贈与契約書を交わすといった方法があります。
住宅購入で親からの支援がバレるケース

住宅購入で親からの支援がバレるケースを解説します。どのような情報から支援が発覚するのか理解しておきましょう。
相続税調査から発覚するケース
相続税調査では、被相続人の資産や過去の資金移動が詳細に調べられます。その中で使途不明の大きな出金が見つかった場合、生前贈与の可能性が疑われて支援がバレてしまうことがあります。
通常の税務調査と比較して相続税調査はより詳細に行われる傾向にあるため、発覚しやすいケースといえるでしょう。
不動産登記から発覚するケース
不動産を購入すると法務局で所有権の登記手続きを行いますが、この登記情報は税務署もアクセスが可能です。記録から、自己資金や収入に見合わない高額な住宅を購入していることがわかると、資金の出所が調査されます。
たとえば、資金の出所が不透明な中で、住宅購入と同時期に親の口座残高が大幅に減っていると、贈与の事実が発覚する可能性が高いでしょう。
法定調書から発覚するケース
法定調書とは、税務署が個人の所得や資産を把握するための重要な資料です。給与所得や源泉徴収票など、支払いに関する情報が記載されており金融機関や雇用主などが税務署に対して直接提出することが義務付けられています。
税務署は法定調書を通じて個人の収入を把握できるため、実際の申告内容と法定調書の金額にズレがあると不審点があるとして調査を行う場合があります。調査の過程で親の資金移動が見つかると贈与を隠していたと見なされる可能性が高まるでしょう。
親からの支援が贈与とみなされ、申請をしなかった場合はペナルティが課せられる
親から住宅購入の支援を受け、その支援が贈与とみなされた場合、未申請だとペナルティが課されます。贈与税の申告を怠ると本来支払う税額に加えて、無申告加算税や過少申告加算税、重加算税、延滞税などを追加で払わなければなりません。
それぞれのペナルティの税率は以下の通りです。
| 無申告加算税 | 10%(50万円を超える部分には5%加算) |
|---|---|
| 過少申告加算税 | 15%(50万円を超える部分には5%加算) |
| 重加算税 | 35% or 40% |
| 延滞税 | 7.3%or特例基準割合+1%の低い方 |
上記のペナルティの中でも、意図的に税金を逃れようとして隠蔽などを行った場合に課される重加算税は特に悪質と認定され、高い税率の追徴課税が徴収されます。親からの支援を隠ぺいしてもバレる可能性が高い上にペナルティが重たいため、正しい手続きを踏むことが重要です。
親に住宅ローンを代わりに払ってもらった場合は贈与にならない?
住宅ローンを親の代わりに支払ってもらうことも原則として贈与としてみなされます。税法上、年間110万円を超える贈与を受けた場合は贈与税の申告が必要です。
親が住宅ローンを肩代わりする金額が上記の基準を超えた場合には確定申告を行い、贈与を申告しましょう。
親からお金を借りたことにすれば贈与にならない?
住宅購入の際に親からの支援を「借りた」ことにすれば贈与に当たらないと考える方もいるかもしれません。確かに「借用」であれば贈与税はかかりません。しかし、それが本当に「借用」であるかどうか税務署は厳しくチェックしています。
そのため形だけ借りるのではなく、以下のポイントを満たす実質的な借用契約を成立させることが重要です。
- 金銭消費貸借契約書(借用書)を作成する
- 金利を設定する
- 実際に親に返済した記録を残す
返済した記録は親に銀行振込で返済するなどの方法をとるとよいでしょう。金銭消費貸借契約書(借用書)には返済計画なども記載するとよいですが、収入の面から計画を全うする能力がないと見なされると贈与と判断されることもあります。
住宅購入で親からの支援を受ける時は特例や制度を活用しよう
年間110万円を超える贈与には贈与税が課されますが、住宅購入が理由であれば特例や制度を活用することで税負担を軽減できることがあります。
たとえば、「住宅取得資金贈与の非課税の特例」があります。これは住宅購入資金のために親から贈与を受けたと認められた場合、一般の住宅購入で最大500万円、省エネ住宅の購入で最大1000万円までの贈与が非課税になる特例です。
さらに、贈与税には110万円を超える贈与に対して課税される「暦年課税」制度の他に「相続時精算課税」という制度もあります。「相続時精算課税」を選択すると110万円の控除のうえにさらに2500万円までの非課税枠が上乗せされます。贈与した人が死亡して相続が発生したときに、贈与された金額と相続する金額を合わせたものに相続税が発生する仕組みです。税の支払いが先送りになるだけと思いがちですが、贈与税と相続税は税率が異なるため贈与額によっては節税できるケースもあります。
住宅購入で親から支援を受ける際に使える特例や制度に関しては、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
親からの住宅購入の支援に関するよくある質問
Q. 住宅購入で親からの支援に贈与税はいくらかかる?
A.
贈与税は贈与を受けた金額から基礎控除額の110万円を引いた金額に対して、所定の税率をかけて算出します。税率は贈与金額が高額になるほど高くなる仕組みです。たとえば贈与額が200万円以下なら「10%」、200万円〜300万円以下であれば「15%」と段階的に高くなります。
Q. 住宅購入で親からの支援を受けるときの手続きは?
A.
贈与を受けた金額が110万円を超える場合にはその翌年の3月に確定申告し、贈与を受け取ったことを申告しましょう。申告後に所定の贈与税を支払うことで手続きが完了します。各種特例や制度を活用する場合にも確定申告が必要です。
住宅購入で親からの支援を受ける時は正しく申告しよう!
住宅購入で親から支援を受けた場合は贈与に該当するため、贈与税のルールを必ず把握しておきましょう。確定申告が必要な場合を理解し、特例や制度で税負担を軽くする選択肢があるかも確認する必要があります。親からの支援は基本的にバレると思い、正しく手続きをすることが重要です。住宅購入という人生の大きなイベントを安心して進めるためにも、贈与に関して不明な点がある場合は専門家に相談するとよいでしょう。
東京都の不動産購入・売却・売買の相談に関しては、住建ハウジングを利用するのがおすすめです。住建ハウジングでは、豊富な経験と実績を活かし、お客様一人ひとりのニーズに合わせた丁寧なサポートを提供しています。お問い合わせや詳細については、下記のリンク先から公式ホームページをご確認ください。不動産に関するさまざまな情報発信も行っています。
投稿者プロフィール
- 監修者
-
宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士
1996年より大手不動産デベロッパー勤務。首都圏の新築マンション販売のプロジェクトマネージャーに従事。多くの物件の担当し、引き渡しまで一気通貫で経験。
その後ベンチャー系広告代理店にて不動産系クライアントのインターネット集客の支援を行う。
現在は広告代理業と併せ、老舗不動産会社として地域ニーズに合わせた事業を展開。20年以上にわたり住建ハウジングと共同でマーケティング活動を行う。






















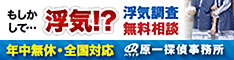
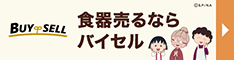










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説