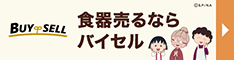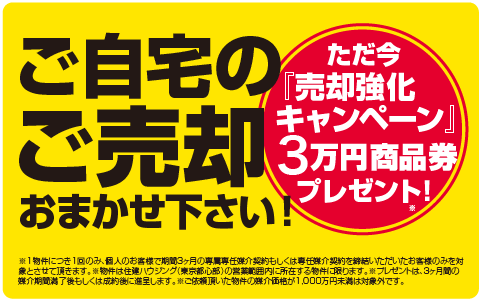不動産を売却した際には、原則として確定申告が必要です。しかし、すべてのケースで申告が必要になるわけではなく、一定の条件を満たせば確定申告が不要となる場合もあります。この記事では確定申告が不要になる条件も含め、確定申告のやり方や流れを詳しく解説していきます。複雑に感じやすい税務対応を正しく理解し、後悔のない売却につなげましょう。
不動産売却時に確定申告が不要なケースとは?
不動産売却時に確定申告が不要になるケースは、2つあります。それぞれの条件を知り、自分があてはまるか確認をしましょう。
譲渡所得(売却益)が発生せず特別控除も受けない場合
不動産売却時に譲渡所得(売却益)が発生しなかった場合には、基本的に確定申告は不要です。譲渡所得とは、土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を売ることで得た利益で、以下の計算式で算出します。
譲渡所得=売却による収入金額-(取得費+譲渡費用)
この値がゼロまたはマイナス(損失)になると、申告すべき所得はない状態と判断されるため、確定申告は不要です。また、不動産売却時にローンの繰延や税の特別控除を受けない場合にも、確定申告は必要ありません。
参考:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
譲渡損失とは、「売却による収入-(取得費+譲渡費用)」がマイナスの状態になることです。損失が発生している場合、確定申告は不要ですが、行った方がお得になるケースがあります。
一定の条件を満たした場合、不動産売却の譲渡損失と、事業所得や給与所得などの他の所得との合計を税対象にする損益通算が適用できます。たとえば、給与所得が500万円で、譲渡損失が−100万円あった場合、損益通算が適用されると所得の総額は500万円-100万円=400万円となり、税金を安く抑えられます。
さらに、損益通算をしても控除しきれない損失については、譲渡年の翌年以後3年間に亘り、繰り越して控除ができます。
参考:国税庁「No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合」
譲渡所得(売却益)と他の所得の合計が20万円以下で年末調整を行っている
不動産売却による譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下に加え、1つの会社に勤務する給与所得者で年末調整を行なっているにあてはまる場合、確定申告は不要です。
この他の所得とは、「配当所得」や「雑所得」のことで、給与所得や退職所得は除きます。こちらの対象は給与所得者のみのため、事業所得を得ている自営業者や個人事業主の方は対象外です。
確定申告が必要なケース
不動産売却時に確定申告が必要なケースも2つあります。何が基準となるのかをしっかりと把握しておきましょう。
譲渡所得が発生する場合
不動産の売却によって譲渡所得が発生する場合、確定申告が必要です。譲渡所得は「売却による収入金額-(取得費+譲渡費用)」の計算式で算出します。会社に勤務して給与所得を得ている方も、不動産売却で譲渡所得が発生した場合には、確定申告が必要です。
譲渡所得には、最高50万円まで特別控除が適用されます。しかし、土地や建物、株式等の売却による譲渡所得は控除の対象外です。そのため、不動産売却による譲渡所得が50万円以下の場合でも確定申告は必要です。
参考:国税庁「No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」
不動産売却の特別控除を受けたい場合
不動産売却時に特別控除を受けたい場合には、確定申告が必要です。特別控除を受ける場合、譲渡所得の計算は通常とは異なり、【売却による収入金額 -( 取得費 + 譲渡費用)-特例控除額】となります。
譲渡所得がゼロまたはマイナスの場合でも、特別控除を受けるときは、確定申告をしなければならないので、注意してください。
●一定の要件を満たす場合の最高3,000万円の特別控除
●10年以上所有する自宅を売却する際の軽減税率適用
不動産売却・いつ確定申告する?

確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の期間に行います。ただし、この期限は年によって日にちがずれることもあるので注意が必要です。
たとえば、その年の期限の日が休日のときは、税務署や金融機関もお休みのため、その翌平日が期限となります。確定申告を行う場合は、その年の申告期間がいつからいつまでなのか、事前にチェックしておきましょう。
期日までに確定申告しないとどうなるか
譲渡所得が発生しない場合は、期日までに確定申告をしなくても、とくになにも起きません。しかし、国税庁から「お尋ね」と呼ばれるアンケートが送られてくることがあります。
国税庁は、登記の移動記録を通じて土地の売買があったことを把握しているため、譲渡所得を得た可能性がある人に対して、アンケートを行います。ただ、実際に譲渡所得がない場合には、事実を簡潔に記載すれば問題ありません。
譲渡所得がある場合には、期日までに確定申告をしないと、ペナルティとして追徴課税が科されます。原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%のペナルティが加算されます。
確定申告の期日を過ぎた場合でも、1ヶ月以内に申告すれば、ペナルティが加算されることはありません。ただし、ペナルティとは別に延滞税が徴収されるので注意してください。
不動産売却・確定申告の方法
不動産を売却した場合の確定申告は、どのような方法で行えばよいのでしょうか。ここでは、確定申告の方法について解説します。ぜひ、自分に合った方法を見つけてください。
電子申告・納税システム(e-tax)で申告する
電子申告・納税システム(e-tax)は、ネットを使って確定申告を行う方法です。パソコンやスマホなどの端末とネット環境があれば利用できるため、近年主流になっています。
e-taxのメリットは、自宅で確定申告書の作成と提出が完結する点です。税務署に行く必要がなく、好きな時間に手続きができます。デメリットとしては、分からないことを確認しづらい点や、ICカードリーダーなど利用環境を整える必要がある点です。
税務署に行き窓口で申告する
税務署に行き窓口で提出する方法は、職員にフォローをしてもらえるのが最大のメリットです。不明点は直接質問ができますし、書類の不備をチェックしてもらえるので、正しく確定申告できます。
一方で、確定申告の時期には、税務署の窓口が非常に混雑するため、手続きを行うのに長時間待たされる可能性があるのがデメリットです。
書類を郵送して申告する
郵送提出は、作成した確定申告書を郵送で提出する方法です。郵便ポストに投函するだけで提出が完了する手軽さがあります。窓口で待たされることも、ネット環境を整える必要もありません。
しかし、書類に不備があった際に、やり直す手間が発生するため、締切に余裕がある場合にのみ、おすすめです。また、郵送の費用かかるので注意しましょう。
税理士に依頼する
税金のプロでもある税理士に、確定申告の代行を依頼するのも一つの選択肢です。プロに全てお任せできるため、自分でやるよりも時間の節約にもなり、正確かつ信頼性の高い申告ができます。初めて確定申告をする方や、確定申告の仕組みを理解できない方は、プロに相談してみましょう。
しかし、税理士への依頼には費用がかかるため、一定の所得がある場合にのみ利用するのがおすすめです。税理士への依頼費用は売上などによっても異なりますが、一般的な相場としては、5万円〜10万円と言われています。
不動産売却の確定申告の流れ

不動産売却した場合の確定申告の流れを解説します。各ステップを1つずつ確認して、確定申告のやり方を把握していきましょう。
1.確定申告に必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類には、税務署で取得する書類と、自分で用意できる書類の2種類があります。 提出に必要な書類は、基本的にご自身で揃える必要がありますので注意しましょう。
| 税務署で取得する書類 | 自分で用意する書類 |
|---|---|
|
●確定申告費用紙 |
●売却時や購入時の売買契約書 ●登記事項証明書 ●仲介手数料や登記費用などの領収証 ●各種特例に必要な書類 |
確定申告書用紙は税務署で入手、または税務署の公式ホームページからダウンロードできます。 なお、確定申告用紙には申告書「A」と「B」がありますが、不動産所得の場合は「B」の用紙が必要です。
譲渡所得内訳書は、譲渡した不動産の概要や売却金額などを記載する書類です。 こちらも税務署で入手、または税務署の公式ホームページからダウンロードできます。
売買契約書は不動産を購入した際の写しと、売却時の写しを準備しましょう。
登記事項証明書は、売却した不動産の所在地や所有者が記載された書類です。 こちらは不動産の所在地を管轄する法務局で取得できるほか、法務局が運営するサイトから申請することも可能です。
売却時に支払った仲介手数料や登記費用などの経費の領収書の写しを準備しましょう。 また測量費など、売却準備に要した費用についても課税譲渡所得額を計算する際の必要書類となります。売却するためにかかった費用については、もれなく領収書を保管しておきましょう。
その他、不動産売却の特例控除を受けたい場合はそれぞれの特例にそって必要な書類があるため、よく確認しておきましょう。
2.譲渡所得を計算する
まずは売却に際して譲渡所得(売却益)が発生したのかを確認しましょう。 譲渡所得の計算方法は下記のとおりです。
譲渡所得=売却による収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得税の納税額は、この譲渡所得または課税譲渡所得に対して税率をかけて計算されます。 なお、不動産の所有期間(長期譲渡所得か短期譲渡所得)によって、適用する税率が異なる点に注意が必要です。 下記のように所有期間が5年を超えるかどうかで適用する税率が変わります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 (所有期間が5年を超える不動産) |
15% | 5% |
| 短期譲渡所得 (所有期間が5年以下の不動産) |
30% | 9% |
※確定申告の際には所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付。
出典:国税庁ホームページ「土地や建物を売ったとき」
3.確定申告書を作成する
確定申告書には、ご自身で必要事項などを記入して作成します。 この確定申告書は、最寄りの税務署または国税庁のホームページから入手することができます。 あまり慣れない作業で大変ですが、国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」でパソコンを使って必要事項を記入し簡単に作成することもできるので、ぜひ利用してみてください。
4.確定申告書や必要書類一式を税務署に提出
作成した確定申告書や必要書類は、税務署の窓口に提出するのが一般的です。 ただし申告期間中、特に期間終盤になると窓口は大変な混雑が予想されます。そんなときは、窓口ではなく郵送や、電子申告・納税システム(e-tax)を使って提出することが便利です。
不動産売却(マイホーム売却)による特別控除の特例
不動産売却(マイホーム売却)では、税金の特別控除が受けられる場合があります。条件にあてはまり、特別控除を受ける場合は確定申告が必要です。自分の場合があてはまるのか、概要や適用条件を詳しく見ていきましょう。
3000万円特別控除の特例
自宅を売却して譲渡所得が発生した場合、一定の要件を満たせば最高3,000万円の控除を受けられる可能性があります。 たとえば、譲渡所得(売却益)が5,000万円発生した場合、そこから3,000万円を差し引いた残りの2,000万円が課税譲渡所得です。したがって、この2,000万円に税率をかけて計算された金額が譲渡所得税の納税額となります。
ただし、3,000万円の特別控除の特例は、買換え特例や、住宅ローン控除など他の特例との併用ができない場合もあるので注意が必要です。
10年越所有の軽減税率の特例
自宅売却の場合は、さらに売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているときは、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に軽減税率の特例が受けられます。 この特例は、要件が合えば3,000万円の特別控除との併用も可能です。
| 課税長期譲渡所得 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 10% | 4% |
| 6,000万円越えの部分 | 15% | 5% |
※確定申告の際には所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付。
特定の居住用財産の買換えの特例
不動産の譲渡価額が1億円以下かつ売却年の1月1日時点で所有期間10年超、居住期間10年以上の自宅(居住用財産)を売却した場合、買換えに対する特例が受けられます。特例を適用させると、自宅を売却した年の前年から翌年までの3年の間に自宅を買い換えた場合に、譲渡益の課税の繰り延べができます。
ただし、こちらの特例は、上記の「3,000万円の特別控除の特例」や「軽減税率の特例」とは選択適用となるため、併用はできません。
不動産売却時の確定申告が必要か不要かを判断しよう!
不動産売却で確定申告が必要かどうかは、「譲渡所得が発生しているか」、「特別控除を適用するか」の2点を基準に判断しましょう。慣れない方にとって確定申告はハードルが高く感じられますが、条件によっては税金を軽減できるケースもあります。不動産売却で後悔しないためにも、やり方や仕組みを把握しておくのがおすすめです。
東京都の不動産購入・売却・売買の相談に関しては、住建ハウジングを利用するのがおすすめです。豊富な経験と知識をもとに、一人ひとりに合わせた丁寧なサポートを行っています。お問い合わせや詳細については、下記のリンク先から公式ホームページをご確認ください。不動産売却に関するさまざまな情報も随時発信しています。
投稿者プロフィール
-
「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。
不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。
























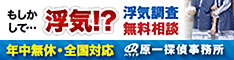










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説