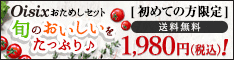毎年春になると気が重い小学校のPTA役員決め。
PTA役員と言えば「なんとなく忙しそう」「人間関係が面倒そう」…といった印象があるので、なるべくなら避けたいと思ってしまいますよね。
実際には、PTAのお仕事とはどんなことをするのでしょうか?
ここでは、具体的な仕事内容や引き受けるおすすめのタイミングなどを紹介していきます。
PTAって何をするの?
PTAとはParent-Teacher Association(親と教師の協同組織)の略で、学校と家庭が協力して子どもの教育に関わっていくために作られた団体で、現在、全国のほとんどの小・中・高校にPTAがあります。
PTAの役割は学校ごとに多少の違いはありますが、一般的には、学校行事への協力や保護者と学校との情報共有、保護者同士の親睦などを目的に運営されています。
役員はどうやって決める?
PTAの役員や委員の選出については、学校ごとに細かなルールが制定されていますが、多くの学校では次のような流れで役員や委員を決めているようです。
立候補者を募り、出なければ多くの場合、抽選やじゃんけんなどで委員を選出。
選出に当たっては、小学校ごとに以下の様なルールが定められています。
● 学校に通う子ども一人につき、必ず一回は何らかの役員・委員を担当する
● 役員・委員によってポイントを定め、子どもが学校に通う間に必要ポイント分の役員・委員活動を行う
自分が通う小学校のルールについては、事前に先輩ママから情報収集しておくと安心ですよ。
断ることはできるの?
フルタイムで働いている人や、人前に出るのが苦手な人などは、「できればPTA役員を断りたい…」と考えている人もいるでしょう。
役員や委員の選出にあたっては、「妊娠中」「0歳児を育児中」「病気での療養中」などやむを得ない理由がある場合は選出から免除する、というルールが定められている小学校が多いようです。
それらに該当する場合は役員・委員の選出から外されます。
免除事項に含まれない人でも、「親の介護をしている」「シングルマザー・ファーザーである」といった個人的な事情を事前に相談しておくと、他の会員の同意が得られれば免除されることもあるようです。
「仕事をしているから」という理由で断ることができるのかということが気になりますが、最近ではパートやフルタイムで仕事をしている保護者が多いので、「仕事をしている」という理由だけでは、PTA役員を免除してもらうことは難しいでしょう。
実際に仕事をしていて平日の活動が難しそうな場合は、「土日の活動は参加する」「書類作成など自宅でできる仕事は受け持つ」といった形で、できる範囲で協力していくという姿勢を示すことが大切です。
基本的にPTAはどの委員会も複数名で運営しているので、仕事をしている人、していない人など様々な事情がある人が助け合って活動をしています。
共働きの保護者が多い現代、「仕事をしているから」を免除理由に含めてしまうと、言うまでもありませんが特定の方にばかり負担がかかってしまいますよね。
「私は仕事をしてるから」と頭ごなしに断るのではなく、「できる範囲で協力する」姿勢を示し、他に引き受けてくれる人がいる場合は、感謝する気持ちを持つことが大切です。
役員の種類や仕事内容

ところで、皆さんが一番気になるのは「実際にPTAの役員・委員はどんなことをするの?」ということかもしれませんね。
PTA役員には大きく分けて、PTA役員全体をまとめる会長、副会長、書記などの「本部役員」と、様々な活動ごとに設けられたクラス委員、広報委員などの「運営委員会」の2つの組織があります。
本部役員
本部役員とは、PTA役員やその他の委員会全体を取りまとめる組織です。
各委員会の予算配分や、学校との連絡、行事への出席、市町村のPTA協議会への出席など、校内外のPTA活動の連絡・調整を行っています。
【本部役員の役職と活動内容】
| 役職 | 内容 |
|---|---|
| 会長 | 学校行事や式典での挨拶、地域のPTA協議会への出席など |
| 副会長 | 会長の補佐、学校との連絡調整、委員会間の連絡・調整など |
| 書記 | PTAからの文書作成、役員会の議事録作成など |
| 会計 | PTA全体の会計管理、各委員会への予算配分、管理など |
| 会計監査 | PTA会計の監査、総会での監査結果報告など |
運営委員会
運営委員会は、親睦会や校区パトロールなど個々の活動ごとに専門の委員会が設けられています。
設置されている委員会は学校によって様々ですが、主な委員会は以下の通りです。
【専門委員会の種類と活動内容】
| 役職 | 内容 |
|---|---|
| クラス(学級)委員会 | 親睦会の企画・開催、懇談会の司会など |
| 広報委員会 | PTA広報誌の編集・発行、PTA活動のブログ更新など |
| 文化委員会 | PTA向け講演会や講習会の企画・開催 |
| 地区(校外)委員会 | 児童の登下校の見守り活動、校区パトロールなど |
| 環境委員会 | 校内・近隣地域の清掃美化活動 |
| ベルマーク委員会 | ベルマークの回収 |
| 推薦(指名)委員会 | 次年度本部役員の選出(11月頃から活動開始) |
やるならばいつがいい?
「低学年のうちは立候補が多い」「6年生のクラス委員は負担が大きい」など様々な噂が飛び交うPTA役員。どのタイミングで引き受けるのがいいのでしょうか?
低学年、高学年それぞれのメリットとデメリットを見てみましょう。
【低学年】
メリット
● 高学年のママや経験者に色々と教えてもらえる
● ママ友ができて学校について色々と情報が得られる
● 早いうちに済ませておくと気分がラク
デメリット
● 知らない人が多いと打ち解けられるか不安
【高学年】
メリット
● 学校や保護者に知り合いが多いので活動がしやすい
● 経験者が多く主体的に関われるのでやりがいがある
● 6年生は学校行事も多く先生方と親しくなることが出来る
デメリット
● 高学年の方が委員長や副委員長を頼まれやすい
● 子どもの受験と重なると忙しい
● 6年生は卒業式後の謝恩会を企画しなければならない場合がある
本部役員に関しては、PTA全体を取りまとめることになるので、できれば何らかの運営委員会を経験してからの方がいいでしょう。
特に会長や副会長は仕事も多く、時間も取られるので、家庭や仕事などにある程度余裕があることが必要です。
本部役員は負担が大きい分やりがいも大きく、PTA活動の醍醐味を味わえる役職でもあります。
上手に活動を続けていくためのポイント

実際に役員や委員になった場合、「上手くやっていけるかしら・・・」と不安を抱く方も多いと思います。
PTA活動を上手く進めるためのポイントを3つ挙げてみます。
できることとできないことをはっきり伝える
役員や委員になった方の中には、仕事をしている方、人前に出るのが苦手な方など、様々な事情を持った方も多いですよね。
不安を抱えたまま活動を始めるのは大変なので、最初に「平日の日中は基本的に参加できない」「パソコンが苦手」など、自分のできないこと、苦手なことをはっきり伝えておきましょう。
また、できないことを伝えるだけでなく、「自宅でできる書類作成は引き受けます」「土日なら時間が取れます」という風に、「これならばできる」という前向きなことも伝えることも大切です。
PTAは保護者と学校によるボランティア組織です。
それぞれができる範囲で分担して活動を行うことが基本なので、無理をする必要はありません。
また、それぞれに得意不得意があると思うので、自分の得意なことを活かし、苦手なことは遠慮なく他の人に任せると気分が楽になりますよ。
PTA役員の経験者に頼る
PTAの役員や委員は、年度ごとに人員が入れ替わりますが、毎年何人かはPTA経験者が含まれています。
わからないことはどんどん経験者に聞いて教えてもらいましょう。
また、委員会ごとに前年度の活動内容の記録が残っていたり、年度初めに引き継ぎの時間が設けられていたりするので、基本的には前年度に従って活動をすれば大丈夫です。
たくさんのママ友を作る!
くじ引きやじゃんけんなどで仕方なく選ばれた方もいらっしゃるかもしれませんが、他の保護者も立場は皆同じです。
縁あって役員や委員に選ばれたのですから、いつまでもくよくよせずに、この機会を活かしてたくさんのママとお友達になりましょう!
送迎が必要な幼稚園と違い、小学校に入ると他の保護者と顔を合わす機会はぐんと減ります。
PTA活動を通じて近所のママや、違う学年のママと知り合いになることは、学校のこと、子どもの習い事のことなど、様々な情報を得るチャンスです。
小学校生活を安心して送るために、ママ友からの情報はとても有益なのです。
大変だけれどメリットもたくさんあるPTA
「色々と面倒そうだし、できればやりたくないPTA」・・・多くの人がそう感じているにもかかわらず、経験した人に話を聞くと、意外と「やって良かった」という人も少なくありません。
PTAの役員や委員になると必然的に学校に足を運ぶ回数が増えますが、先生方と繋がりができることで、学校での子どもの様子を知る機会も増えます。
また、PTAを通じて知り合ったママ友は、学校のこと、子育てのこと、色々な情報を教えてもらったり相談したりできる貴重な仲間。
PTA役員を引き受けることは、安心して小学校生活を送るためにきっと役立ちますよ。
購入者の声も動画配信中です
投稿者プロフィール
- 「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや住まいに関する情報を発信するWEBサイトです。1977年創業の不動産仲介会社住建ハウジングが運営しています。


















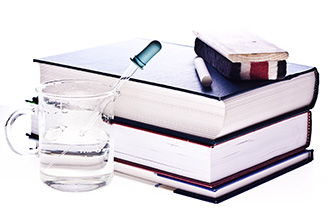




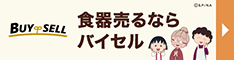










 不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について
不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について
不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説
不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説